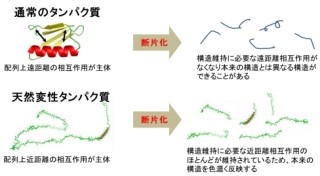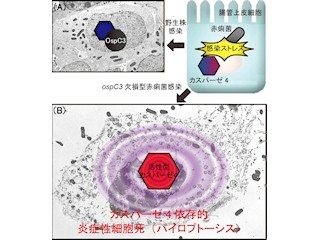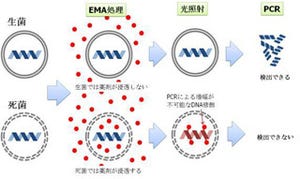東京大学は1月18日、亀田メディカルセンター、富山大学などとの共同研究により、2011年4~5月にある焼肉チェーン店で生肉を食べた人々が腸管出血性大腸菌「O-111」による食中毒を発症した事例を分析することにより、同菌による脳症の臨床症状の特徴と、ステロイドを用いたその新しい治療法の効果を明らかにしたと発表した。
成果は、東大大学院 医学系研究科 国際保健学専攻 発達医科学分野の水口雅 教授が研究代表者を務める、厚生労働科学研究(難治性疾患克服研究)急性脳症研究班に所属する、亀田メディカルセンター小児科の高梨潤一博士、富山大 医学部附属病院小児科の種市尋宙 博士、富山県衛生研究所の佐多徹太郎所長が研究代表者を努める厚生労働科学研究(特別研究)O-111食中毒研究班、国立感染症研究所感染症情報センターの岡部信彦・前センター長らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、1月17日付けで「Neurology」誌オンライン版に掲載された。
過去数十年にわたり、日本および世界の各地で感染の集団発生事例が繰り返されてきたO-157やO-111。これらに代表される腸管出血性大腸菌は、汚染された食材や井戸水などを介して経口感染し、それらの菌が産生した「志賀毒素」により、下痢は腹痛などの「大腸炎」を発症してしまう(血便を伴うような場合もあり、その場合は「出血性大腸炎」と呼ばれる)。志賀毒素は、一部の赤痢菌なども産生する毒素タンパク質で、「ベロ毒素」と同義だ。ヒトの細胞においてタンパク質合成を阻害する作用を有する。
また大腸炎患者の一部(数~20%)は、「溶血性尿毒症症候群」を併発することがあり、この場合は急性腎不全、溶血性貧血、血小板減少などの症状を伴い、予断を許さない状態だ。ただし現代医学では、急性腎不全に対しては輸液や透析の、溶血性貧血に対して輸血などの集中治療により救命可能である。
それに対し、溶血性尿毒症症候群のさらにごく一部(数%)の患者が併発するのが「脳症」で、こちらは非常に危険だ。正式には「急性脳症」と呼ばれ、けいれん、昏睡とほかのさまざまな神経症状を伴う。脳内には炎症がないのに広範囲の脳浮腫をきたし、脳機能障害(意識障害)を呈してしまうのである。
急性脳症は一般的にはインフルエンザなどのウイルス感染による症例が多いが、腸管出血性大腸菌などの細菌感染もあり、O-157やO-111などの食中毒は軽く見てはならない。この脳症に関しては有効な治療手段が現代医学では乏しいため、死亡に至る例も決して少なくなく、実際に腸管出血性大腸菌による死亡例の大多数の死因が脳症となっている。よって、脳症の治療法開発は急務となっているというわけだ。
2011年4~5月にかけて、ある焼肉チェーン店で生肉(ユッケなど)を食べた人々がO-111に感染して食中毒を発症し、富山県を中心に患者が多発したことを覚えている人も多いだろう。それで、好物のユッケが食べられなくなったなどと、嘆いた人もいたはずだ。だが、その食中毒は86名が大腸炎を発症し、うち34名が溶血性尿毒症症候群、うち21名が脳症を併発する事態となった。しかも5名が死亡するという大変な事態に発展したのである。5名の死因は前述したように脳症だった。この非常事態を受けて研究チームは、連携してこれらの患者の臨床データを集積、解析し、脳症の臨床症状の特徴を明らかにすると共に、脳症に対する新しい治療法の効果の調査を実施したのである。
今回の事例の特徴はまず、溶血性尿毒症症候群や脳症を合併する重症患者の割合が、大腸炎患者の中でそれぞれ40%、24%と過去の事例に比して著しく高いことだ。これは最初に「ごく一部」と説明したにもかかわらず、今回の総感染者数に対して各重症患者の人数からわかってもらえることだろう。
脳症を発症した21名の男女比は、男性が6名、女性が15名で、小児は10名、成人は11名だった。死亡した5名は大腸炎から脳症発症までの時間が短く、脳浮腫が急激に進行して死に至ったという。また、死亡した患者の中にはステロイド治療を受けた者はいなかった。
これに対し、脳症に感染した患者の内生存した16名中、15名は後遺症なく回復している。回復した者の内11名がステロイド治療の1種「メチルプレドニゾロン・パルス療法」を受けていた。メチルプレドニゾロンは副腎皮質ステロイドの1種で、パルス療法とはステロイドを短期間に集中的に大量に投与する方法のことをいう。
今回の回復例(15例)と死亡ないし後遺症例(6例)を比較した結果、脳症発症までの時間、腎機能の指標で腎障害(急性腎不全)で上昇する「血清クレアチニン値」、メチルプレドニゾロン・パルス療法の施行に関して統計学的に有意な差が検出されたのである。これらの結果から、脳症に対するステロイド治療の有効性が示唆されたというわけだ。
ステロイドには、「炎症性サイトカイン」の過剰な作用を抑制する効果がある。炎症は感染などの有害な刺激に対する体の反応のことで、サイトカインは細胞間でやり取りされる多様な生理活性を持つタンパク質の1種のことである。炎症性サイトカインは炎症を強め、発熱、組織の腫れ(浮腫)、機能障害などの症状を引き起こす特徴がある。
実は、これまでインフルエンザ脳症などでは、炎症性サイトカインの病的意義が解明され、ステロイド治療が広く行われてきていた。これに対し腸管出血性大腸菌による脳症では、長年にわたって志賀毒素が最重要視されてきた関係で、同毒素を除去する試みはあったが、ステロイド治療は行われてこなかったという経緯がある。
ところが近年の日本の研究で、腸管出血性大腸菌脳症患者の血液でも炎症性サイトカインが増加しているという重要な事実がわかってきたことから、ステロイド治療も行われるようになってきたというわけだ。今回のO-111集団食中毒事例で脳症患者の治療にあたった種市博士らは、この情報に基づいて、ステロイドなどの炎症性サイトカインを抑制する治療を2011年5月から積極的に導入。その結果、同年4月中に脳症を発症した患者(ステロイド治療を受けなかった)に比し、5月になってから発症した患者(多くがステロイド治療を受けた)の治療成績は、際立ってよくなったというわけである。
今回の研究により、ステロイド治療は腸管出血性大腸菌の脳症における有効な治療法として有望な候補であることが明らかとなった。今後の研究を通じて、より確実性の高い証拠を積み重ねてゆく必要があるとしている。