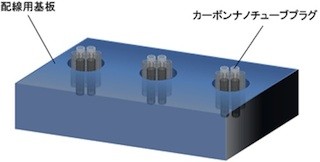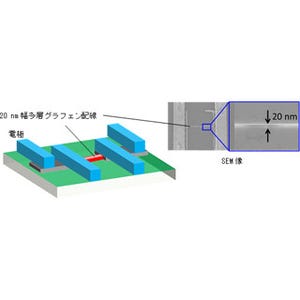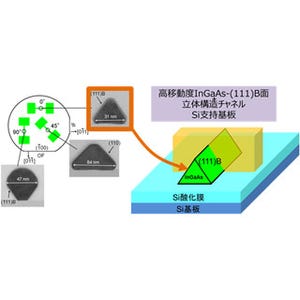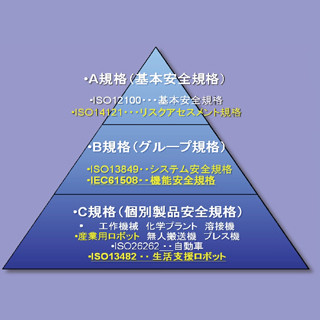産業技術総合研究所(産総研)は12月12日、検出対象のバイオ物質に付着させた蛍光標識からの発光信号を表面プラズモン共鳴励起蛍光増強(SPRF)機能によって強めて、対象バイオ物質の高感度検出ができるV字型の断面を持つマイクロ流路型センサ(V溝バイオセンサ)チップを開発したと発表した。
同成果は、同所 電子光技術研究部門 光センシンググループの藤巻真研究グループ長、フレキシブルエレクトロニクス研究センター 先進機能表面プロセスチームの野村健一研究員、福田伸子主任研究員らによるもの。詳細は、英国科学雑誌「Nature Communications」に掲載された。
近年、様々な疾患に起因して体内に発生するバイオマーカーが特定されてきており、糖尿病のような生活習慣病やガンなどの早期発見が可能となってきた。さらに、これらのバイオマーカーを検出することで、まだ病気ではないが病気になりつつある状態、未病状態が検知できることも分かってきており、人を病気にさせない技術として注目を集めている。また、感染症でも、感染初期の極微量の菌やウイルスを迅速に高感度で検出できるようになれば、治療の初動を早めることで早期回復が期待できるとともに、感染拡大の阻止にも繋がる。
これらを実現する鍵となる技術が、超高感度バイオセンサ技術である。すでにいくつものセンサ技術が実用化されているが、簡易検査では十分な感度や定量性が得られないといった問題がある。一方、高感度な検出手法では、操作が煩雑でその場での迅速な判定は難しい。現状では、未病状態や感染初期を正確にその場診断できる技術はなく、その実現に向けて、従来技術の改良、新規技術の開発など、様々なアプローチから研究されている。
従来のSPRF検出系は、光学プリズム上にSPR励起層を持つチップを密着させ、さらにこのチップ上に検体を保持する流路を接合した構成だった。また、励起用の光を、プリズムに対して所定の角度に調整して入射する必要があった。そのため使い勝手が悪く、装置が大型化するため、高感度であることが分かっていながら実用的な使われ方はされていなかった。そこで、底面に光が入射するプリズム面となるようなV字型の溝のマイクロ流路により流路そのものにプリズムの機能を持たせ、流路の内面にSPR励起層として金(Au)薄膜を持った構造を考案した。これによって、プリズム、検出用チップ、流路の3つの部材に分かれていた構成を一体化させた。また、センサチップ底面に励起用の光を垂直に入射すればSPRが励起されるようにV溝の頂角を設定してあるので、煩雑な入射角の調整が不要で、下方から照射される励起光に対して水平にチップを置くだけでSPRF効果が得られるようにした。
|
|
|
図2 (a)従来のSPRF励起用の光学システム。プリズム底面に検出用チップを密着させ、検出チップ表面上に流路を接合して測定を行う。(b)従来のプリズム部分を回転させて2つ組み合わせた、V溝バイオセンサ発案時の概念図。(c)今回開発したV溝バイオセンサチップの断面図 |
図3は、光源にLEDを用いた場合のセンサシステム全体の構成図。コリメーターレンズにてLEDからの光を平行光にした後に、ポーラライザ(偏光子)でSPR励起に必要な向きの偏光にする。さらに、バンドパスフィルタで、単色光に近い光にした後に、V溝バイオセンサ底面に垂直に照射する。なお、光源としてレーザーダイオード(LD)も使用できる。LDからの光は、ほぼ単色で、しかも偏光なので、ポーラライザ、バンドパスフィルタは不要となる。V溝内面に形成したAu薄膜表面に励起光によってSPRが励起されるので、この面に蛍光色素で標識されたバイオ物質が吸着すると強い蛍光を発するため、高感度でバイオ物質を検出できる。センサチップの材料にはポリスチレンを用いた。励起光波長、各種材料の屈折率や厚さなどからV溝頂角の最適値を算出したところ49度となった。なお、ロングパスフィルタは蛍光だけを透過させて励起光が直接CCDカメラに入ることを防ぐために設置している。
図4は、インフルエンザウイルスの検出結果。ここで用いたセンサのV溝内面には厚さ0.6nmのクロム(Cr)層を接着層とし、SPR励起層としてAu層を形成してある。Au層の上には、カルボキシル基(-COOH)の付いた自己組織化単分子膜(Self-assembled monolayer:SAM)を形成し、その上にA型インフルエンザウイルスの一種であるA/Udorn/307/1972ウイルスを固定化した。エタノールアミンでブロッキングを行った後、Anti-Udorn抗体を加え、その後、2次抗体として蛍光色素Alexa-Fluor-700にて標識された抗体を加えた。図4(b)はインフルエンザウイルスの濃度と蛍光強度の関係を示す。計測時間は2分とした。図に示すように0.2HA unit/mLの濃度のウイルスがノイズレベルに対して有意に検出できている。なお、インフルエンザウイルス検出以外にも、DNA検出では1nM(Mはmol/L)、ビオチン-ストレプトアビジン結合では100fMの濃度での検出が可能だった。
現時点では、V溝バイオセンサによって得られる信号強度は、理論値の1%以下に留まっている。これは主にV溝内面の緩やかな凹凸に原因があると考えている。センサチップは金型成型によって作製しているが、金型はV溝に対応する三角形の凸形状を持つ。今回用いた金型には研磨時に残ってしまう数十µmピッチで高さ数百nm程度のうねりがあり、これがV溝内面に反映される。このうねりのため、理論通りにSPRが励起されず、感度が低くなっていると考えられる。金型の精度を上げることで、1~2桁以上の高感度化が期待できるとしている。
また、今回開発した技術を応用し、パナソニック、神戸大学と共同で、鳥インフルエンザウイルス監視システム用のV溝バイオセンサシステムを試作した。試作機は260mm×180mm×160mmと、体積で従来機より約1/9に小型化した。今回の試作機の蛍光検出部には冷却CCDを採用しているが、この部分をフォトダイオードなどで置き換えることができれば、さらに小型軽量化できるという。
V溝バイオセンサは、検出対象によってはすでに100fMオーダーの検出が可能であり、多くのバイオマーカー検出においては十分な感度を実現できているが、人に感染する前の環境中(例えば室内)に存在する極微量ウイルスを検出するには、現状よりさらに3桁程度の高感度化が必要であると試算される。今後は、センサチップの製造プロセスを改良し、より理想的な形に近いV溝形状を実現させると同時に、V溝中に対象物質を濃縮させる技術も付与し、これらのニーズに応えられるような高感度化を目指す。また、現在は液体試料をピペットにて手動で注入しているが、小型ポンプを備えたマイクロ流路送液技術を融合させ、より簡便に検出できるシステムの構築も目指す。さらに、2~3年以内の、実験室レベルの微量物質センサシステムとしての製品化、その数年後には臨床現場で使用できるシステムの完成を目標にするとコメントしている。