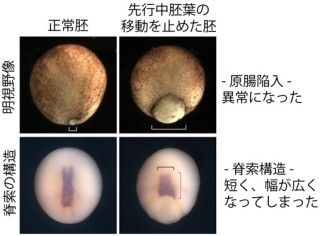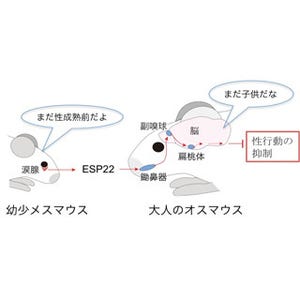京都大学(京大)は、タンザニア・マハレ山塊に生息する野生チンパンジーを長期的に観察したデータから、チンパンジーのオスは離乳後でも、母親を亡くすと生存が困難になることを明らかにしたと発表した。
同成果は、同大 野生動物研究センターの中村美知夫 准教授、同 伊藤詞子 研究員、同 座馬耕一郎 研究員、神戸学院大学の早木仁成 教授、鎌倉女子大学の保坂和彦 准教授らによるもの。詳細は米国科学誌「American Journal of Physical Anthropology」電子版に掲載された。
ほ乳類は生後しばらくの間、母親からの母乳を頼りに生きる必要があり、離乳前に母親が死別するなどの理由で母乳を得ることができなければその子供も死別してしまう。逆に言えば、ヒトを除くほ乳類は離乳さえしてしまえば、母親が不在でも生きていくことができると考えられてきており、ヒトに近縁な生物で、メスが集団間を移籍する父系社会を築くチンパンジーであっても、離乳期を迎える4~5歳を過ぎれば、そのように考えれてきた。
今回の研究では、タンザニア・マハレ山塊に生息する野生チンパンジーの長期データをもとに、孤児になった37頭のオスのデータを年齢ごとに分析。その結果、子供期から青年期にあたり、完全に自分で餌を食べることができるほか、次第に母親と疎遠になり、オトナのオスたちの「社交の場」に参加していく時期にあたる5~13歳のオスにおいて期待寿命に達する前に死亡してしまう例が多く確認されたという。
今回の知見について研究グループでは、チンパンジーにとっての母親の重要性がこれまで考えられていた以上に長く継続することを示唆するものだとし、重要な局面で母親と一緒に食物を食べることができたり、他個体とのけんかの際に母親からの助けがあったり、といった利益があるのだろうと考えられるとコメントしているほか、母親がいることが心理的な安心感に繋がっている可能性もあるとしている。
また、こうした授乳期間を終えた後も長期間、子供のサポートを続けるというヒトの特徴に近い今回の発見は、長期にわたって継続するヒトの親子関係がどのように進化してきたのかを明らかにする上でも、重要な知見と言えるとも説明しており、今後は、チンパンジーの母親から大きくなった子供へのサポートについての体系的な研究はあまりないことから、そうした具体的なサポート行動を調べることで、父系社会における母親の重要性を明らかにしていきたいとしている。