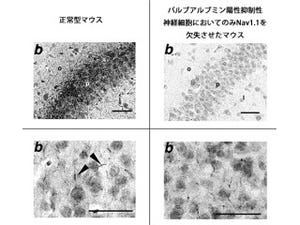国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は9月19日、聖マリアンナ医科大学、鳥取大学との共同研究により、学習障害の中核を占める「ディスレクシア(発達性読み書き障害)」において大脳の「大脳基底核」と「左前上側頭回」の2領域に異常があることを、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)などを用いる研究によって発見したと発表した。
成果は、NCNP 精神保健研究所 知的障害研究部の稲垣真澄部長、同・脳病態統合イメージングセンターの守口善也氏、北洋輔日本学術振興会特別研究員、聖マリアンナ医科大の山本寿子氏、鳥取大の内山仁志氏、同・関あゆみ氏、同・小枝達也氏らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、9月19日付けで英科学研究誌「BRAIN」オンライン版に掲載された。
発達障害の一型である「学習障害」は、特に教育分野においてその対策が強く求められている。学習障害の中核を占めるディスレクシアは、日本の人口の約0.7~2.2%、100~200万人いると推定されている。全般的な知能が正常範囲にあり、視覚や聴覚などの末梢感覚器の障害がなく、学習環境や本人の意欲にも問題がないにも関わらず、「読み書き」に困難が認められ、小学校高学年になってもひらがなが読めない、漢字が書けないといった形で障害が現れるのが特徴だ。特に、正確かつ/または流暢な単語認識の困難があり、綴りや文字記号の音声化が劣拙であることを主徴とする。
言語圏によって有病率は異なり、アルファベット語圏では5~17.5%とされるが、日本語圏では1%未満から3%程度という。文字言語の使用が求められる小学校以降に顕在化することが多く、現在では、特別支援教育の主要な対象の1つとされている。同障害を抱える著名人としては、俳優のトム・クルーズ、映画監督のスティーブン・スピルバーグ、ヴァージングループ会長のリチャード・ブランソン、スウェーデン国王カール16世グスタフなどがいる。
ディスレクシアはコミュニケーションに障害があるなど、周囲の一般人にとってわかりやすい形で障害が現れるわけではないため、「本人の努力が足りない」などといった誤解や偏見を生みやすく、同障害の病態解明は医学的にも社会的にも急務とされていた。
そこで研究チームでは今回、ディスレクシアの原因とされる認知能力の1つである「音韻処理機能」に焦点を当てて、脳機能の異常を明らかにすることにしたのである。なお音韻処理とは、一連の音刺激(例:会話)などにおいて、最小の音単位(音素・拍)を認識・処理する能力のことをいう。日本語の例では、例えば「たいこ」という発話を聞いた時に、それらが3拍で構成されていることや、真ん中の音が「い」であることなどを認識する能力とされる。文字の読み能力に強く関わるといわれており、音韻処理の問題がディスレクシアの原因の1つとして考えられている。
日本人の健常成人30名、健常小児15名、および臨床診断が確定したディスレクシア児14名の計59名を対象に、音韻処理に関わる課題を新たに作成・実施し、音韻処理の際の脳活動をfMRIによって測定したところ、読み書き障害児には2つの脳領域、「大脳基底核」と「左前上側頭回」に活動の異常があることが確認された。
大脳基底核は大脳半球の基底部の髄質にある神経核の集合体で、運動調節、認知機能、感情、動機付けや学習などさまざまな機能を担っているが、音韻処理においてはその効率性に関与していると考えられている。そして健常成人や健常小児の大脳基底核では、要請される音韻処理のレベルに応じてその活動が変化していたことに対し、ディスレクシア児では要請されるレベルに関係なく常に大脳基底核が活動していた(画像1)。つまり過活動だったのである。
もう1つの左前上側頭回は、大脳皮質の側頭葉に存在するしわの隆起した部分のことで、熟達性に関与していると考えられているという。同領域は健常成人や健常小児などでは、音韻処理の能力が高ければ高いほど活動が認められるが、ディスレクシア児では活動が低下していた(画像2)。
行動学的データとfMRIデータの解析から、ディスレクシア児の音韻処理能力が低下する背景には、この2つの脳領域の活動異常があると考えられるとする。特に大脳基底核は、アルファベット語圏では指摘されることが少なく、日本語圏のディスレクシア児の背景病態を考える上で重要な知見の1つとして考えられるという。
今後期待される展開としては、第1に脳機能評価を用いた客観的な診断法が確立されることだとする。現在、種々の神経心理検査や問診などによって診断されている、ディスレクシアの診断プロセスに今回の研究成果に基づく脳機能評価を併用することで、診断の精度が高まり、誤診や障害の見逃しを軽減することが期待されるという。
第2に、脳機能評価に基づいた治療法の開発・治療効果判定が考えられる。現在では、主に心理・教育分野において治療や介入がなされているが、今回の成果を基に音韻処理に関わる治療・介入法の開発や、治療・介入後の改善の程度を、脳機能評価によって判定することなどが可能になるとしている。