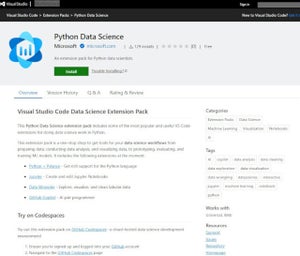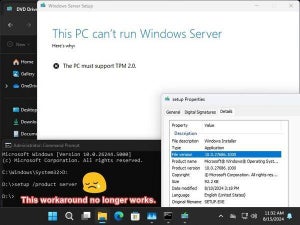世界を驚かせた内燃機関のみでの超低燃費の実現
快適な走りと優れた居住性、そして燃費の良さの追求で、全世界から高い評価を受けているマツダ。同社製自動車のブランド力の源泉の1つとなっているのが、次世代技術群「SKYACTIV TECHNOLOGY(スカイアクティブ テクノロジー)」だ。SKYACTIVは、エンジン、トラスミッション、ボディ、シャーシに至るまで、車に搭載するすべての技術を革新するものである。
SKYACTIVテクノロジーは2007年3月にマツダの技術開発長期ビジョンとして発表された「サステイナブル"Zoom-Zoom"宣言」のもと開発が進められてきた。2008年6月の正式発表の場で、この技術により2015年までに同社製自動車の平均燃費を、グローバルで2008年比30%向上させる、と宣言したことで世界中の関係者を驚かせた。現在SKYACTIVテクノロジーはマツダの様々な車に生かされており、内燃機関のエンジンだけの動力でハイブリッド車に迫る優れた燃費性能を実現している。マツダにとってSKYACTIVは、同社の成長を支えるまさに原動力だと言って過言ではない。
このSKYACTIVテクノロジーの開発で威力を発揮したのが、マツダの開発陣の間で脈々と受け継がれてきたモデルベース開発である。モデルベース開発とは、シミュレーション技術をソフトウェア開発に取り入れた開発プロセスのことで、自動車業界を筆頭に、近年取り入れる企業が増えている。自動車におけるモデルベース開発と言うと、一般的には制御開発のために使う「制御対象モデル」と「制御モデル」のことを指すが、マツダではCAE(Computer Aided Engineering)も含めたシミュレーションを使った開発全般をモデルベース開発と呼んでいる。その理由について、SKYACTIVテクノロジー開発の先陣で指揮をとった同社パワートレイン開発本部 パワートレインシステム開発部の部長、原田靖裕氏は次のように説明する。
「究極の開発の姿から思い描いた場合には、制御対象モデル、制御モデルの2つとCAEとを区別する意味がなくなってくる。これらを連続してつながる一つの技術やプロセスになるはずだと考えるからだ」
原田氏は、SKYACTIVのプロジェクト発足当初、CAEグループのマネージャーとしてCAEの計算を一手に引き受けていた。その後はモデルベース開発の主査として全社横断的にモデルベース開発を見渡して改善を図る役割を担ったのである。
「モノで試行錯誤するのではなく、ソフトウェアの中で意図を持った机上設計から机上検証までを行い、モノは一発でつくる──我々のモデルベース開発が目指すのはそういうところだ」と原田氏は言う。
巨大なプロジェクトを支えたモデルベース開発
マツダの制御システム開発の規模は10年間で10倍という勢いで拡大してきた。とりわけSKYACTIVの開発ではモデルが大規模化し、航空宇宙や自動車の分野で広く使われているモデルベース開発ソフトウェアの限界を超えるまでになっていた。ソフトウェアがフリーズした際には、開発メーカーが「世界で初めて起きた問題」だと驚き、特別対策体制を組んで対処にあたったということからもその規模の巨大さがうかがえる。
「燃焼効率改善率を従来の2倍以上」という高い目標を掲げたSKYACTIVの開発においていかにモデルベース開発が大きな役割を果たしたのかがわかるのが、次に紹介する燃焼効率改善の取り組みだ。
SKYACTIVの最初のステップで燃費を大きく改善できた最大の要因は、エンジン燃焼の革新にある。燃焼効率を改善するにはエンジンの圧縮比を上げれば上げるほど良いとされるが、圧縮比を上げると異常燃焼も起きやすくなる。しかし、ある時エンジン担当のチーフエンジニアが15:1という通常よりはるかに高い圧縮比を採用することを提案した。当時12:1の圧縮比でも実現が困難だったため、多くの人々は「絶対に無理だ」と反対したという。しかし、実際に実験したところ、予想したよりもうまく(大きさなどに課題はあったが)エンジンがまわったのだ。これは当時のCAEモデルでは説明がつかない現象だった。
そこで、ガラスを通して内部が観察できるエンジンをつくり、シミュレーションと実機とを比べながら、CAE技術者とエンジン設計者、実験者が一体となってこの燃焼のカラクリを説明できるモデルの構築をとことん追求していった。約1年かけてモデルを構築し開発進捗会議でこの高圧縮比エンジンのモデル予測精度改善結果を説明したところ、大きな拍手が起きいつまでも続いた。ピリピリとした空気が流れるいつもの会議からは想像もつかない光景に、ある設計者は「20年間設計をやっていてこんなことは初めてだ」と、深く感動していたという。
「当初はモデルに懐疑的だった開発の最前線を担う専門家たちから、開発後半に『あのモデルがなければ、この燃焼を絶対に実現できなかった』という言葉をもらった。モデルが信用できるようになれば、机上での仮説検証はいくらでもできるようになる。SKYACTIVという技術革新の成功は、常識にとらわれない発想と、モデルベース開発によるスピーディな検証があってこそ実現できた」と原田氏は振り返る。
RX7開発から伝わるモデルベース開発の技術とノウハウ
マツダのモデルベース開発の歴史は1980年代にまで遡る。原田氏は87年、同社の「RX7」で発生する加速時の振動を抑える点火アクティブ制御を、モデルベースで取り組んだのだ。当時、新制御ロジックの開発は、半年を要するのが普通だった、制御ロジックの開発着手からキャリブレーション終了までをわずか1週間でやり遂げたことは、関係者を大いに驚かせた。原田氏は制御に使う関数を自らアセンブラで組み、自身で設計した基板のチップに実装した。実装前のシミュレーションも行った。この時に作成した関数の一部は、別の言語に変換され、いまでも使われておりSKYACTIVを支えているという。
その後、マツダが開発したMILS(Model In the Loop Simulaton)がル・マン24時間レースでも使われ、1991年の総合優勝に貢献する。コース変更が発表され、レーシングカーでの事前テストもできない状況だったこの時、MILSを活用して路面モデルを作り、仮想コース上でエンジンと車両の設計と走り方の戦略策定を行ったのである。
マツダのモデルベース開発を始まりからこれまで支え続けている原田氏は、モデルベース:開発の意義について次のように総括する。
「多くのエンジニアがもれなく質の高い設計をするためには、モデルベース開発は欠かせない存在だ。未知の世界で無数のアイデアを試すことができるのがモデルベース開発。実機の制作が不可欠な従来の開発手法では、前モデルをベースに少しだけ改良したものを数パターン作り、その中から良いものを選ぶという程度のことしかできなかった。それに対してモデルベース開発ならば、あらゆる選択肢の中から本当に良いものを採用することができる。我々は、単なる効率化のためだけでなく、新たな技術の創造のためにモデルベース開発を使うべきだと考えている」
なお、原田氏は9月12日、13日に東京都文京区の東洋大学 白山キャンパスで開催される『ソフトウェア品質シンポジウム2013』に登壇予定だ。13日(木)の9時15分より、『SKYACTIVテクノロジーとその開発を支えたモデルベース開発』というタイトルで講演を行う。本稿で紹介した内容をさらに深堀りした話が聞けるので、興味のある方はぜひとも参加してほしい。