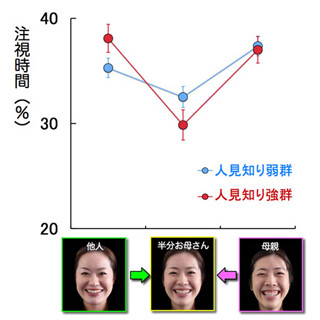大阪大学(阪大)は8月8日、ヒトにおいて親切が広く交換されるための仕組みである「社会間接互恵性」が、5~6歳齢の幼児の日常生活で働いていることを確認したと発表した。
成果は、阪大大学院 人間科学研究科の清水真由子特任研究員、同・大西賢治助教らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、8月7日付けで米オンライン科学誌「PLoS ONE」に掲載された。
ヒトは日常生活で困っている他人を見ると、たとえそれが自分の知らない人であっても助けてあげたい衝動にかられ、多くの場合何らかの親切を行う性質を持っている。このようなヒトの利他性は動物界の中でも大変特異的で、どのような仕組みによって広範囲に及ぶ親切の交換が維持されているのかは大きな謎とされてきた。
この謎を説明するために提唱されたのが、社会間接互恵性と呼ばれる仕組みだ。社会間接互恵性は、ある個体が利他行動が行われた結果その個体の評価が高まり、他者に行った利他行動が回り回って別の第三者から返ってくる仕組みのことである。画像1はそれをイメージしたものだが、「親切児(B)」が「受け手(C)」に親切を行ったのを観察した「親切行動観察児(A)」が、後に「親切児(B)」に親切に振る舞っているというものだ。
この仕組みは、集団の成員が第三者間のやり取りの情報からある他者を評価し、後にそのほか者に対して利他的に振る舞うかどうかを決定することによって維持されている。これはまさに「情けは人のためならず」ということわざが表す内容と同じことだ。これまでに、利他性を調べるゲームや、物語を聞いて登場人物に資源を分配する実験などからヒトの利他行動のやり取りに社会間接互恵性が働いている可能性が指摘されていた。しかし、この仕組みが日常生活でも働いているのかどうかは、実験によるデータを取得することが難しいといった理由から示されていなかったのである。
そこで研究チームは今回、幼児が日常生活の中で他児に対して社会間接互恵的に振る舞うのかを検討するために、大阪府下の保育園で5~6歳齢児を対象として、日常生活における幼児同士の利他行動のやり取りに関するデータの収集を行った。ある幼児が、他児に親切をした児を見た後に、その親切な幼児に対してより親切に振る舞うようになるのかどうかを厳密に検討するため、以下のような特殊な手法を用いた観察が行われたのである。
まず、追跡観察をする児(親切児、画像1中のB)を12名選択。それらの児が他児(受け手、画像1中のC)に利他行動(具体的には、他児(C)を手伝ってあげる行動や、他児(C)に物を貸してあげる行動)が行われた瞬間から10分間の観察を行い、その場面を「親切行動後場面」とする(画像2)。
親切行動後場面が始まった瞬間に親切児(B)の周囲1m以内にいた児(受け手以外)からランダムに選んだ1名を親切行動観察児(画像1中のA)とし、親切児(B)が受け手に親切にするのを観察していた児として、その児(A)の行動が観察された。その後、親切行動後場面の10分間に親切行動観察児(A)が親切児(B)に向けて行った利他行動が記録された形である。
また、親切行動観察児(A)が親切児(B)に対して行った親和行動も記録された。この親和行動とは、体に触ったり、肯定的な内容で話しかけたり、自分の持っている物を見せたりする行動のことで、「相手と仲よくしたい」、「相手を好ましく思っている」という時によく起こる行動とされている。さらに親切行動後場面とは別に、後日、親切児(B)のすぐ近くに同じ親切行動観察児(A)がいるのが発見された瞬間から10分間同様の観察を行い、普段場面とした(画像2)。
親切行動後場面と普段場面でそれぞれどのくらいの利他行動、親和行動が見られるかを比べると、親切行動後場面において普段場面よりも高い頻度で利他行動、親和行動が起こっていることが確認されたのである(画像3)。
画像3が、親切行動後場面と普段場面における親切行動観察児(A)から親切児(B)への利他行動と親和行動の頻度を表したグラフだ。このグラフについて補足すると、グラフ中のピンクの棒は親切行動後場面における親切行動観察児(A)から親切児(B)への行動、紫の棒は普段場面の同様の行動を表する。両場面を比較すると、利他行動と親和行動の両方が親切行動後場面で多いことがわかる。
親切行動観察児(A)は親切児(B)が受け手に利他行動が行われたのを見た直後に、普段よりも高い頻度で親切児に対して利他行動をしていた。この効果は「親切児(B)が普段受ける利他行動の頻度」や「親切児(B)と親切行動観察児(A)の仲の良さ」などを考慮して分析したとしても消えなかったという。このことから5~6歳齢児は、日常生活の中で間接互恵的な行動傾向を示していることが確認されたというわけだ。
また、親切行動観察児(A)は、親切児(B)が親切な行動をしているのを見た後に、利他行動だけでなく親和行動も普段より頻繁に行っていた。このことから、幼児が第三者間のやり取りから他者を評価する際には、その他者と仲よくしたい、その他者を好ましく思うという単純な感情が重要な役割を果たしている可能性が示唆されたのである。
今回の研究から、間接互恵性の成立にとって重要な行動傾向が、幼児期から日常生活で発揮されていることが判明した。この結果は、ヒトの利他性の進化がどのようにして起きたのかを明らかにする上で重要な知見となるという。
また、今回の研究が示した「他者間のやり取りから他者の評価を形成し、親切な者にはより親切に振る舞う」という傾向は、社会間接互恵性の成立にとって最も重要なルールだ。しかし、これ以外にも、他者に親切にしない者には親切にしない(もしくは罰を与える)というルールなど、いくつかの重要なルールが理論研究から指摘されている。今後は実験を併用しながらこれらのルールが幼児の日常生活で働いているのかを検討していく予定とした。