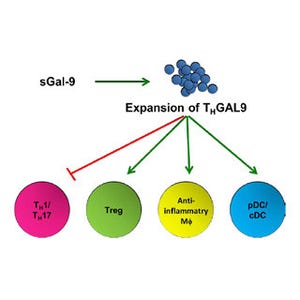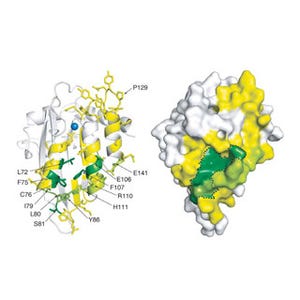理化学研究所(理研)は7月3日、タイで実施された遺伝子検査に基づくエイズ治療薬の使い分けに関する前向き臨床研究において、遺伝子検査の有用性を実証したと発表した。
同成果は、理研統合生命医科学研究センターの久保充明副センター長、同センター ファーマコゲノミクス研究グループの莚田泰誠グループディレクターらとタイ国立マヒドン大学医学部ラマティボディー病院、タイ王国保健省医科学局(DMSc)の共同研究グループが行った前向き臨床研究「GENPART(Genotype-based personalized prescription of nevirapine)Study」によるもの。詳細は7月3日にマレーシア・クアラルンプールで開催されたエイズ関連の国際会議「IAS(International AIDS Society)2013」で発表された。
エイズウイルス感染者の発病や母子感染を防ぐために用いられるエイズ治療薬は、毎日飲み続ける必要があるが、一方で、高価であるため経済的負担が大きいという課題がある。そうした理由から、タイでは治療薬の中でも比較的安価な成分「ネビラピン」を含む「GPO-Vir」が開発され、多くの医療機関で使用されるようになってきたが、同薬はネビラピンの服用により薬疹が副作用とし21%の発症頻度で起こっており問題となっている。
研究グループはこれまでの研究から、ネビラピンによる薬疹の起こりやすさに関連する遺伝子として、「HLA-B」および「CCHCR1」を発見しており、HLA-B遺伝子の「HLA-B*35:05」という型を持つか、あるいはCCHCR1遺伝子上の一塩基多型(SNP)である「rs1576」においてグアニン(G)を1つ以上持つ患者(GG型およびGC型)が、どちらも持っていない患者に比べて薬疹が4.6倍起こりやすいことも突き止めていた。
これらの成果を実際に医療現場へ応用するためには、臨床研究を実施する必要があるため、その調査として研究グループは2009年より、タイ国内の9医療機関にて、ネビラピンを投与する前に個人の遺伝子型を調べ、医師がその情報を基にエイズ治療薬を選択することで、薬疹の発症リスクを軽減できるかどうか検討するための前向き臨床研究を行ってきた。
具体的には、臨床研究に参加した1103名の患者を、遺伝子検査せずにネビラピンを投与する標準治療群と、遺伝子検査を行ってネビラピンを投与するかどうかを決める介入治療群の2群にランダムに分け、介入治療群には医療機関に設置された理研と凸版印刷、理研ジェネシスが共同開発した小型遺伝子解析システム「Quimple」のプロトタイプを用いてHLA-B*35:05およびCCHCR1の遺伝子検査を行って、薬疹発症の非リスク型と判定された患者にはネビラピンを、リスク型と判定された患者には他のエイズ治療薬を服用してもらうようにして調査を行った。
こうして標準治療群と介入治療群における薬疹の発症率を比較したところ、それぞれ18.0%および13.2%となり、標準治療群と比べ介入治療群では薬疹の発症率が約3分の2に減少することが示され、遺伝子検査がエイズ治療薬による薬疹の軽減に有効であることが示されたという。
なお、Quimpleのプロトタイプは、採血から解析結果出力までの遺伝子型判定を約1時間で実現しており、将来、医療現場に普及すれば遺伝子検査のために患者を長時間待たせることがなくなると期待されることから、そうした装置を活用して、エイズ患者に遺伝子検査を行うことで、薬疹リスクを軽減できるようになり、個人に最適なエイズ治療の確立を目指した、オーダーメイド医療の実現に向けた道が開けることが期待されると研究グループではコメントしている。