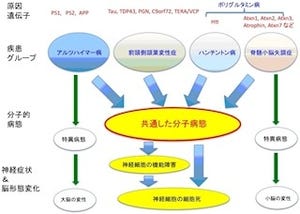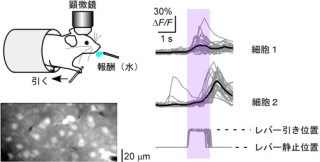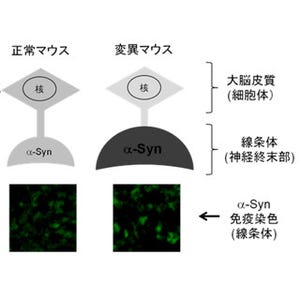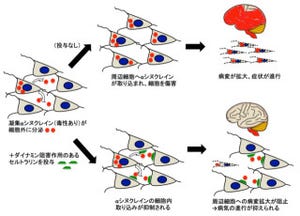東京大学(東大)は、これまで病気の発症のメカニズムが不明で、有効な根本的治療法がなかった神経難病「多系統萎縮症」に対し、日米欧の国際多施設共同研究による遺伝子解析を行った結果、家族性・孤発性に共通して病気を発症しやすくなる遺伝子(COQ2遺伝子)が存在することを発見したと発表した。
同成果は同大 医学部附属病院 神経内科の辻省次 教授、同 三井純 特任教授らによるもの。同成果の詳細は「The New England Journal of Medicine」に掲載された。
多系統萎縮症は、進行性の神経難病である脊髄小脳変性症の中で最も頻度の高い孤発性の疾患で、ふらつき、しゃべりにくさなどの小脳の障害による症状、震えや筋肉のこわばり、動きづらさなどのパーキンソン症状、血圧の変動や排尿・排便の障害などの自律神経障害による症状など、多くの神経系統に障害をきたすことが知られており、日本の患者数は人口10万人当たり10人程度と推定されており、その発症年齢は平均50歳台後半の壮年層が多い(患者数として1万2000人程度)。
今回の研究では、次世代シーケンサーを活用し、日本のほか、フランス、ドイツ、イタリア、オーストラリア、米国の大規模多施設研究体制による協力態勢のもと、孤発性の多系統萎縮症の試料の大規模収集と、まれに発生する家族内の複数の発症者(多発家系)の試料収集を実施し、多発家系における発症者が共有するゲノム領域の特定に成功した。
そこで、次世代シーケンサーを用いて、全ゲノムの塩基配列解析を実施したところ、2つの多発家系において、発症者が、候補領域内に存在する遺伝子(COQ2遺伝子)にホモ接合性あるいはヘテロ接合性の変異を有していることを確認し、これが病因遺伝子となっていることを明らかにした。
COQ2遺伝子は、体内でコエンザイムQ10を生合成するために必要な酵素であり、実際に、発症者の組織内におけるコエンザイムQ10量を測定したところ、その含量が低下していることも判明したという。
さらに、日米欧の研究グループにより提供された孤発性の多系統萎縮症患者グループと、対照となる健常者グループに対して、COQ2遺伝子の塩基配列の解析を行い、患者グループでCOQ2の変異が高頻度に観察されるかどうかを検討したところ、日本人においては、V343Aという変異が健常者群では3%であるのに対し、患者群では9%と3倍ほど高いこと、ならびにV343A変異がCOQ2の活性を軽度低下させることを確認したという。
研究グループでは、この変異は日本人だけに観察され、比較的頻度が高いことからも、治療法との関連で注目されるとする。また、V343A変異以外にも、COQ2の機能を強く障害する複数の低頻度変異が見いだされたとのことで、これらは、健常者グループでは極めてまれ(0.1%)であったが、患者グループでは10倍以上頻度が高い(1.06%)ことが確認されたという。
これらの結果を受けて研究グループは、COQ2遺伝子は多系統萎縮症の発症メカニズムとして、まったく予想していなかった遺伝因子であったとしているが、発症メカニズムの少なくとも一部にCOQ2遺伝子が関わっていることが見いだされたとしており、コエンザイムQ10の重要な機能であるミトコンドリアにおけるエネルギー産生系に関わっていること、ならびに抗酸化作用を持っている点などを、新たな視点のもと、研究を進めることで、神経難病の多系統萎縮症に対して実現可能な治療法の開発が進むことが期待されるとコメントしている。