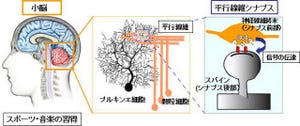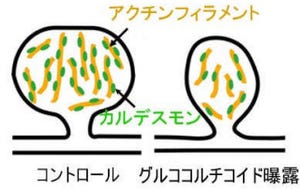金沢大学子どものこころの発達研究センターは1月25日、産学連携のプロジェクトで開発された「幼児用脳磁計(Magnetoencephalography:MEG)」を活用して調査を行った結果、一部の発達障害児は、言葉の意味を理解することは苦手ではあるが、目で見たことおよび文字の理解においては、健常児と比較して同等、あるいは逆に優れている傾向があることが示され、それは幼少期(5~7歳)よりすでに認められていることから、生まれながらに備わっている先天的な脳機能に由来する可能性を示唆し、特に文字を読む能力は、大脳の右半球の後方部(頭頂-側頭-後頭)の脳機能結合の高さに関係することを解明したと発表した。
成果は、金沢大 医薬保健研究域医学系の三邉義雄教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、英国時間1月25日付けで英国科学雑誌「Scientific Reports」にオンライン掲載された。
超伝導センサ技術「SQUID磁束計」を用いて、脳の微弱磁場を頭皮上から体にまったく害のない方法で計測・解析できる装置として、「脳磁計」がある。平成20年に、脳磁計を幼児用として特別に開発したのがMEGだ。
幼児用MEGでは超伝導センサを幼児の頭のサイズに合わせ、頭全体をカバーするように配置することで、高感度で神経の活動を記録することが可能になった(画像1)。なお、現時点で世界で2台しか存在しない。
|
|
|
画像1。実際のMEG測定 |
MEGは神経の電気的な活動を直接とらえることが可能であり、その高い時間分解能(ミリ秒単位)と高い空間分解能において優れているため、脳のネットワークを評価する方法として期待されている。さらにMEGは放射線を用いたりせず、狭い空間に入る必要がないことから、幼児期の脳機能検査として存在意義が高まっている点も優れた点だ。
今回、幼児用MEGを用いて、健常に発達している幼児(5-7歳)26人と、広汎性発達障害児童26人を対象として、脳内ネットワークの調査が行われた。
その結果、広汎性発達障害児童において高い読字能力を示す群は、脳の右半球後方のネットワークが、ガンマ波と呼ばれる振動を介して、強くつながっていることが示された(画像2)。この関係は、健常に発達している幼児では見られない現象であったことから、広汎性発達障害に固有の、知的特徴に関わる生理学的指標と考えられた。
なお、ガンマ波は約30Hz以上の早い周波数のことだ。この周波数帯域は、特に視覚を含む脳の情報処理に深く関与していることがわかっている。また、神経同士の連絡をスムーズに行う際にも重要な振動であるという。
今回の技術では、幼児に恐怖感を与えず、わずか5分で、脳の機能的発達について検査を行えることから、とても簡便で有効な検査方法といえる。現時点で脳疾患の新しい治療法を示すものではないが、この技術を利用することで、広汎性発達障害患者群で、右脳が特定の役割を果たしていることを解明し、幼児の複雑な脳機能発達と知的能力についての客観的な評価方法を確立できる可能性が高まったと、研究グループはコメントしている。