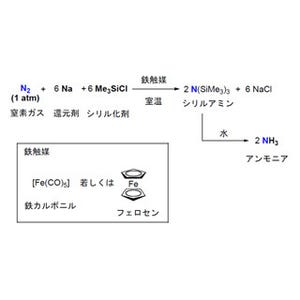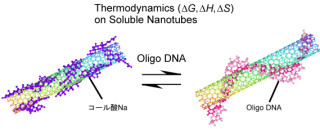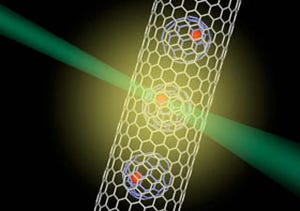九州大学(九大)は、第3世代の有機EL発光材料「Hyperfluorescence」の開発に成功したと発表した。同成果は、同大 最先端有機光エレクトロニクス研究センター(OPERA)の魚山大樹氏、安達千波矢 センター長らによるもの。詳細は、国際学術雑誌「Nature」のオンライン版に掲載された。
高効率な有機EL素子を実現するためには、電荷再結合に伴う励起子生成とその放射失活過程の制御が鍵となる。有機分子の励起状態には 、一重項励起状態(S1)と三重項励起状態(T1)の2つのスピン多重度の異なる状態が存在するが、電子とホールの再結合による励起子生成過程では、スピン統計則に従って、三重項励起子が75%の確率で生成され、一重項励起子が25%の確率で生成される。このため、高効率な有機EL素子を実現するために、三重項からの放射遷移を利用したリン光材料の使用が必要不可欠であると考えられてきた。実際、これまでにTris(2-phenylpyridinato)iridium(III)などの室温において、強リン光発を有する有機金属化合物を発光材料として用いることで、電流励起下での高効率な発光が得られてきた。しかし、これらの発光材料は、希少元素であるIrやPtを含有することや、青色発光材料の安定性に問題を抱えており、新しい切り口からのEL発光機構の開発が期待されていた。OPERAでは、一重項と三重項励起エネルギー差(△E13)が極めて小さい分子を設計することによって、三重項励起子を一重項励起へアップコンバーション(熱活性化遅延(TADF)現象)させ、励起一重項状態からの高効率なEL発光の実現を目指してきた。
これまで、OPERAでは、2009年度にポルフィリン誘導体(SnF2OEP)を用いて、電流励起下での遅延蛍光現象を確認したが、そのEL外部量子効率が~0.1%程度の極めて低い効率に留まっていた。その後、最先端研究開発支援プロジェクト(FIRST)において、TADFの原理を量子化学的な視点から考察し、新規に分子設計・合成を行い、トリアジン-カルバゾール誘導体を中心とした材料設計を進め、2011年度には外部量子効率~5.3%、2012年夏には同~11%を報告し、着実な研究開発を進めてきた。また、新たなTADF材料骨格の創出やExciplex機構の開拓も同時に行なってきた。
今回、各種電子供与性(ドナー性)と電子受容性(アクセプター性)置換基を含有する新規化合物の設計・合成に網羅的に取り組み、小さな△E13を保持しながらも、内部EL発光効率がほぼ100%の発光効率を示す新しい発光分子(カルバゾリルジシアノベンゼン誘導体:CDCB)の創出に成功した。さらに、CDCBを発光層に有する有機EL素子において、外部量子効率19.3%という極めて高い数値が得られたという。このことは、電流励起下で生成された三重項励起子が高効率で一重項励起子に変換され、EL発光に至っていることを意味しており、レアメタルを含有する有機金属発光材料を使わなくても、100%内部EL発光効率の実現が可能であることを確実なものとした。今後、有機EL素子の発光材料は、蛍光、リン光に次ぎ、第3世代のTADF材料へ大きくシフトしていくことを意味しているとコメントしている。
従来、スピン多重度の異なる分子軌道間の遷移には、強いスピン-軌道相互作用が必要であり、必ずハロゲンやレアメタルなどの重原子を含有させる必要があると考えられてきたが、今回の成果は有機化合物の分子設計の自由度を生かすことで、比較的単純な分子構造で励起電子状態を制御し、励起一重項と三重項間の遷移確率と各レベルからの放射失活過程を制御できることが明らかになった。今後、アカデミックな視点から、より詳細な物性解析を進め、有機発光材料の学理の確立とともに、さらに新しい有機発光材料の創出を目指していくという。また、TADFを発光中心に用いた有機ELデバイスの迅速な実用化を目指して、材料・デバイス・プロセスの開発を統合し、光の三原色を示す高効率なRGB発光材料のラインナップ、高耐久性素子の実現へと研究開発を進めていく。なお、九大では、この高効率な遅延蛍光現象を「Hyperfluorescence」を命名し、有機光化学の確立とともに、実用化に向けた研究開発を産官学で推進していくとした。