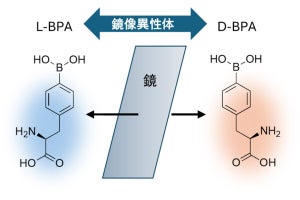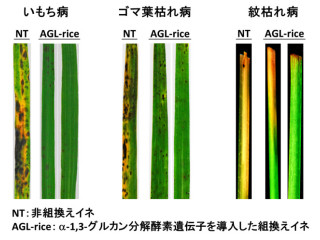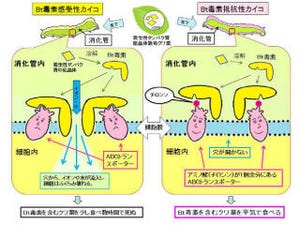農業生物資源研究所(生物研)は12月5日、水田で育つイネ(日本晴および農林8号)のほぼ全遺伝子の働き(発現)を大規模に解析して得られたデータをもとに、気象データと移植後の日数から任意の遺伝子の働きを推定できるシステムを構築したことを発表した。
同成果は生物研 石毛光雄 理事長、同植物科学研究領域長の飯哲夫氏、同植物科学研究領域 植物生産生理機能研究ユニットの井澤毅 上級研究員、同農業生物先端ゲノム研究センター ゲノムリソースユニット長の長村吉晃氏、同植物科学研究領域 植物生産生理機能研究ユニットの永野惇 特別研究員(現 京都大学ポストドクター)、同農業生物先端ゲノム研究センター ゲノムリソースユニットの佐藤豊 任期付研究員らによるもので、米国の科学雑誌「Cell」に掲載された。
生物研など日本の研究機関が中心となって進められた国際プロジェクトにより、日本イネ品種「日本晴」のゲノム塩基配列(DNA中の塩基の並び順)が2004年に完全解読され、イネが持つ約2万7000個すべての遺伝子配列情報が明らかとなり、現在、それを活用した有用なDNAマーカーが開発されるようになるなど、ゲノム情報を活かしたイネの育種が進められるようになってきた。
遺伝子は、ただゲノム上に並んで存在しているだけではなく、特定の条件や器官で働いて(発現して)はじめてその機能を発揮するが、ゲノム配列が解読された結果、イネが持つすべての遺伝子1つひとつが「いつ」、「どこで(どのような条件で)」、「どの程度」発現しているか? といったことを一度に解析できるようになり、これを活用することで、育種の栽培法の改善などが可能となることから、これまでに、「マイクロアレイ解析」などの手法を用いて、様々な条件の下で、イネの全遺伝子の発現データの解析が実施されてきた。しかし、遺伝子発現データの実用面での有効利用は、まだほとんどなされてこなかったという。
こうした遺伝子発現量データの利用が進まない原因の1つに、データが得られた実験条件があげられるという。これまでに行われた実験の多くは、温室などの安定な実験室条件の下で行われており、通常イネが栽培される水田のような気象条件などが複雑に変化する自然条件下のものではなかった。そのため、温室などで得られた遺伝子発現データが、必ずしも水田で育つイネに適応できるとは限らなかったのだ。
こうした課題を受けて今回の研究では、「水田で生育するイネの葉」を採取し、全遺伝子の発現量データの解析を実施したほか、サンプル採取時の気象データも合わせて入手、解析を実施。得られたデータを統計的にコンピュータ解析することで、イネの葉の遺伝子1つひとつの発現(働き方)を、気象条件などの環境条件等から予測できるシステムの構築を試みた。
この取り組みにより、2008年につくば市内の水田でサンプリングされた461個のイネ(日本晴および農林8号)の葉のサンプルについてほぼ全遺伝子(2万7201個)の発現量データが得られ、そのデータと、気象庁の計測による気象データ(風量、気温、湿度、日照、大気圧、降水量)、移植後の日数、採取した時刻をもとに大型コンピュータによる統計的な解析を行った結果、イネの葉で働くことが分かった1万7616個の遺伝子のうち、1万7193個について、「気象データ」「移植後の日数」「時刻」を入力することで、任意の遺伝子の発現程度を推定できるシステムの構築に成功したという。
また、2009年に、2008年と同様なサンプルを108個採取し、1万7193個の遺伝子の発現を実測し、2008年のデータから構築された予測システムに、2009年の「気象データ」「移植後の日数」「時刻」を入力し、遺伝子発現の程度を推定し、実測値と推定値を比較したところ、構築されたシステムの信頼性は高く、高い精度で多くの遺伝子の働き方を予測できることが確認されたという。
研究チームでは、今回開発したシステムを使うことで、過去の気象データをもとに、日本各地のイネの葉での遺伝子の働き方を推定することができるようになると説明するほか、推定された遺伝子の働く様子(遺伝子発現データ)と、過去のイネが受けた気象の影響(例えば、高温障害、冷害など)を比較することで、これらの障害に関係の深い遺伝子のリストアップが可能となるとする。また、今回明らかにされた遺伝子の働く様子(遺伝子発現量の推定データ)は、イネの栽培状況の判断に使える「遺伝子発現マーカー」の開発につながることが考えられ、特定の遺伝子の日々の働き方を指標に、出穂期を正確に予測してそれに応じて施肥をするタイミングを決定したり、病気にかかりやすい状態であることを検知し、被害が確認できる前に農薬を撒くことなどが実現可能になるとする
研究チームでは、今回の結果をより信頼性の高い成果に変えていくためには、サンプルの採取と統計的な解析を、つくば市だけでなく日本各地で行うこと、ならびに今回用いた日本晴ではなく、コシヒカリなど数多く栽培されている品種に対応したシステムに変えていく必要があるとするほか、今後は、品種間差の遺伝子発現データまでを考慮した統計解析技術を検討しながら、遺伝子の働き方をモニターする(または予測する)ことにより、より効率的に育種を進められるようになることが期待できるとしている。