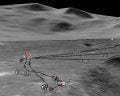産業技術総合研究所(産総研)は10月29日、月探査衛星「かぐや」が月表面を網羅する約7000万地点で取得した200億点以上の「可視赤外線反射率スペクトル」のデータを「データマイニング手法」を用いて解析し、地球から見た月の表側と裏側の「二分性」といわれる地形の違いの原因と考えられている超巨大衝突の具体的な痕跡を発見したと発表した。
成果は、産総研 情報技術研究部門 ジオインフォマティクス研究グループの中村良介研究グループ長、同・石原吉明研究員らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間10月29日付けで英国科学誌「Nature Geoscience」にオンライン掲載された。
今回、可視赤外線反射率スペクトルデータに対して、クラス分類というデータマイニング手法を適用し、衝突溶融物に多く含まれる「低カルシウム輝石」の分布状況を検討(画像2)。
その結果、月の表側にある「プロセラルム盆地」に対応する直径3000kmもの円状の分布が発見された。これは、超巨大衝突によって生成した衝突溶融物によるものと考えられ、月の形成初期の超巨大衝突を、初めて観測データによって裏付けることができた形だ。
地球の起源と進化を調べることは資源探査の点からも重要であるが、地球には40億年以上前の地質学的情報はほとんど残されていない。一方、地球の隣にずっと存在し続けてきた月では、40億年以上前に形成された岩石が比較的よく保存されているため、月の歴史を詳細に調べると、地球形成初期の情報を得ることができる。
月や地球のような天体の表層部を調べる手法として、探査機や人工衛星からのリモートセンシングによるデータは不可欠だ。最近では、可視光だけではなく赤外線を含む数100以上の波長帯での観測ができるようになってきたため、そのデータ量は莫大になっている。このような巨大なデータを活用し、有用な情報を引き出すための解析手法の必要性が高まっているというわけだ。
産総研の情報技術研究部門では、個人では保有しきれないほど膨大なデータを、クラウド上で解析するためのツール開発を進めている。一方、地質情報研究部門では、地球観測衛星が取得した可視赤外線反射率スペクトルデータを資源探査に活用するための研究を長年にわたって行ってきた。この両者を融合させ、月探査衛星「かぐや」の取得したデータに応用することで、月表面に存在する物質の特定を試みたのが、今回の研究である。
月の起源について、最も可能性が高いと考えられているのは、地球に巨大な天体が衝突し、その時生じた破片が集積して月になったとする巨大衝突説だ。この説では、できたばかりの月の表面は融けた溶岩の海で覆われている。
月の「高地」は、この溶岩の海が冷えて固まる際に浮上・集積してできた岩石で構成。一方、「海」は「高地」の形成後に内部から噴出した溶岩が窪地に溜まって形成されたと考えられている。
画像1で示されているように、暗い領域の「海」は月の表側に広く存在するが、裏側にはほとんど見られない。また過去の月探査から、表と裏では「海」と「高地」の比率だけでなく、地殻の厚さや放射性元素の分布もまったく異なることが明らかになっている。
この表側と裏側の非対称性は月の二分性と呼ばれているが、その成因は明らかになっていない。過去に「表側で発生した巨大な天体衝突が高地の物質を吹き飛ばして、直径3000kmもの巨大な衝突盆地(画像1左のプロセラルム盆地)が形成され、その結果として二分性が生じた」という仮説が提案されていたものの、実際に衝突が起こったことを示す物質科学的な証拠は見つかっていなかった。
画像1は、日本の月探査衛星「かぐや」が観測した月の表側(左)と裏側(右)。裏側の南方に見えている若干暗い領域は、南極エイトケン盆地と呼ばれ、太陽系全体でも最大級の衝突盆地である。表にある「雨の海」はおよそ38億年前の衝突によって形成された衝突盆地だ。また、プロセラルム盆地についても衝突盆地だとする仮説がある。
画像2に示されているように、月表面の主な鉱物は、それぞれ特徴的な可視赤外線反射スペクトルを持つ。2007年に日本が打ち上げた月探査衛星「かぐや」には、この反射スペクトルを測定し、詳細な月表面組成を調べることができる観測装置「スペクトルプロファイラ」が搭載されていた。スペクトルプロファイラは2007年12月から2009年6月までの間に、月面上の約7000万地点で200億点以上の反射スペクトルデータを測定したのである。
研究グループは、この膨大なデータを「決定木」を用いてクラス分類することで、特定の鉱物のスペクトルだけを抽出する方法を確立。今回、低カルシウム輝石を約20%以上含む物質に着目し、月表面上での分布を詳細に調べた(画像3・4)。
低カルシウム輝石はさまざまな岩石に含まれる鉱物であるが、今回発見された濃集地点は大規模な衝突によって地殻だけでなくマントルの一部まで溶融して衝突溶融物が生成され、再固化する際に産出されたと考えられる。
また、低カルシウム輝石はアポロ計画で取得された「雨の海」からの放出衝突溶融物にも多く含まれ、そのスペクトルは「かぐや」が測定した低カルシウム輝石に富む地点のスペクトルと一致している。
画像3に示されているように、低カルシウム輝石に富む物質は、雨の海の周縁部、南極エイトケン盆地の内部、月の表側全体を覆うプロセラルム盆地周縁の3つの領域に集中していた。
「雨の海」と「南極エイトケン盆地」は地形的な特徴などから、直径がそれぞれ約1000km、2500kmの衝突盆地であることが知られている。こうした大規模な衝突により、マントルの一部まで溶融し、衝突溶融物が再固化する際に低カルシウム輝石を産出したと考えられる。
一方、「雨の海」と「南極エイトケン盆地」以外の表側全体の分布点は、プロセラルム盆地(画像1・左)を形成した超巨大衝突によるものという考えだ。直径3000kmにも及ぶプロセラルム盆地を形成するためには、数百kmサイズの天体が衝突する必要がある。そのような衝突があったとすると、そこに存在していた「高地」はほぼ完全にはぎとられたはずだ。
また衝突によって地殻がはぎとられ深部の圧力が減少すると、溶岩がより噴出しやすく(海が形成されやすく)なるという。つまり、月の二分性はプロセラルム盆地を作った超巨大衝突によって生じたと考えられるのである。
今回、低カルシウム輝石の偏在が発見されたことで、月の二分性が超巨大衝突によるという仮説の物質科学的な裏付けが得られた形だ。また、適用したデータマイニング手法が200億点ものリモートセンシングデータに対する解析法として有用であることが確かめられたことも大きな成果である。
今後、月の形成条件をさらに調べるため、可視赤外線スペクトルだけではなく、地形や元素組成といった多種多様なデータを統合解析して、大規模な衝突が実際にどのように起こったのかを解明していくという。
産総研では、地球観測データ統合のために「GEO Grid」の開発が進められているが、GEO Gridの手法を月探査データに応用して、惑星科学研究者が利用できる統合解析プラットフォームを構築し公開していく予定である。
また、今回開発されたデータマイニングによる解析手法を、経済産業省が開発している地球観測衛星搭載ハイパースペクトルセンサ「HISUI(Hyperspectral Imager SUIte)」のデータに応用する予定だ。
今回のデータマイニング手法をさらに発展させて、「かぐや」のスペクトルプロファイラの数万倍にも達するHISUIのデータ解析へ適用すれば、鉱物資源探査や環境モニタリングの精度や効率が格段に向上すると期待されるとしている。