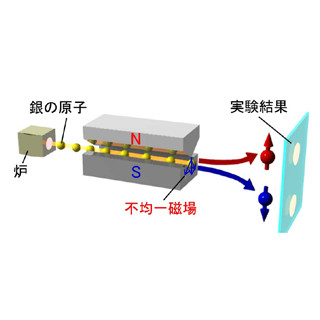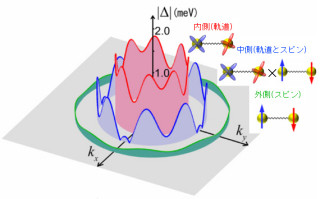理化学研究所(理研)と東京工業大学(東工大)は10月22日、あらゆる種類の放射性同位元素(Radio Isotope:RI)ビームのスピンの向きを、効率よく一定方向にそろえる手法を開発したと発表した。
成果は、理研 仁科加速器研究センター 偏極RIビーム生成装置開発チームの上野秀樹チームリーダー、同・市川雄一 基礎科学特別研究員(現・東工大特任助教)らを中心とする国際共同研究グループらの研究グループによるもの。
研究の詳細な内容は、日本時間10月22日付けで英科学雑誌「Nature Physics」オンライン版に掲載された。
原子や電子、原子核といったヒトの目に見えないミクロな粒子を特徴づける性質には、スピンと呼ばれる物理量がある。量子力学の確立以来、ミクロな粒子のスピンを人工的に操作することで、次々と新たな現象が見つかってきた。
ある新しいミクロな対象にスピン操作する手段が開発されると、その後の科学を飛躍的に進化させる可能性がある。近年注目されているミクロな粒子の1つとして、RIビームが挙げられる。
RIビームは自然界に存在しない多種多様のRIが、高速なビームという形で現れたものだ。特に、理研仁科加速器研究センターが保有する重イオン加速器施設RIBFは世界最高強度のRIビームの製造能力を持っており、供給可能なRIビームの種類は約4000種にも上ると予想されている。
しかし、その中でスピンを一定の向きにそろえるスピン操作が可能なものは数10種類しかなかった。この制限は、スピン操作のメカニズムとRIビームの生成方法とのミスマッチが原因だ。
RIビームファクトリー(RIBF)などの重イオン加速器施設では、安定な1次ビームを標的物質に入射し、その1次ビーム核の構成要素である陽子や中性子をはぎ取る「入射核破砕反応」を起こすことで、RIを2次ビームとして取り出せる。
この陽子や中性子をはぎ取る単純な反応過程でスピン操作が可能であることを旭教授が1990年に明らかにした。しかし、有効なスピン操作は「反応が単純であること、つまり少しの陽子あるいは中性子をはぎ取ること」が前提条件となるため、1次ビームから多くの陽子や中性子をはぎ取って生成しなければならないRIは有効なスピン操作が困難だった。
そのため、通常1次ビームとして利用できる原子核は、化学的性質から大強度ビームが供給できる希ガスなどの数種類に限定される。これにより、必然的にスピン操作可能なRIもその1次ビームの原子核から近い核、つまり少数の陽子や中性子をはぎ取るだけで生成可能な原子核に限られていた。
さらに、実際に研究で利用可能なスピン操作できるRIビームを得るためには、スピンの向きを整列させる「スピン操作効率」と、スピンがそろったRIビームの「収量」という2つの要素を同時に満たさなくてはならない。共同研究グループは、互いに相反するこれらの要素を同時に高める手法の開発に挑んだ。
研究グループは今回、「分散整合2回散乱法」と呼ばれるスピン操作方法を新たに開発した(画像1)。有効なスピン操作を行うための条件として、「反応が単純であること」が挙げられる。
画像1は、新手法「分散整合2回散乱法」適用時の実験レイアウト。今回の研究で開発された新しいスピン操作法「分散整合2回散乱法」は、2段階核反応と分散整合という2つの新しいアイデアに基づく。2段階核反応ではスピン操作効率の最大化を、分散整合では収量減少の最小化を図る。
1次ビームである48Ca(質量48の放射性カルシウム)は、1次標的に入射して多数の陽子や中性子がはぎ取られ、33Al(質量33のアルミニウム)の2次ビームを生み出す。
33Alは「分散整合条件」を満たしながら2次標的に入射して、1個の中性子がはぎ取られる。次に、ある特定の速度を持つ集団を選択できるスリットを通して、スピンの向きがそろったRIビームを3次ビームとして得ることができるというわけだ。
そこで、目的とするRIビームを生成する時にだけ1つの陽子あるいは中性子だけをはぎ取る「最も単純な反応」を起こすように工夫した。具体的には、安定な1次ビームを2回標的物質に入射する、2段階のステップを経て目的のRIビームを生成する。
1段階目の入射核破砕反応を終えたビームの原子核が目的の原子核より陽子あるいは中性子が1つだけ多い核を選ぶことで、2段階目の反応は「最も単純な反応」となり、スピン操作の効率を最大化することができる(画像2)。
画像2は、分散整合2回散乱法で重要な開発要素の1つである「2段階核反応」。核反応によって生じるビームの速度(運動量)の広がりを光の波長の広がり(色)に例えられている。
1回目の標的を通過して取り出される2次ビームは、最終目的とするRIより陽子あるいは中性子が1つだけ多い核になるように設定。その結果、2回目の反応ではスピン操作効率を最大化することができる。これによりどのようなビームから生成されたRIでもスピン操作が可能となるというわけだ。
しかし、反応を2段階のステップにしてスピン操作の効率はよくなるものの、生成反応回数が2倍になるために目的とするRIビームの収量が少なくなるという問題が生じる。なぜなら、RIを生成する入射核破砕反応は入射するビームの一部でしか生じないため、2回の反応後に取り出すRIビームの収量は少なくなるからだ。
またスピンの向きがそろったRIビーム抽出するためには、速度によって振り分け、ある特定の速度を持つ集団を選択する。そのためスリットという速度選択装置を用いるが、その選択が2回も行われるために収量はさらに大幅に減少してしまう。
そこで、収量の減少を最小限にするために、分散整合条件というビームの広がりを打ち消す条件で2次ビームを輸送することで、1回目の反応後のスリットを省略することに成功した(画像3)。その結果、特定のスピンの向きに整列させたRIビームを選択でき、さらに1つのスリットだけで速度選択することにより、一定の収量を得ることが可能になったというわけだ。
画像3は、分散整合2回散乱法でもう1つの重要な開発要素「分散整合」。分散整合条件を満たすように2次ビームを輸送すると、1回目の反応で速度を抽出しなくても2回目の反応で同じ速度変化したもの、つまりスピンが整列したRIビームを網羅的に収集することができるため、スリットを省略することができる。通常は原子核の緻密なエネルギー構造を調べるのに用いる。
本手法の実証実験をRIBFで行ったところ、1次ビーム48Caから33Alを経由して、"1中性子はぎ取り反応"で32Al(質量32のアルミニウム)を生成することにより、生成した32Alの内約8%を有効なスピン操作することに成功した。
一方で、比較実験として従来手法で48Caから1回の反応で32Alの生成が行われたところ、有効なスピン操作は確認できず、操作できた割合は0.8%以下であるという結果が得られている。
測定に要する時間の短さは、スピン操作効率の2乗と収量との積で決まる。この実験では、新手法と従来法との収量比が1:1.6だったので、従来手法に比べて50倍以上の改善を達成したことになる形だ。
分散整合2回散乱法を用いることで、原理的には、あらゆる種類のRIビームに対してスピン操作を行うことができ、かつ大強度で得ることができる。例えば、スピン操作したRIビームを用いて、その磁石的性質である磁気モーメントを1日で測定できる範囲をシミュレーションすると、従来手法に比べて圧倒的に広範な範囲の不安定核が測定可能になることがわかる(画像4)。
画像4は、測定可能なRIの広がりを表した核図表。1日間の測定時間で原子核の磁気モーメントの値を決定できるRIの範囲をシミュレーションしたものだ。18O(質量18の酸素)や48Caなどは、RIBFで用いられる代表的な1次ビームの原子核を示す。赤色が従来の手法で到達可能な範囲、青色が新手法で到達可能な範囲。従来に比べて圧倒的に到達可能な範囲が広がったことがわかる。
RIビームの特長として種類の豊富さが挙げられるが、この手法はRIBFなどの施設で供給される多種多様のRIビームに「スピン」という新たな可能性を付加するものだ。今後、RIビームとして得られる不安定核の性質を調べる基礎研究はもちろん、RIビームを用いた物質研究などの応用に向けても幅広い可能性が期待できると、研究グループはコメントしている。