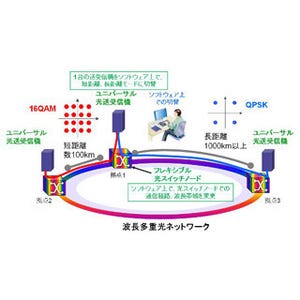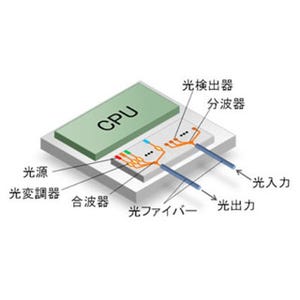富士通研究所は9月20日、スマートフォンなどの無線通信端末向けに小型で低電力な温度補償機能を搭載したCMOS電力検出器を開発したと発表した。詳細は、9月17日からフランスで開催されている国際会議「ESSCIRC 2012(European Solid-State Circuits Conference 2012)」にて発表された。
近年、スマートフォンやタブレット端末に代表される無線通信端末が急速に普及している。無線通信端末は、小型化、低コスト化を図るため、部品や回路の実装面積を削減することが求められている。
無線通信端末の送信部分には、端末から基地局へ電力を増幅して送信するためのパワーアンプ(電力増幅器)と、その電力の強度を検出する電力検出器が必要となる。近年の無線通信端末は、複数の周波数帯に対応しており、それぞれの周波数帯用のパワーアンプの出力に対して、その個数分の電力検出器が必要になるため、電力検出器の実装面積を削減することは特に重要になっている。
一般的な電力検出器は、分配器を経由して得られたパワーアンプからの小さな信号を高周波増幅器で増幅し、整流などの変換処理を行うことによって検出する。しかし、パワーアンプの広い出力電力に対応して信号を増幅するためには、複数段の高周波増幅器が必要になり、実装面積を小さくすることが困難だった。
また、小型化のための1つの手段としてダイオードを用いて整流する手法が知られているが、ダイオードは温度によって特性が変化するため、単に組み込むだけでは電力検出器の特性が変化してしまう。特に、ダイオードを用いた電力検出器とパワーアンプを集積化した場合、パワーアンプの自己発熱によってチップの温度、すなわち、電力検出器が受ける温度が変動する。この自己発熱量は、パワーアンプの出力電力に応じて変化するため、温度変動によって電力検出の精度が悪化する。
そこで今回、ダイオードを用いて電力検出を行うと同時に、温度補償を実現する技術を開発した。電力検出は、ダイオードを用いて電力に比例する電流を生成することにより実現している。
また、温度変動は、温度によって変化する電流を同じダイオードを用いて別途生成し、検出された電流から差し引くことによって補償する。温度が変化し、ダイオードに流れる電流が変化しても、温度変化に相当する電流を同じ量だけ差し引くことにより、温度に依存せず電力に比例した電流のみが検出できる。
同技術を適用した電力検出器を90nmのCMOSテクノロジーを用いて試作した結果、実装面積を従来の約1mm2から1/25となる0.04mm2に、消費電力を5mWから1/10となる0.3mWにすることが可能となった。
また、-30℃~125℃の温度範囲内において、従来と同等レベルの検出精度(検出誤差が±0.5dB以内に収まる入力ダイナミックレンジは20dB以上)を実現した。今回の試作で対応した周波数は、WCDMAの通信方式で用いられている3つのバンドBand I(2.1GHz帯)、Band V(850MHz帯)、Band IX(1.7GHz帯)だが、LTEに適用することも可能。また、小型・低電力、かつ温度補償機能を搭載しているため、パワーアンプとの集積化も可能になる。