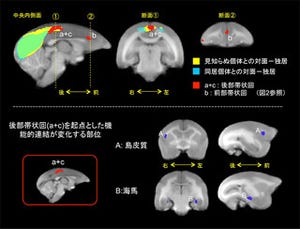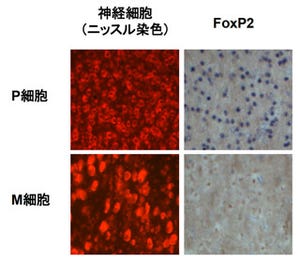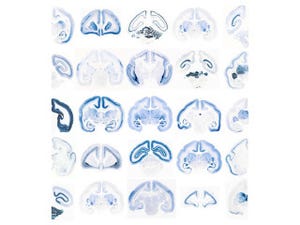京都大学(京大)は、立命館大学と福知山市動物園との共同研究により、テナガザルがヒトのソプラノ歌手と同様の方法で、大きく澄み、朗々とした「ソング」といわれる独特の音声を作り出していることを見出したと発表した。
成果は、京大 霊長類研究所の西村剛准教授、同・香田啓貴助教、同・正高信男教授、同・親川千紗子大学院生(現・東北大学農学研究科助教)、立命館大学理工学部の徳田功准教授、福知山市動物園の二本松俊邦園長らの共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、8月24日付けで米国自然人類学雑誌「American Journal of Physical Anthropology」にオンライン掲載された。
テナガザルは、東南アジアのうっそうとした熱帯雨林の樹冠に生息している類人猿(ヒト上科のサル類)で、チンパンジーやゴリラ、オランウータンなどの大型類人猿に対して、小型類人猿と呼ばれる。
ソングと呼ばれる、大きく澄んだ声で朗々と歌い、音声コミュニケーションをすることで有名だ。そのソングは視界の効かない樹冠でも2km以上聞こえ、霊長類の多様な音声の中でもかなり独特なものとなっている。
一方、ヒトの音声も声は小さいものの、すばやくアイウエオなどの音の種類を変えている点で非常に独特だ。ヒトの音声は、喉にある声帯を呼気で振動させて作る音源により、声帯のある声門から唇に至る空洞である声道内の空気が共鳴して作られる。
この音源と共鳴を独立に変えられる仕組みを「音源-フィルター理論」という。ヒトの音声言語の成立に欠かせない基盤の1つである。音声言語は、その基盤の上に、喉や舌などの音声器官の形態やその運動の仕組みに大きな進化的変更があって成立したと考えられてきた。
ソングを作り出すために、テナガザルにはどんな進化があったのかはこれまで不明であった。例えば、南米のホエザルは、喉の器官形態を大きく変えて、森じゅうに響き渡る大きな声を作り出せるようになっている。しかし、テナガザルには、そのような器官の形態進化が見られない。
一方、大きく澄んだ音を出す管楽器は、ヒトとはまったく違った仕組みで音を作り出しており、そのような仕組みがテナガザルにも備わっているのかも知れないということも考えられていた。
そこで研究グループは、福知山市ならびに福知山市動物園の全面的な協力のもと、シロテテナガザルの「福ちゃん」(メス、当時2歳9カ月齢)にヘリウムガスを吸ってもらうという手法で、その音声を分析したのである。
ヒトの場合、ヘリウムガスを吸うと、声帯での声の高さは変えていないにも関わらず、声道の共鳴が変化して、高く変な声になったように聞こえてしまう。実験の結果、シロテテナガザルにも同様の音声変化が確認された。これは、ヒトと同様に音源-フィルター理論による仕組みの存在を示しており、管楽器などでは起こらない事象だ。
さらに、音声生成の数理モデルを利用して詳細に分析したところ、テナガザルは、声帯で高い音源を作り出し、それを声道の一番共鳴しやすい高さに合わせていることがわかった。これは、ヒトのソプラノ歌手が歌うときの仕組みと同じだという。
この結果はヒトを含む霊長類の多様な音声は、必ずしも音声器官の形態や音声を作り出す仕組みの独自の変化を必要としないことを明らかにしたものとなった。ソプラノ歌唱は、ホール全体に響き渡る美しい歌声で観客を魅了するが、その仕組みから、アイウエオといった音素を判別することが難しい声だ。
テナガザルは、見通しが悪い熱帯雨林で遠くにいる同種個体に自らの存在を伝えるべく、ヒトでもできるソプラノ歌唱をするようになったのだろうと、研究グループは語っている。一方、ヒトは顔を突き合わせる位の距離で、音素がはっきり聞き取れ、かつすばやく変化する声を作り、そこに言語の意味を載せる音声を作り出すようになったと考えられる。
そのような生態環境の変化や社会構造の進化に対応した音声の多様性を進化させるには、音声器官の形態進化や運動進化といった大掛かりな進化ではなく、共通の基盤をどう使うかという運用がより重要な貢献をしていることが示された形だ。
また今回の結果は、ヒトの音声言語を含む霊長類の多様な音声が、従来いわれている以上に、共通する音声器官と音声生成メカニズムで成り立っていることを示し、音声言語の進化プロセスの解明に向けた新しい視点をもたらしたと、研究グループは述べている。