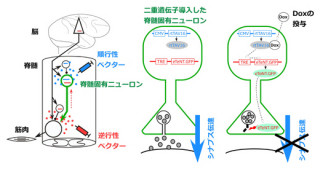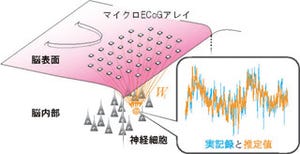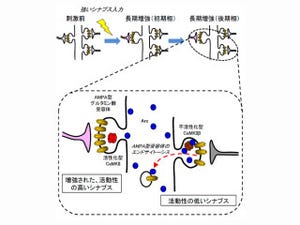東京大学は、運動を学習する場合、記憶を「少しずつ忘れる」ことは、むしろ、運動制御の指令を最適化する効果があることを理論的に証明し、同時に、個々の記憶素子において軽微な忘却が起こることを仮定してニューラルネットワークモデルを構築すると、霊長類の一次運動野神経細胞で観察されるのとほぼ同じ神経活動パターンを再現できることを明らかにしたと発表した。
成果は、東大大学院 教育学研究科 平島雅也助教と野崎大地教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、6月28日付けで米科学誌「PLoS Computational Biology」オンライン版に掲載された。
我々が普段何気なく行っている歩行や、目標物に向かって手を伸ばす動作である「到達動作」は、制御工学の観点からみると非常に洗練されたものだ。筋活動パターンを詳しく調べた研究によれば、目的の動作を実現し得る筋活動パターンは無数に存在するにも関わらず、その中で最も効率のよいパターンが選択されていると報告されている。
無数にある解の中から、1つの解を選ばなくてはならない「冗長性問題」は、多くの筋、関節、神経細胞が関わる身体運動制御を理解する上で重要な問題だ。
これまで、脳はある基準に照らし合わせて最適な解を選び出すことによって、この問題を解決していると考えられてきた。しかしながら、制御工学から提唱された評価基準は数学的に複雑なもので、実際の脳でその計算がどのように行われているのかは明らかではなかった。
運動制御問題における評価基準は、「筋活動の二乗和」あるいは「ニューロン活動の二乗和」であるといわれている。しかし、脳がこのような複雑な計算を行っているという神経科学的証拠はいまだ見つかっておらず、最適化計算の実態は謎に包まれている状況だ。
今回の研究では、発想の転換を行い、工学的な最適化計算と同等のことを、複雑な評価基準を計算することなしに、脳に生得的に備わっている機能だけで行うことができるのではないかと考えた。
そこで注目したのが、「忘却」だ。忘却というと、記憶を阻害するものとして悪いイメージを持つ人が多いかも知れない。しかし、忘却は、古くよりニューラルネットワークの分野において、ネットワーク性能を高める効果があることが知られている。今回の研究では、忘却が運動制御系において有効に機能し得るかどうかを理論的に調べた。
その結果、(1)極めて多くのニューロンが運動課題に参画すること、(2)誤差情報に基づいた運動学習が長期間行われること、(3)忘却率が学習率に比べて極めて小さいこと、などの条件が揃えば、ニューラルネットワークは必ず最適な状態に達し、最も効率のよい神経活動パターンを出力できるようになることを明らかにした(画像4)。
一方、忘却がまったくない場合には、学習に伴って運動誤差は減少するものの(画像1)、神経活動レベルは減少せず、最適な状態に達する前に学習が終了してしまうこと(画像3)が判明。
画像1~4は、ニューロン1000個を用いたシミュレーションの結果だ。画像1と2は、運動誤差の推移を示している。画像3と4の各曲線は、各初期条件から開始したニューロン活動の二乗和の推移を示す。
忘却がまったくない場合には、運動誤差は減少するものの(画像1)、ニューロン活動度は減少せず、最適解には到達しない(画像3)。一方、軽微な忘却がある場合には、運動誤差が減少した後(画像2)、ニューロン活動度は初期条件によらず最適解に達する(画像4)。
また忘却が大きすぎる場合には、必要以上に神経活動レベルが低下して運動課題の遂行ができなくなってしまうことを明らかにした。つまり、軽微な忘却を有する時のみ、ネットワークは最適な状態に達することができるのだ。
もし実際の脳において忘却が機能しているのだとすれば、忘却を有したニューラルネットワークモデルは、実際の脳活動パターンを予測できるはずである。そこで研究グループは、一次運動野及び筋骨格系の解剖学的知見を用いてニューラルネットワークモデルを構築して実験を行った。
そして軽微な忘却条件下において長期間の運動学習を行わせたところ、さまざまな運動課題において、霊長類の一次運動野で観察されるのとほぼ同じ神経活動パターンを再現できることが確認されたのである(画像5~7)。
神経生理学の分野では、到達動作中の一次運動野ニューロン群の「至適方位」(個々のニューロンで最も活動が高くなる運動方向)の分布には偏りがあることが知られており、その発生機序に注目が集まっているところだ。
二次元到達動作中(画像6)及び三次元到達動作中(画像7)の至適方位の偏りが共に、忘却による最適化によって生じ得るという統一的な理論で説明した点も、今回の研究の大きな成果の1つとなっている。
画像5~7は、今回の研究で再現した一次運動野ニューロンの至適方位の偏り。画像5は姿勢保持課題における至適方位のヒストグラムを肩肘トルク平面で示した、2007年のHerter氏の報告を再現したものだ。画像6は、二次元到達動作における至適方位のヒストグラムを外部座標系の水平面内で示したもので、2001年のScott氏の報告を再現している。
画像7は三次元到達動作における至適方位の偏りを球面上の色グラデーションで示したもので、2006年のNaselaris氏の報告を再現した形だ。
今回の研究の結果は、脳の運動学習プロセスにおける軽微な忘却の存在が、運動指令の最適化に貢献している可能性を初めて示したものだ。なお、今回の研究は数式とコンピュータシミュレーションを用いた理論的研究であるため、実際のところ、本当にこの軽微な忘却が最適化に貢献しているのかどうかは定かではないという。
今後、霊長類を用いた電気生理学的実験において、多数のニューロン活動を長期的に調べることによって、忘却の有効性を実証していく必要性が残されている。
しかし、筋の発揮力や神経細胞の活動レベルの二乗和という複雑な量を計算せずに、脳に生得的に備わった機能だけで最適化計算と同等のことが実現できることを示した意義は非常に大きいと考えられると、研究グループはコメントした。
極限のパフォーマンスを目指すスポーツ選手や音楽家では、パフォーマンス低下を恐れるがあまり、過度の練習を行い、心身にさまざまな問題を来たすケースも少なくない。
しかし今回の研究で示した通り、軽微な忘却であれば、それはむしろ効率のよい動作に導いてくれる可能性もあることがわかった。今後、忘却の有効性に関する理解がより深まることで、適度な休息を含んだ効果的な練習スケジューリングの開発などにつながることが期待されると、研究グループは述べている。