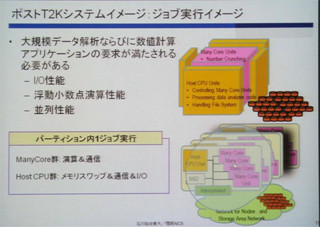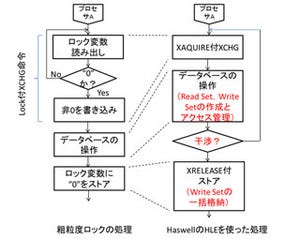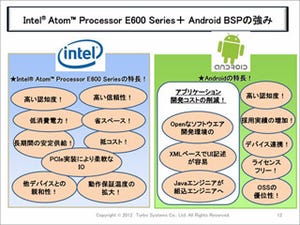Intelは3月6日(米国時間)にSandyBridge-EPというコード名で知られる「Xeon E5ファミリ」の発表を行った。日本においても3月7日に発表会が行われると思うが、まずは同製品の概要をご紹介をしたい。
今回発表された製品は、2P構成に対応した「Xeon E5-2000シリーズ」が17製品、1P構成に対応した「Xeon E5-1000シリーズ」が3製品の合計20製品となる。表1にSKUの一覧を示すが、上は8Core/16Threadから下は2Core/4Threadまで様々である。価格もローエンドは202ドル、ハイエンドは2,057ドルと、こちらも幅広いレンジに展開されている。
製品の構成は、同じくSandyBridge-EPを利用したIntel Core i7-3960X ExtremeとかCore i7-3930K/3820と同じく、内部に8つのコアと8つに分かれたLLC(Last Level Cache)を双方向のリングバスで繋ぎ、ほかにDDR3×4のメモリコントローラとQPI/PCI Express/DMIの各I/Fが搭載されるという構成だ。ダイそのものはこちらと全く同一で、なのでダイサイズは20.8mm×20.9mmの434.7平方mm、トランジスタ数は22.7億個となり、後は製品のSKUでいくつかのCPUとLLCを有効にする/しないが変わるだけである(Photo01)。2P構成の場合がこちら(Photo02)で、従来は6.4GT/sのQPIが1本で2つのCPUを接続していたのが、この世代では8GT/sのQPI×2で接続する形になる。
|
|
|
|
Photo01:Intel Core i7-3960X Extremeなどとの大きな違いは、QPI×2が有効になっていること。これで2P構成を可能にする |
Photo02:理論上はQPIが2本あれば3P以上の構成も可能になるのだが、残念ながらそうしたオプションは用意されていないようだ |
この世代で大きな変革は、まずPCI Express 3.0を最大40レーンも搭載したことである(Photo03)。もっともCPU側にPCI Expressを搭載したのは通信機器向けのJasper ForestことIntel Xeon C5500/C3500シリーズの方が先な気がするのだが、こちらは通信機器向けであってサーバ向けではないということで、この表現になったのだろう。またIntel Turbo Boost Technologyも2.0に進化した(Photo04)。ちなみにこれによってどの程度性能があがるか、を示したのがこちら(Photo05,06)である。
またサーバ向けということで、Intel Node ManagerとIntel Datacenter Managerによる管理機能が搭載されている(Photo07)。
とざっくり機能を紹介したところで、以下若干の補足を。今回のE5-1000/2000シリーズはいずれもLVDDR3に対応しているほか、DDR3-1600までの速度に対応しているのが特徴である。ただし勿論いくつか制限があり
- Unbuffered DIMMの場合、1chあたり最大2枚までに制限され、動作周波数は1333MHzまで
- Registered DIMMの場合、1chあたり最大3枚が可能だが、3枚の場合は最大1066MHzまで。2枚以下の場合は最大1600MHzまで
ということになっているそうだ。
次にチップセット。Xeon E5-1000/2000シリーズには、Patsburgで知られていたIntel C600シリーズチップセットが対応することになるのだが、この構成が少し変である。図1は2P構成での例であるが、片方のE5-2000シリーズのCPUとDMI 2.0経由でつながることになる。従来のESB(Enterprise Southbridge)だとDMIだけでは帯域が足りないため、これに加えてCPUからx4程度のPCI Expressレーンを引っ張り出すのが通例であったし、昨年のCOMPUTEX TAIPEI 2011で展示されたX79マザーボードは、いずれも6GbpsのSASを8ポート装備だったから、単純に考えてもこれだけで48Gbpsに達する。なので、これをフルに生かそうとおもったらCPUとの間に追加でPCIe Gen2 ×8レーンを1本足す(これだけだと微妙に足りないのだが、まぁだいぶマシだろう)必要があると思われたのだが、これも省かれる事になってしまった。
C600には、4種類のSKUが存在しており、それぞれ
- C602(Patsburg-A):Entry向け。SASは未対応で、SATA/3G×4が追加される。
- C604(Patsburg-B):Basic構成。4ポートは同じだがSATA/3GとSAS/3Gの両方に対応。
- C606(Patsburg-D):Performance構成。8ポート構成でSATA/3GとSAS/3Gの両方に対応。CPUに対してPCIe Gen1 x4のUplinkを利用。
- C608(Patsburg-T):Premium構成。C606に加え、SASポートでのRAID 5が構築できる。
という構成になっている。USB 3.0の対応も見送られており、SATA/6Gは2ポートのみ。SASは全量3Gという、非常に微妙な構成になっている。またC606/C608では、追加のPCIe Gen1 ×4はUplinkのみとして使う(Downlinkには利用しない)という話で、また説明によればこれを使わなくても利用できるという話である。
要するに、6Gという高速なPHYを8ポートも追加するのが無理だった、という話なのであろう。非公式ながらPatsburgは最初のステッピングのトラブルの話が絶えず、新ステッピングに作り直したなんて話も漏れ伝わってきているが、この際にトラブルの元になる機能を削った結果として、P67にSAS/SATAポートを最大8つ追加したというような、良く判らない製品になってしまったわけだ。そろそろSAS/12Gに対応した製品も出てきはじめ、主流がSAS/6Gというこのご時勢でSAS/3Gだけのサポートという事にどの程度の意味があるのかはよく判らない。もっと言えば、普通SASを使う場合はオンボードにSASコントローラを搭載する形態が一般的であり、これをチップセットに移動して低価格化を図るという狙いなのであろうが、今度はSASコントローラを交換するためにはチップセットの交換(=マザーボードの交換)が発生してしまうわけで、正直これが賢明な選択なのかどうか、俄かには判断しにくい。おそらくメインストリーム向け製品は、CPUから出るPCIe Gen3レーンにSASコントローラを外付けする形で実装し、低価格向けのみがチップセット上のSASポートを使うといった形になるのではないかと想像される。