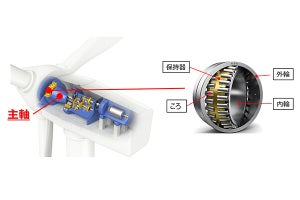石川県金沢市を舞台に、メディアアートとクリエイターの祭典「eAT KANAZAWA 2012」(以下、イート金沢)が1月27、28日に開催された。本レポートでは同イベントの様子を数回にわたってレポートする。
デジタルクリエイターの祭典「eAT KANAZAWA 2012」密着レポート【1】
デジタルクリエイターの祭典「eAT KANAZAWA 2012」密着レポート【2】
デジタルクリエイターの祭典「eAT KANAZAWA 2012」密着レポート【3】
eatの"t"、セミナーA「technology」
本イベント2日目のプログラムは3つのセミナーから始まる。会場は例年と同じく金沢市民芸術村。約9万7,000平方メートルの広大な敷地面積を誇る北陸随一の多目的アートスペースである。本レポートの1回目でお伝えしたとおり、今回のイート金沢は"earth"、"art"、"technology"がキーワードだ。3つのセミナーはこのキーワードに相応しいゲストスピーカーとモデレーターによって進行された。
セミナーAのテーマは「テクノロジー」。モデレーターはイート金沢の中心的人物のひとり・クリエイティブディレクターの宮田人司氏、ゲストにはインフォバーン代表取締役CEOの小林弘人氏、そしてITジャーナリスト・林信行氏という顔ぶれで行われた。
小林氏といえば『ワイアード日本語版』や『サイゾー』の創刊編集長で、昨年はWebクリエーション・アワードでWeb広告賞を受賞するなど、日本を代表するWebメディアプロデューサーである。一方の林氏は、スティーブ・ジョブズやアップル、iPhone、iPadの関連著書ではすっかりお馴染みであり、常に世界の最先端情報を精力的に発信し続けているジャーナリストだ。
テクノロジーと私たちのくらしについて、今なにが起きているのか? ふたりの話をじっくりと聞いてみたい参加者たちの熱い視線がステージに注がれていた。
テクノロジーと私たちのくらし
セレンディピティ(Serendipity)という言葉がある。日本語では偶察力と訳されるが、不思議だなと思うことからヒントを得て探求し、やがてまったく別の新しい価値を見い出す能力を指す。日常の気づきがやがて世界を、我々の生活を変えていくことにつながる。特に今、この偶然を見つける機会が、特定の誰かだけではなく、誰もの日常の中で加速度的に増えているのではないか、という観点からセミナーはスタートした。
偶然を見つける機会がいまなぜ増えているのか? そこには「我々の生活や日常に一気に浸透してきたスマートフォンやタブレットといった新しいコンピュータの形と、ツイッターやフェイスブックに代表される新しい情報流通が起因していると感じる」とモデレーターの宮田氏はいう。クリエイティブやITの仕事に関わる人、あるいはその世界で仕事をしていきたい人たちにとって、この日常の変化はとても重要なアイデアや気づきにつながるのではないか? とも。
「欧米だけでなく、例えばマレーシアといったアジア圏でも『借金してでもスマホは買え』といわれるぐらいスマートフォンは広がっています。少し前に米国のワイアード誌で『Web is Dead』というセンセーショナルなタイトルの特集が組まれましたが、要するにこれからはPCからのインターネット接続ではなく、スマートフォンといった移動体通信端末からのインターネットアクセスが主流になると予測されています」(小林氏)
「とにかくいま、情報もモノも溢れている時代。少し古い話ですが、2009年に発表された日本のある統計によると、我々が情報に触れる機会は12年前に比べて673倍に増えています。人間の脳の処理能力がその間に673倍増えているわけではないから、そのほとんどを我々は毎日捨てていかなければいけない状態。ではそんな時代の中で、逆にどうすれば情報が届けられるのかが重要になってきます」(林氏)
インターネットが普及したこの15年で、我々のワークスタイル、ライフスタイルは様変わりした。一方でそれら情報流通量が増大したことにより、今度は情報を得る・情報を届ける手段に変化が生じている。簡単にいえば、場所やスペースに縛られることのないスマートフォンをはじめとする移動体通信端末の台頭によって、我々はいつでもどこでも情報にアクセスできるようになった。ここを考えるうえで大切なことは、日常における時間軸、人との軸、空間軸(位置情報)がポイントになると林氏は指摘する。
「この3つの軸から生まれたアイデアや発見が、結果として新しいサービスやビジネスにつながっている例は枚挙にいとまがない。例えば、カーナビはわりと前から身近にはあったものの、スマートフォンの登場で一気にもっと一般化しました」(林氏)。そして、一般化したからといって進化が止まるわけではないのがテクノロジーでありセレンディピティである。カーナビでいえば「イスラエルでは、みんなで作るカーナビ『Waze』なるサービスも始まっています。また、新興ビジネスのスタートアップに要する資金集めの場となるクラウドファンディングも3つの軸が変化したことで盛んになってきています」(小林氏)。
では、スマートフォンをはじめとする情報流通テクノロジーの進化があったから新しいサービスやビジネスが誕生しているのか? そこにはもうひとつ、大きな要素が関係している。日常における3つの軸の変化と、結果として生まれた新しいサービスやビジネスの間には、(リアルでバーチャルな)人間を介したソーシャルなコミュニケーションが存在しているということだ。
「このコミュニケーションにはある種の指向性があり、またどちらが発信者でどちらが受信者ということではなく、例えばソーシャル上で専門性や見識、有益な情報を発信すると、結果として自分に戻ってくる特徴があります。わかりやすくいえば、ネットの情報は発信する人に、情報も人も集まってくるということ。ツイッターのフォロワーがよい例だ。その情報流通が瞬時になりました」(小林氏)
「ギブアンドテイクの法則で、まずはギブすることは大切。また、感染というキーワードもモチベーションの維持と拡大には重要だと思います。賛同者がいるとわかるだけで情熱を持ち続けられる。一方で、なにかを伝えようとする際に気をつけなければいけないのは、わかりやすさ、シンプルなものであること」(林氏)
モチベーションとリテラシー
セミナー中盤からは、林、小林両氏から「結果として生まれた」世界で始まっている新しいサービスやビジネスの具体事例が多く紹介された。どれも関わる人達のモチベーションが伝わるものばかりだった。ただし、振り返って今の日本の状況を見ると、資本主義社会が行き着くところまでいってしまっている現在、なぜ日本の産業界も教育体系も停滞したままなのか、新しいことをしていくうえでのモチベーションが、どこか持てない雰囲気があるように思えてならない。会場から講師に対し以下の質問が上がった。
ーー若い世代がこれからなにかに気づき、モチベーションを持って新しいことに取り組んでいけるためにはどんなことが必要だと考えているか?
「私は『失敗』だと思います。失敗することが許容される企業体質だったり教育環境だったり、そういう組織体系にならない限りは、例えばなにかの新しいマーケティングをやるにしても、上司が『それ本当に売れるのかよ?』と、なにもしないうちから、自分が見てきたものの延長線で物事を判断されてしまう。それがいけない。だってやってみなきゃわからないんだから。で、結果、今、これが店頭で伸びています、だからこれをやりましょうとなって二番煎じ的なものばかりが溢れる。新しいものを提示しない限りイノベーションは生まれません。それには失敗は必ずあって、成功はたくさんの屍のうえでが旗が立っているはず。だからその失敗や失敗した人も再び巡回できて、その失敗を許容できる環境が必要だと思います。そういう意味では今の日本企業はリスクに対する許容量が低く、失敗の経験は本来とてもいいことなのに、失敗に対する恐れが強いのだと思います」(小林)
「日本は失敗したチームはすぐ解散させられる。失敗は成功に至る過程でしかないのに。ただ、企業や組織がそういう体質を変えていくことも大切ですが、失敗した本人がそこでくじけるのではなく、どうしてもこれをやるんだという気持ちを持ち続けることは重要。実は我々はとても狭い世界で生きていて、ほんの一歩外へ出るだけで、あるいは新しい人と出会うことで、これまで解決できなかったものが一気に進むことはよくあります。それもセレンディピティでしょう」(林)
豊かなくらしの定義は時代、教育体系、世代、あるいは個人の考え方でさまざまだが、インターネットはそもそも誰かのものではなくみんなのものだ。そこは共有、シェアの発想から築きあげられた世界であって、オープンに誰もが利用し簡単に活用できる環境がある。その意味ではすでにこの環境が当たり前の世代にとって、開かれた世界、シェアのパワーをどう利用するのかという発想こそがモチベーションになり、新たなビジネスモデルの構築にもつながるが、理解しておかなければいけないのは、テクノロジーやインターネットはあらゆるものをパワフルに増幅させる側面を持っているということ。
「オープンである以上、それを使うにはリアルな社会と同じように責任が伴うし、リテラシーを持たなければいけないでしょう。この教育は最低限必要なこと。そのうえで、パワーを増幅してくれるテクノロジーをどう使っていくのかが大切だと思います」(小林氏)
ますます当たり前なものとして身近に存在するインターネットとテクノロジー。回避する発想やスタンスだけではなく、受け入れてこそなにかに気づける。そこに新しい「豊かなくらし」が見えてくるのかもしれない。