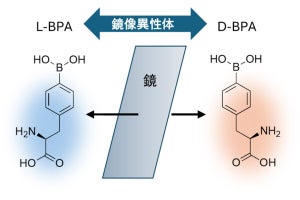大阪大学(阪大)、理化学研究所(理研)、横浜市立大学、東京工業大学(東工大)、常磐植物化学研究所、千葉大学で構成される研究グループは、レアプラントとして価格が高騰してきているマメ科の薬用植物「甘草」(カンゾウ)の主活性成分である「グリチルリチン」生合成のカギとなる酵素遺伝子を明らかにし、酵母で「グリチルレチン酸」の生産に成功したと共同で発表した。阪大 大学院工学研究科の村中俊哉教授らによるもので、成果は米科学雑誌「The Plant Cell」に掲載予定で、それに先だって近日中にオンライン版に掲載される。
甘草(画像1)の地下部(肥大根および地下茎)は「甘草根」と呼ばれ、医薬品、化粧品のほか、甘味料原料として大きな需要があり、世界市場における甘草根の年間輸出額は4200万ドルにものぼるという。
また、甘草根は日本薬局方に収載されている210種類の漢方処方の70%に配合されており、最も使用量の多い生薬となっている(画像2)。さらには、甘草根から抽出される、計30の炭素数で構成されている化合物群「トリテルペン配糖体」の1種であるグリチルリチンが、肝機能補強機能、抗ウイルス作用など多様な薬理活性を持つ。そのため、医薬品や化粧品として多用されているという次第だ。
さらに、砂糖の150~300倍もの甘みを持ちながら低カロリー(一般にゼロカロリーとされる)の非糖質系甘味料であることから、メタボリック症候群の予防にも役立つとして注目され、数多くの食品にも添加されている。
そのほかにも、甘草が米国立がん研究所にもニンニクなどと並んでがん予防に最も効果的な食品の1つとしても位置づけられており、洋の東西を問わずに健康に必要な化合物として注目されている状況だ。
その甘草根の供給は、中国、中近東などの乾燥地域である。自生する野生種に依存しているのが難点で、1kgの甘草の採取で5平方メートルの草原が破壊されるといった報告もあるなど、環境破壊の問題を抱えているのが現状だ。そのため、主産国の中国ではレアアース同様にレアプラントの採取・輸出規制が始まっており、今後の輸入価格の高騰と供給の不安定化への懸念が高まっている。モンゴルなどにおいては栽培化への取り組みも実施中なのだが、栽培品ではグリチルリチンの蓄積量が低いという問題があり、うまくいっていない。
良質の甘草根およびその成分を安定かつ持続的に供給するには、栽培条件の最適化や品種改良などの生産技術の確立が重要だ。さらに、将来的なグリチルリチン高生産品種の分子育種や、発酵工業的手法によるグリチルリチン生産のためにも、生合成機構の解明と合成酵素の同定が必要不可欠である。
しかし、それらについての知見はほとんどなく、そこで今回、グリチルリチン生合成分子機構の解明に向けて、生物有機化学的手法、分子生物学的手法、組織培養法など、さまざまなテクノロジーを駆使して、オールジャパンともいえる体制を組織し、研究が進められたというわけだ。
グリチルリチンの構造は、多くの植物に共通に存在している「トリテルペン」(トリテルペン配糖体に糖がついていない段階の化合物)の1種である「β-アミリン」が炭素骨格となり、その11位と30位の炭素に対する酸化反応と、3位水酸基への配糖化反応により生合成されると考えられている(画像3)。
甘草に特異的なこれらの反応ステップには、それぞれ2つの酸化酵素と配糖化酵素が関与すると推定された。「酸化テルペノイド」を含む多様な植物2次代謝産物の生合成においては、「シトクロムP450」(アミノ酸からなるタンパク質に加えてヘムを持ち、酸素分子をさまざまな分子に添加する働きを持つ酵素群)と呼ばれる一群の酸化酵素が関与することが確認されている。
研究グループは2008年、ウラルカンゾウ(学名:Glycyrrhiza uralensis)の地下茎から作成した完全長「cDNAライブラリー」(機能のある遺伝子として発現しているmRNAを、人工的にコピーした相補的(complementary)DNAのライブラリーのこと)の合計5万6000EST(cDNAライブラリーの内、末端の数百塩基程度の配列を決定したものを、EST(Expressed Sequence Tag)と呼ぶ)を利用し、β-アミリンの11位の2段階の水酸化反応を触媒し、グリチルリチンの生合成中間体の1つである「11-オキソ-β-アミリン」に変換するシトクロムP450(CYP88D6)を特定することに、世界で初めて成功したという実績を持つ。
今回の研究では、CYP88D6とは異なるファミリに属する別のシトクロムP450タンパク質が30位炭素の酸化に関わることを明らかにし、「CYP72A154」と命名した。シトクロムP450は、アミノ酸配列が40%以上一致すると同一ファミリーに、55%以上の一致で同一サブファミリに分類される。
CYP72A154の機能を解明するため、研究グループはまず「バキュロウイルス/昆虫細胞系」を用いて、タンパク質を発現させた。ちなみにバキュロウイルスは、昆虫細胞に感染する2本鎖DNAウイルスで、核多角体病ウイルスとも呼ばれている。感染細胞内でタンパク質「ポリヘドリン」を大量合成し、感染後期には全細胞タンパク質の半分近くにも達するという特徴をも持つ。ポリヘドリン遺伝子の強力なプロモーターの下流に外来遺伝子を連結し、昆虫細胞に感染させることで、昆虫細胞内で組み換えタンパク質の合成を行うことができるのである。
そして、CYP72A154を含む「ミクロソーム画分」(ほとんどのP450タンパク質は小胞体膜上に局在しており、そのほか細胞膜やゴルジ体などを含む画分のこと)を用いた試験管内での酵素反応実験を行った。
結果、CYP72A154が1-オキソ-β-アミリンの30位の3段階の水酸化反応を触媒し、グリチルリチンよりも高い抗炎症作用や抗アレルギー作用を有するグリチルレチン酸(グリチルリチンの非糖部に相当)に変換する活性を持つことを明らかにしたのである(画像3)。
研究チームは続いて、別のマメ科植物「ミヤコグサ」から単離していたβ-アミリン合成酵素遺伝子とCYP88D6遺伝子を同時導入して、11-オキソ-β-アミリンを生産するように改変した酵母を作出した後、さらにCYP72A154遺伝子を導入(画像4)。その結果、この酵母は、微量ながらもグリチルレチン酸を生産することを確認した。これにより、グリチルリチン生合成に関わる2つの酸化酵素の両方を特定することに成功し、グリチルリチンやその関連成分のバイオテクノロジー生産への道筋を示したのである。
|
|
|
画像4。組み換え酵母におけるグリチルレチン酸生合成経路再構築の概略図。β-アミリン合成酵素(黒い実線矢印)、CYP88D6(青い矢印)、およびCYP72A154(赤い矢印)をそれぞれコードする遺伝子を酵母に導入することで、酵母内在のステロール合成経路の中間物質である「2,3-オキシドスクアレン」から分岐するグリチルレチン酸生合成経路を再構築した |
研究グループは、今回の解明により、今後は組み換え酵母における生産性の向上を進めることにより、発酵工業的手法によるグリチルレチン酸の生産に応用ができると期待されるとしている。