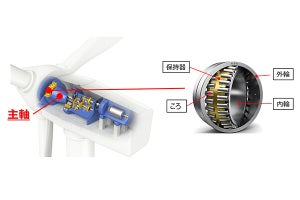これまでアクション映画や子供向け映画に有効な映像技術であり、すべてのジャンルの作品に向いている技術ではないとされてきた立体映像。現在公開中の時代劇映画『一命』では、時代劇初となる3Dを導入している。3Dは時代劇に何をもたらしたのか、本作の3Dスーパーバイザーとして参加した灰原光晴氏に話を聞いた。
映画『一命』は時代劇に初めて立体映像を導入した作品。立体映像化への道は、監督やカメラマンなどの制作スタッフに「3D映像制作の基礎知識」についてレクチャーするところから始まったという。三池崇史監督は本誌のインタビューにおいて「作品内容と最新映像技術(立体映像)というアンバランスさがすてきだなと思って撮影を決めました」と話しており、本作の立体映像のテーマに"さりげない3D"を掲げていた。
この作品の特徴に、画面の背景や美術の色鮮やかさがある。その要因のひとつとなっているのが立体映像で、奥行きのある映像にすることで、役者の演技を邪魔することなく、背景も自然と目に入ってくるようになっている。灰原氏は「3Dカメラの設定で、3D感を強調することも抑えることも可能です。したがって、シーンによって3D感の強弱があります。また、3D感はカメラの設定だけではなく、セットや小道具などの美術や衣装の素材、雨や雪の効果、色彩の鮮やかさ、なども大きな役目を果たします。この作品の場合、立体映像を用いたことにより、俳優さんの表情や衣装、小道具、美術をより堪能できるようになったのではないか」と、その効果を話している。
実際、役者の表情も立体映像を用いたことで、アップにならずとも観客の記憶に残りやすくなり、それは、津雲半四郎(市川海老蔵)と斎藤勘解由(役所広司)の庭先での掛け合いで見事に表現。ちょっとした動きや表情の変化を立体映像で表現したことで、静かな映像でありながらも、迫力のある映像に仕上がっている。
|
|
立体映像を用いた場合、一般的な2D作品に比べ、制作費が高くなるイメージがあるが、本作では立体映像の制作で最もお金のかかるVFXを極力使わないようセットを多用。その結果、美術費は増えたがVFXにかかる費用は少なくなったという |
また、「日本家屋は武家屋敷でも貧乏長屋でも、その質感は3Dに向いていると思いました」(灰原氏)というように、時代劇ならではの醍醐味もあるようだ。立体映像を利用することで、役者の演技に観客を集中させ、言葉の少ないシーンにおいても映像だけで観客に語りかけることに成功し、なおかつ、日本にある美しい四季も表現した本作。映画『一命』の出現により、立体映像の将来に新たな可能性を見出したといっても過言ではないだろう。
まだまだ発展途上の3D映像制作の世界だが、今後はどのように進化していくのだろうか。灰原氏は「この秋に家庭用のヘッドマウントディスプレイが登場するなど、3Dを見る環境はまだまだ進化しています。その進化に合わせて、さまざまな楽しみ方が増えるのではないでしょうか。これからは一時のブームに押されてというのではなく、3Dである必然性を制作者が意図し、生み出されていく作品が増えていくと思います」と語った。
映画『一命』は、全国公開中。