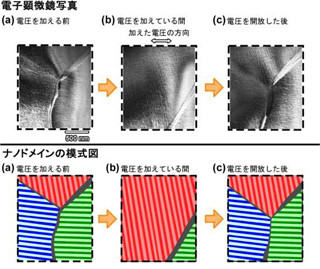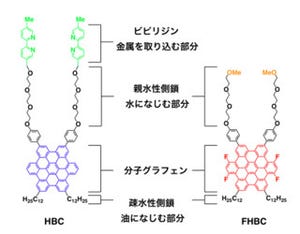東京大学の研究チームは、好熱菌の炭素・窒素代謝を連結する酵素であるグルタミン酸脱水素酵素(GDH)とロイシンとの複合体の立体構造を明らかにし、アロステリック制御機構を解明し、ロイシンによるアロステリック制御機構がヒトなど哺乳類由来GDHと共通している可能性を示した。同成果は、同大生物生産工学研究センターの富田武郎 助教、同 葛山智久 准教授、同 西山真 教授らによるもので、米国生化学分子生物学会の学術誌「Journal of Biological Chemistry(JBC)」に掲載された。 GDHは、α-ケトグルタル酸とグルタミン酸との間の可逆的変換を触媒する酵素だ。炭素・窒素代謝を連結する代謝の中枢を担うために、ほとんどの生物がこの酵素を有している。好熱菌Thermus thermophilus由来GDHはロイシンによって強く活性化を受けるという特徴を有している。今回、研究チームはT. thermophilusのGDHとロイシンとの複合体の結晶構造を、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の物質構造科学研究所放射光科学研究施設を用いて明らかにした。
一般に、GDHは同一サブユニット6個からなるホモ6量体を形成することが知られているが、決定した構造は、互いに相同性を有するGdhA(制御サブユニット)4つとGdhB(触媒サブユニット)2つから構成されるヘテロ6量体であり、GDHとしては初めてのヘテロ6量体の構造となった。
それらサブユニット間の境界領域に存在するポケットにロイシンが結合していることが見出され、同部位へのロイシンの結合がGDHの活性化を引き起こすことが明らかとなった。
一方、ヒトやウシのGDHもロイシンによって活性化されることが知られているが、その機構は不明なままであった。
研究チームがアミノ酸配列を比較したところ、T. thermophilusのGDHにおいてロイシン結合に関わるアミノ酸残基がヒトやウシのGDHにも保存されており、哺乳類のGDHもまた同様な機構でロイシンによって活性化される可能性が考えられた。
そこで、保存アミノ酸をロイシンが結合できなくなるように置換したヒトGDH2の変異酵素を作製し、ロイシンに対する感受性の変化を調べたところ、各変異体はロイシンによる活性化能を消失していることが判明した。この結果は、栄養シグナルとして機能するロイシンのセンシング機構の一端を明らかにしただけでなく、哺乳類のGDHの活性化についても重要な情報を提示することになったという。
哺乳類のGDHは複雑に制御され、GDH活性の脱制御を与える変異のいくつかは高インスリン症/高アンモニア血症の原因と同定されており、今回の成果によりロイシンの生体調節因子としての機能の解明につながる可能性が出てくることから、GDHをターゲットとした創薬開発にも結び付くものと期待されると研究チームでは説明している。