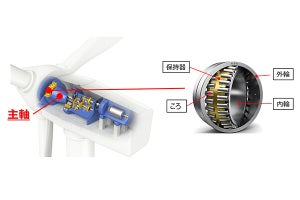「デザインの寿命を長くすること」をスローガンに掲げ、展示期間を終えたフラッグやテント等の素材をリサイクルバッグに作り変える活動を行うクリエイティブ集団「蝉 semi」。そのスローガンとプロダクトのデザインに対する共感により、クリエイティブな層から徐々に広まりつつある彼らが、多摩美術大学 上野毛キャンパスにて開催された「第1回産廃サミット」で新作を初披露した。
街を思う気持がきっかけに
2010年、彼らが大学院2年目のとき、六本木の商店街で展開したフラッグデザインコンテストが「蝉 semi」誕生のきっかけ。当時、六本木商店街振興組合には「六本木ヒルズと東京ミッドタウンだけが目立っているこの街の回遊性を上げたい」、「夜の街というイメージを払拭できない」という課題があった。そこで同じKMD(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)の同級生で町づくりに興味があった同志が、デザインで何かできないかと考えて提案し、実施に至ったのだという。
消費されないデザインを目指す
代表の石川氏は以前、吉田カバンやIKEAといったデザインプロダクトのメーカーに所属しており、当時は、自分のデザインしたディスプレイや製品が期間や目的を果たしたのち、すぐに廃棄されることに疑問を感じていたという。この疑問に対する返答のひとつとして、一番自分が得意とするバッグ制作という分野でなにかできないかと試行錯誤していたという。
また、もう一つ抱いていた課題として「製品が世の中に出る出口のところまでブランド全体をコントロールすることが困難だった」とも語る。「蝉 semiでは、どう作って、どう見せて、どう売るかというところまですべて自分たちで行います。短期的な収益を得ることも大事ですが、手間ひまかけて出口まで自分たちでずっとやっていきたいんです」。蝉 semiのスタイルは、こうした過去の課題によるものだったのだ。
次の「かっこいい」を見つけること
プロモーション設計を担当する鎌田氏は、また別の想いで蝉 semiに携わっている。「僕の個人的な感覚として、いわゆるブランドものに執着する人が少なくなってきている気がします。それはものすごく市場が成熟しているから。かっこいいものを出されても『もう知っているよ』と言われてしまう。先進国の次の"かっこいい"は、ブランドが生まれた背景への共感とプロダクトの見た目としてのデザイン性の両立だと思っています。そして、そういうものほど人に薦めたくなる。そんなブランド、プロダクトを生み出していきたいです」。
企業ブランディングを本業で支援している彼だからこそ見つけられた課題であり、いまの時代に求められるチャレンジでもあるのだろう。
「インタラクション」の実現へ
Webサイトのインタラクション設計を担当する鹿毛氏は、「今は自分たちが素材を持ち寄っていますが、必ずしも自分たちである必要はないと思っています」と語り、カスタマーやデザイナーが素材を持ち寄る仕組みを作れたら面白いのではないかと、日々模索しているという。また、素材やネーム入れの指定など、既存のWebサイトにスパイスとしてのいろんな仕掛けを構想しているそうだ。
彼はデザイナーとのインタラクションこそが、いままでにない「かっこいい」につながるのではないかと考えている。そして、そのインタラクションがプロダクトに対する愛着にもつながり、デザインの寿命を長くするという蝉 semiのコンセプトにもつながってくるのだ。
進化する「蝉 semi」
今回発表された新作の素材には、製造中止となってしまったサンルーフの素材、つまり「産業廃棄物」を使用している。石川氏が訪ねた工場で、使い道なく放置されていたものだという。一般的にはゴミとされるものではあるが、素材のストロングポイントを最大限に活かし、デザインプロダクトとしてクオリティーの高いものをアウトプットした。「売れなかったもの、製造中止になったもの、未使用に近い新品など、産業廃棄物の二次利用という背景に共感してもらえたら嬉しいです。それと同時に、デザインプロダクトとしての魅力も感じてほしい」と思いを語った。
幸いなことに、プロダクトやデザインの消費という傾向は、表面的にはずいぶん改善されてきたそうだ。しかし一方で、イベントで使われた素材など、一般の人の目に触れないところでは改善されていないとも感じているという。
また今後、蝉 semiをビジネスとして大きくしていくにあたって避けられない「自動化」。彼らはそのプロセスの中にも、人の手やぬくもりを盛り込んでいくことで面白いものをつくりたいと語った。こうした彼らの課題に対する向き合い方に、これまでのクリエイティブと評される集団との違いを感じた。