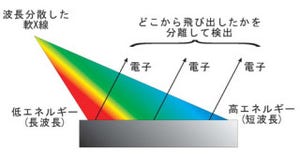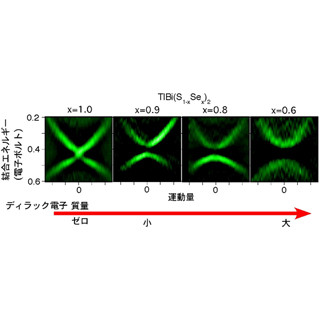大型ハドロン衝突型加速器(LHC)を利用した国際的な大規模実験「アトラス」(ATLAS:A Toroidal LHC Apparatus)に参加している日本グループは9月6日、陽子・陽子非弾性散乱断面積の測定結果を、同日公開の「Nature」誌の電子版に掲載したと発表した。
陽子・陽子衝突の断面積(散乱確率)は、素粒子物理学の基本的な物理量を示す。また、地球に飛来する高エネルギーの宇宙線と大気との反応や、将来のより高いエネルギー加速器での衝突頻度を見積もる上でも重量な量だ。
今回の研究は、欧州合同原子核研究機関「CERN」に建設されたLHC加速器でのアトラス実験による衝突エネルギー7TeVでの結果である。陽子・陽子衝突反応としては、LHC以前のデータと比べてほぼ100倍近い衝突エネルギーの測定となっている。
これまでの実験により、陽子・陽子の非弾性散乱の断面積は、大まかにはエネルギーによらずほぼ一定であることが判明した。これは、陽子がクォークやグルーオンから構成された物質でできた球体で、球体同士が重なれば散乱を起こすと考えると、その散乱確率は球体の速度によらないということから説明可能だ。
しかし、より詳細に調査すると、断面積はエネルギーの増加に伴い緩やかに上昇することがわかった。これは、陽子がエネルギーとともに緩やかに膨張していることを示す。だが、量子色力学を使ってもこの現象を定量的に計算することは、現在のところできていない。そのため、さまざまな実効理論が提唱されているという次第だ。
今回の測定では、重心系エネルギー7TeVの衝突で、励起エネルギーが15.7GeV以上ある非弾性散乱の断面積が求められた。その結果、エネルギーに対する断面積の増加がやや緩やかな理論との一致がよいことが判明した。
また、従来の実験と直接比較するために、全励起エネルギー領域へ断面積を外挿。比較の結果、断面積が増加傾向にあることは確認できたものの、外挿の不定性が大きく、幅広い理論の予想と矛盾しない結果となっている。
アトラス実験では、ヒッグス粒子や超対称性粒子の発見が重要な目的となっているが、同時に今回の解析のように、陽子の基本反応量の測定や標準理論の精密測定など、広範囲の研究が進められている。
今回の実験は2010年3月31日に最初に行われた7TeV衝突のわずか数時間のデータからのもの。2011年9月初めまでに、その1億倍以上のデータの収集が完了しており、よりまれな事象の探索が進んでいる。