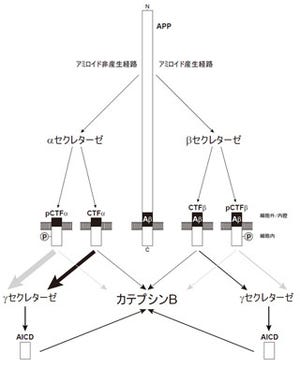理化学研究所(理研)は、たんぱく質などの生体分子が持つ状態(構造)と、それぞれの状態形成に重要な役割を果たす水などの環境分子との分子間相互作用を、相互作用の種類や原子間の距離情報を含めて体系的に明らかにする計算手法「DIPA(Distance-dependent intermolecular perturbation analysis:ディーパ)」を開発した。
同成果は、理研生命システム研究センター 合成生物学研究グループの小山洋平特別研究員、上田泰己グループディレクターと東京大学 生産技術研究所の小林徹也講師との共同研究によるもので、米国の科学雑誌「Physical Review E」のオンライン版に掲載された。
たんぱく質やDNAなどの生体分子は、同じ分子であっても、状態(構造)によって異なる働きを示して複雑な機能を発揮するため、生体分子の機能を理解するには、生体分子の状態を明らかにし、その状態を変化させる制御機構を理解することが重要となる。
生体分子の状態変化は、生体分子内の相互作用(共有結合、ファンデルワールス相互作用、静電相互作用)だけでなく、水やイオン、化合物など周りの環境分子との相互作用(ファンデルワールス相互作用、静電相互作用)からも大きな影響を受けるが、生体分子と環境分子との相互作用は複雑であり、これまでの生体分子の状態の解析では、生体分子内の原子の位置など、その分子内部の情報だけを利用してきたため、環境分子の寄与まで含めた詳細かつ体系的な解析ができていなかった。
同研究グループはすでに2008年に、生体分子内の原子間相互作用のエネルギー(ポテンシャルエネルギー)に対して主成分分析を行うPEPCA(ペプカ)を開発していたが、PEPCAは、たんぱく質の折り畳み(フォールディング)などの大きな構造変化を解析できるが、環境分子の寄与を解析することはできなかったため、生体分子と環境分子との間の相互作用を扱えるようにPEPCAを拡張した「IPA(Intermolecular perturbation analysis:アイピーエー)」をさらに開発していた。
IPAは分子間相互作用のポテンシャルエネルギーの平均値に対して主成分分析を行うものだが、実際に、1個のアミノ酸の両端にアセチル基(CH3-CO-)とN-メチル基(-NH-CH3)が結合した小分子(アラニンジペプチド)の水中での様子をシミュレーションし、IPAで解析したところ、3つある状態のうち2つの状態をうまく分離できなかった。その原因を詳細に検討した結果、ペプチドの状態の識別には、ペプチドと水の間の距離の情報が重要であることが判明し、研究グループでは分子間の距離の情報を扱えるようにIPAをさらに拡張した「DIPA」を今回、開発した。
DIPAは、ある距離での分子間相互作用(ファンデルワールス相互作用、静電相互作用)と、その距離の範囲内にある平均環境原子数の積に対して関数主成分分析を行う。こうしてDIPAは3つの状態を識別できるとともに、それぞれの状態に対して重要なアラニンジペプチド分子と水分子との相互作用を明らかにすることができるようになった。
またIPAでは、構造への寄与が小さい長距離の相互作用が解析結果の精度を悪くするのに対し、DIPAでは距離の情報を取り入れることで、重要な寄与をする近距離からの相互作用だけを取り出し、寄与が小さい長距離からの相互作用を分離できるため、IPAと比べ計算時間を10分の1程度に短縮できるようになった。
研究グループでは、より現実的な問題にDIPAを適用できるかどうかを検証するために、10個のアミノ酸が連なった最小クラスのタンパク質「シニョリン」が水中で折り畳まれていく様子をシミュレーションした。まず、シニョリンがどのような状態を持ち、シニョリン内のどの相互作用が重要であるかを明らかにするために、PEPCAを適用してバイプロットで表示したところ、4つの状態(正しく折り畳まれた状態、誤って折り畳まれた状態1と2、ほどけた状態)が明らかになったほか、それぞれの状態で安定化するためには、シニョリン内のどの原子とどの原子の静電相互作用が重要であるかも判明した。
次に、PEPCAでは解析することができない環境分子(水分子)の役割を明らかにするために、DIPAを適用してバイプロットで表示したところ、PEPCAと同じ4つの状態を確認することができた。
DIPAでは、シニョリン内部の情報を直接的には用いていないが、シニョリンの状態が変化すると周囲の水分子との相互作用の様子が変わるため、このパターンを見分けてシニョリンの4つの状態を識別できたほか、それぞれの状態に重要な水とシニョリンとの静電相互作用も明らかにすることができたという。例えば、「正しく折り畳まれた状態」に対して2つの「誤って折り畳まれた状態」のほうが安定化している原因の1つには、8番目のアミノ酸の酸素原子と水の水素原子との静電相互作用があり、特に、その距離が約6Åのとき、最も影響の大きいことが判明した。
今後、京速コンピュータ「京」などのペタフロップス級のスーパーコンピュータが本格稼働することで、多くの生体分子が機能を発揮し始める様子の再現に必要な、マイクロ秒単位のシミュレーションを多数実行することが可能になってくる。そうしたシミュレーションの結果をDIPAで解析することができれば、環境分子による生体分子機能の制御メカニズムをより詳細に理解できるようになるほか、明らかにした分子間相互作用のパターンと似た薬剤を探索することで、生体分子の状態を選択的に変化させ、分子機能を人工的に制御することが可能になることから、今回の成果は創薬への応用にも期待できると研究グループでは説明している。