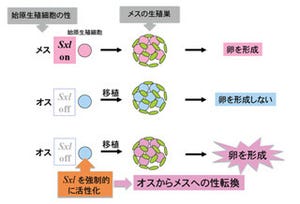自然科学研究機構 基礎生物学研究所(NIBB) 統合神経生物学研究部門の野田昌晴教授らの研究グループは、トウガラシの辛味成分(カプサイシン)や熱、酸などの浸害刺激に応答して開口するチャンネル分子として有名な「TRPV1」チャンネルを発現する細胞株を用いて、TRPV1が体温付近の温度で浸透圧感受性を示すことを確認すると共に、その応答がカプサイシンや酸によっても相乗的に増強されることを見出した。同成果は米国の科学雑誌「PLoS ONE」に掲載された。
ヒトの体液(血液、脳脊髄液等の細胞外液)の浸透圧は常に約300mOsm/kgに保たれているが、この体液圧を保つことは生命維持のために必須であり、そのためヒトの体は体液の浸透圧を監視する仕組みを備えている。脱水などにより体液の浸透圧が上昇した場合には、口渇感を感じて飲水するとともに、脳下垂体から抗利尿ホルモン(バソプレッシン)が血中に放出され、腎臓において尿量を減少させるなどの反応が出ることになるが、TRPV1の遺伝子を欠損したマウスでは、体液浸透圧の制御において異常を示すことから、TPV1が浸透圧センサ分子の候補であるとも言われていたが、TRPV1が実際に浸透圧感受性を持つことは確認されていなかった。
今回、研究グループは、ラットのTRPV1の全長を安定的に発現した細胞株を用いて細胞内Ca2+イメージングを行なうことによって、TRPV1が体温付近で浸透圧感受性を示すことを確認した。この浸透圧への応答は、室温付近(24℃)ではごくわずかであったものが、温度の上昇と共に増大し、哺乳類の体温に近い36℃付近で最大となった。
次に、36℃に保って浸透圧を変動させたところ、300mOsm/kg(平常時の体液浸透圧)を境に、それよりも低浸透圧側では細胞内へのCa2+流入が減少するのに対し、高浸透圧側ではCa2+流入が大きく増加することが明らかになった。
このようにTRPV1は、体液浸透圧の上昇をより良く感知する性質を持つことが判明したほか、アクアポリン(水チャンネル)を阻害して、浸透圧変化による細胞容積の変化を抑えると、応答が減弱したことから、TRPV1は浸透圧の変動に伴う細胞膜の張力の変化を感知して開口している可能性が示唆された。
TRPV1の浸透圧に対する応答は温度により増強されたが、さらに酸やカプサイシンによっても同様に相乗的に増強されることが判明したほか、カプサイシンに対する応答も浸透圧上昇によって増強されることも分かったことから、TRPV1は複数の異なる活性化刺激を統合する性質があることが明らかになった。
|
|
|
TRPV1は43℃以上の熱、酸、化学物質(カプサイシンなど)の浸害刺激で活性化することが知られていたが、今回、体温付近では浸透圧上昇の刺激によっても活性化することが判った。また、この浸透圧感受性は、他の刺激、酸やカプサイシンによっても増強されることが判った。これにより、TRPV1はこれらの異なる刺激を統合する役割を果たしていると考えられる |
今回の結果は、全長型のTRPV1が生体内の高浸透圧センサとして機能し得るということを証明したものであるほか、TRPV1が異なる刺激を統合するという発見は、いくつかの疾患に伴う生理現象の理解に貢献するものであると研究グループでは説明している。例えば、糖尿病患者の主要な症状に多飲があるが、糖尿病の急性の合併症としてアシドーシス(酸性血症)が知られており、同症状はTRPV1によって体液浸透圧の上昇が感知され飲水が誘発されていると考えられているが、糖尿病患者ではアシドーシスによってこれが増強されている可能性が考えられるという。
また、感染や炎症、虚血等によって組織が酸性化すると、TRPV1がそれを感知し、痛覚が生じることが知られているが、傷害部位においては浸透圧も上昇することから、傷害部位の酸性化と浸透圧上昇が相乗的にTRPV1を活性化することで、痛みをより鋭敏に感知する機構として働いているのではないかと考えられるという。