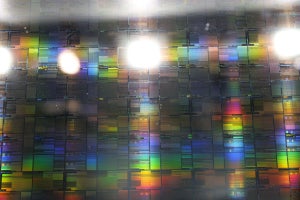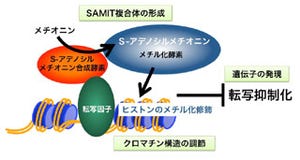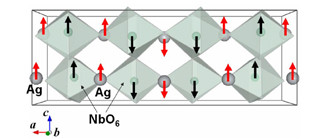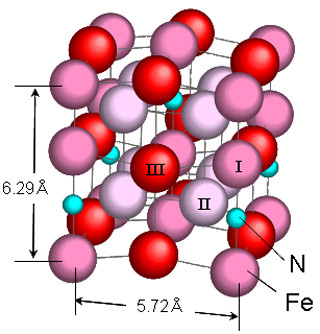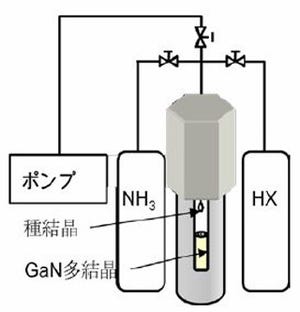東北大学大学院工学研究科の西澤松彦教授は、産業技術総合研究所(産総研)と共同で、酵素とカーボンナノチューブ(CNT)が均一に複合化したフィルムを開発した。これは、「貼ったり」「巻いたり」して使える柔軟な酵素電極シールで、触媒活性も従来の数倍以上とのことで、果糖を分解する酵素と、酸素を分解する酵素を含むシール2枚で作ったバイオ電池は、果糖水溶液から過去最高の出力密度で発電したという。同成果の一部は2011年3月10日に米国化学会誌「Journal of The American Chemical Society」にオンライン掲載された。
バイオ電池やバイオセンサに必要な酵素電極(酵素を固定化した電極)の作製は、まず炭素のナノ粒子やナノチューブを固めて電極を作り、そこへ"後から"酵素溶液を塗布する2段階の方法で行われてきた。
これは電極を作る時の加熱などに酵素が耐えないためだが、同法では、電極内部の微細構造への十分な酵素導入が困難であった。今回の共同研究では、"酵素のサイズに合わせて電極が収縮する"という1段階のプロセスを実現し、同問題を解決した。
酵素を固定した電極(酵素電極)は、電気化学バイオセンサやバイオ電池の性能を決定するコア部品で、バイオセンサは医療・環境・食品分野の計測で用いられており、一方のバイオ電池も生体・環境に優しい安全な電源として今後の実用化が期待されている。
最近の酵素電極には、カーボン微粒子やCNTを焼き固めた多孔性のナノ電極が用いられ、酵素はこれらのナノ電極に"後から"固定化されるものの、すでに出来上がったナノ構造の内部へ、サイズが同程度の酵素を導入するのは困難であったほか、このような従来のナノ電極は脆いため、支持体を必要とし、変形もできなかったが、今回、CNTフォレストをナノ電極に用いることで、これらの問題を解決した。
同CNTフォレストは、産総研ナノチューブ応用研究センターが開発したスーパーグロース法で作製される1mm×1mmのフィルムであり(厚さは0.012mmに設計)、合成用の基板からピンセットで剥がして用いることが可能だ。フィルムは、1mm長さのCNTが16nmの間隔で整然と配列したもので、これは酵素の溶液が容易に浸透できるスペースであり、フィルムの内部深くまで均一に酵素が導入可能であった。
また、酵素を十分に浸み込ませたCNTフィルムを溶液から取り出して乾燥させると、数分間で酵素のサイズ(フルクトースオキシダーゼの場合は7nm)まで収縮することが確認できた。これにより、内包する酵素のサイズにあわせて内部構造(CNT間隔)が自動的に調節される酵素ナノ電極が実現したことを意味するという。
果糖を酸化する酵素(フルクトースオキシダーゼ)を内包したCNTフィルムと、酸素を還元する酵素(ラッカーゼ)のCNTフィルムを作製し、それぞれをアノードとカソードに用いてバイオ電池を作製し、200mMの果糖水溶液に酸素を飽和させて発電実験を行ったところ、撹拌条件下で1.8mW/cm2の出力密度が得られたという。
これは過去の最高値を大きく上回る性能で、CNTフィルムが高密度に酵素を保持したほか、酵素と電極(CNT)との電気的接触が効率よく形成されたためと考えられるとしている。内包させる酵素の種類を変えれば、ブドウ糖水溶液の電池やセンサなども作製可能だと考えられるほか、この酵素電極は柔軟な自立型フィルムであり、「貼ったり」「巻いたり」しても活性が落ちないことが確認できたことから、使い終わったら剥がして交換するなど、自由な使い方が選べる酵素電極としての活用が可能となると研究チームでは説明している。
バイオ電池やバイオセンサは医療・食品・環境分野など広範囲にわたり応用が期待できるが、酵素電極は一般に、酵素の寿命のため1週間程度しか使い続けることができなかった。今回開発された技術を用いれば、貼っても巻いても活性が低下しない酵素電極シールが実現できるようになり、容易に交換することが可能となるという。すでに同技術は特許出願を進めており、研究グループでは、実用化に向けた研究開発に協力可能なパートナー企業を募集していくとしている。