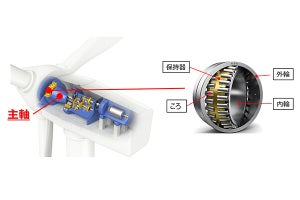大竹しのぶと宮﨑あおいという豪華なキャスティングで、ある親子の姿を描いた映画『オカンの嫁入り』のDVDがリリースされた。この作品を手掛けた呉美保監督に話を訊いた。
呉美保
1977年、三重県出身。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒業後、大林宣彦監督の事務所に入社。スクリプターとして映画制作に参加しながら監督した短編『め』が2002年「Short Short FilmFestival」入選。2003年、短編『ハルモニ』で「東京国際ファンタスティック映画祭/デジタルショート600秒」の最優秀賞受賞。2005年、長編作品『酒井家のしあわせ』で監督・脚本を担当。2010年の『オカンの嫁入り』は2作目に当たる
自分の解釈を信じて撮る覚悟が必要
――『オカンの嫁入り』は、出演者もかなり豪華です。監督2作目ということで、プレッシャーのようなものはありませんでしたか。
呉美保(以下、呉)「豪華な出演者や大きな予算でプレッシャーを感じたというよりは、今回は原作があるということ自体がプレッシャーでした。原作があるということは、作品に色々な解釈が出来るということです。自分とは違う解釈をしている人がいるかもしれない。でも、自分が監督する以上、自分が原作を誰よりも好きでいて、自分の解釈を信じて撮るという覚悟が必要です。それがプレッシャーでした」
――原作ものを映画化するときには、「原作を忠実に再現する」、「映画として独自の解釈を加える」など、本当に様々なスタイルがあります。今回、呉監督はどのような部分を意識して映画化されたのでしょうか。
呉「原作をそのまま脚本にしたのでは、あえて私が監督する意味がないので、どの部分を大切にするのかを考えました。原作では、登場人物のバックボーンがそれぞれ章ごとに描かれているのですが、映画では母と娘の物語という部分に集約して描きました」
――原作以上に、この映画では言葉が少ないですね。登場人物も、あえて言葉にはしなくても、心の機微が伝わっているという印象がありました。これは、呉監督のデビュー作『酒井家のしあわせ』でも感じたことです。
呉「その部分は意識しているのだと思います。他の映画を観ていても、説明のような独り言とか、とても違和感があるので。親子って、何かもどかしいものなんじゃないかという印象があるんです。この映画の親子もふたりで生きてきて、絆は誰よりもあるのでしょうが、それが日常に流されて上手く表現できないでいる。それがこの物語の根幹だと思ったので、そこをしっかりと描きたいと思いました。その描き方にしても、セリフで伝えるというより、むしろ会話ができなくなるというほうが伝わるし、私としては生理に合うんです。そこは、原作から変えた部分ですね」
オカンの嫁入り
|
|
|
|
自由奔放な母・陽子(大竹しのぶ)とふたりで生きてきた娘の月子(宮﨑あおい)。ある日、陽子は30歳も年下の青年 研二(桐谷健太)と再婚するということを月子に告げる。ふたりの結婚にどうしても納得いかない月子だったのだが…… |
|
――デビューから2作品とも、物語の中で「余命」が重要なポイントとなっています。
呉「この映画は原作でそれが扱われていたというだけで、余命に関してはたまたまです。私自身としては、『オカンの嫁入り』は余命に関するエピソードがなくても、感動できる作品だと思っています。監督として、"また泣かせる余命系?"と観た人に思われないような作品として、しっかりと描ければ良いと思いました」
――呉監督の作品には、沢山の心優しい人が登場します。そういった人々を描いていきたいという気持ちがあるのでしょうか。
呉「優しい人の想いが詰まったお話がデビューから2作続いたのですが、私自身はそれほど優しくもないし、優しさに関してこだわりはないです。ただ、これからも色々な家族の形を撮っていきたいというのはあります。私自身、自分の家族観がわからない部分があるので、色々な家族を映画で描くことで、家族観に対する自分なりの答えを出していきたいという気持ちがあります」
――現実としては、呉監督の映画で描かれているような暖かく優しい人々で形成された家族ばかりでなく、冷え切った家族や崩壊した家族も存在しています。そういった家族への関心はあるのでしょうか。
呉「そうですね。私は新聞の三面記事をよく読むのですが、家族間の殺人事件などを、つい追ってしまうのです。これから家族を描いていく以上は、いつか取り組む題材かもしれません」