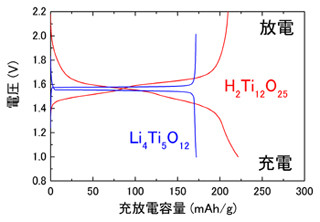産業技術総合研究所(産総研)は、異なる有機分子間の電荷移動に伴う光吸収を利用した、新しいタイプの有機光起電力素子(有機太陽電池)の動作実証に成功したことを明らかにした。 米国物理学会誌「Physical Review Letters 2010年11月26日号」に掲載されるほか、オンライン版として11月24日(米国東部時間)に公開された。
有機太陽電池は、軽量で折り曲げが可能な太陽電池シートを非高温、非真空下で製造できるため、大面積化や低コスト化に有利とされており、世界中で研究開発が行われている。しかし、その変換効率は、この数年で7~8%程度まで向上してきているものの、結晶Si系などで20%を超した製品が、また薄膜a-Si系でも15%程度を研究段階で実現していることを考えると、有機太陽電池の実用化にはさらなる高効率化が必用とされている。
有機太陽電池の高効率化を阻害する要因としては、利用できる光が可視光領域(波長<800nm)に限られており、太陽光エネルギーの約4割を占める近赤外光の利用が困難なことや光励起状態が短寿命で、電気エネルギーに変換される前にエネルギーの大半が失われることなどがある。通常、有機半導体では光吸収によって生じる励起子の広がりが分子の内部に限られていることがこれらの問題の主原因であり、現状の仕組みでは根本的な解決は難しいと考えられていた。
産総研では、これまでに異なる分子間の電荷移動に伴う光吸収(分子間電荷移動励起)を光電変換に利用する有機太陽電池の開発に取り組んできていた。分子間電荷移動吸収を利用すると、分子の組み合わせによって吸収する光の波長領域を広げることができ、従来の有機材料では不可能であった近赤外光の利用が可能になると期待されているためで、今回は異なる分子を組み合わせた有機分子化合物半導体に、電子と正孔をそれぞれ高効率に取り出せる導電性有機材料の電極をつけて有機光起電力素子を試作、動作の確認を行った。
今回用いられた有機分子化合物半導体は、電子を放出しやすいドナー性分子(DBTTF)と電子を受け取りやすいアクセプター性分子(TCNQ)が交互に積み重なった結晶構造を持つ。この材料は近赤外領域に強い光吸収を示し、従来の有機半導体と比べ2分の1から3分の1の光子エネルギー(波長にして2倍から3倍)で電子を励起することができる。
この有機化合物半導体の単結晶に、電子を高効率に引き出せる電極を陰極に、正孔を高効率に引き出せる電極を陽極にした光起電力素子(MIM型ダイオード)を作製。得られた素子は整流性を示し、波長1μm以上の近赤外領域に至る広い波長範囲で光起電力効果を示すこと、すなわち光電変換が確認された。
さらに、光励起によって生じた励起子が周囲に拡散し、電子と正孔に分離していく様子を観測するため、回折限界まで集光したレーザー光を用いたレーザー光誘起電流測定(LBIC測定:Laser Beam Induced Current)を行った結果、上記の拡散長は20μmに達し、有機太陽電池で標準的に用いられるフラーレンと比べ1,000倍以上長いことが判明した。加えて、拡散長が励起波長とともに変化する様子から、分子間電荷移動吸収によって生成した励起子は、光励起直後に電子と正孔に分離しており、これが20μmの拡散長の原因になっていることも判明した。これにより電子と正孔が再結合するまでの寿命が著しく長くなり、有機太陽電池の高効率化が可能となると研究チームでは説明している。
なお、研究チームでは、今後は、素子の薄膜化と多層化を進めることで分子間電荷移動吸収を活用した高効率の太陽電池の開発に取り組むことを目指すとしている。