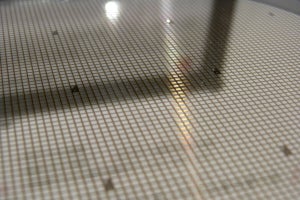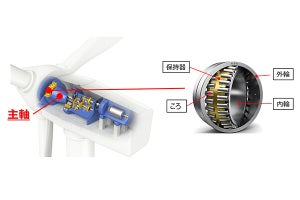海外で人気の"メイド・イン・ジャパン"は、家電製品や自動車だけではない。食品や文具など、日用品の分野においても、日本ブランドは人気を集めているのだ――。
そう言われてみると、「ああ、なるほど。実際、そうなんだろうな」とは思う。ただ、そのことを強く意識したことはないし、具体的にどんな商品が、どういうふうに受け入れられているのかなど、まったく見当がつかない。
本書『日本ブランドが世界を巡る』は、各種商品のパッケージデザインにポイントを絞り、各国の状況を伝える異色のレポート。現地向けにローカライズされたパッケージを眺めるだけでも楽しいが、どうしてそうなったのか、という裏話が面白い。メインは、各メーカーに取材した記事。同時に、ところどころ、著者の体験や実感に基づいた記述も挟み込まれ、その分、読みものとしては、立体的な仕上がりになっている。
まず冒頭、世界を巡る日本ブランドの第一弾として登場するのは、日清食品「チキンラーメン」。2008年に発売50周年を迎え、世界6か国(7地域)での商品展開を行ったという。誌面には、中国(広東省)、香港、インドネシア、インド、ブラジル、ハンガリー、米国、それぞれの地域で発売されたチキンラーメンのパッケージが勢ぞろい。本家・日本のパッケージを基本に、現地の食文化・食習慣に合わせて、デザインを修正していることが一目瞭然。
大きなポイントは、チキンラーメンの上に乗せる卵のイメージ。日本人は、生卵にさほど抵抗を感じないが、その感覚が海外でも通用すると思ったら大間違い。なので、海外のパッケージでは、生卵ではなく、炒り卵やゆで卵、あるいは、鶏肉に置き換わっている。国や地域によってシズル感が異なるのだ。
チキンラーメンを皮切りに、紹介されているのは、我々の生活に密着しているものばかり。カルビー「かっぱえびせん」、ロッテ「キシリトールネオ」、ヤマサ醤油「醤油」、エスビー食品「チューブ入りわさび」、味の素「味の素」、サントリー「伊右衛門」、キリンビール「キリンチューハイ氷結」、大正製薬「リポビタンシリーズ」、JT「マイルドセブン」、花王「アタック」、大日本除虫菊「金鳥の蚊取り線香」、久光製薬「サロンパス」などなど。あまりにも身近すぎるため、これらの商品が“海外展開”している事実に、まずは驚かされる。そして、それらが、周到なマーケティングに基づいて“お色直し”される様子が読みどころ。
たとえば、上海エリアにおけるキリンビール「キリンチューハイ氷結」の事例。商品が与える印象は、ほとんど変わらないが、色合いに注目すると、上海の若い女性たちの感覚が垣間見えてくる。著者いわく「上海女子の心を引き付けたロゼのピンク」。日本よりも、いくぶん、華やかなテイストになっている。
サントリーの上海向けのオリジナルビールも興味深い。日本向けの商品では絶対に使わないであろう“富士山”のモチーフが堂々と用いられているのだ。そもそも、パッケージ自体、缶ではなく瓶が一般的。よって、日本で暮らしている人間からすると、「えっ? これがサントリーのビール?」と思ってしまうくらい、見事に“上海化”している。
著者の渡部千春は、大御所から新進まで、多くのデザイナーを取材してきたデザインジャーナリスト。国内外を問わず、さまざまなメーカーを紹介してきた実績もある。その一方、カッコつきの“いわゆるデザイン”だけでなく、我々の身近にあるモノをとりあげ、その来歴を調べるという仕事も続けている。こうした作業の一端は、『これ、誰がデザインしたの?』や『続・これ、誰がデザインしたの?』(共に美術出版社刊)にまとめられた。現在はブログで継続中である。
『日本ブランドが世界を巡る』にも、有名デザイナーや大手デザイン事務所は、ほとんど登場しない。登場したとしても、あくまでもクレジット程度に留めるのみ。そう、主役は、デザイナーではない。といって、メーカーでもない。本書がスポットライトを当てているのは、“消費者の欲望のありよう”なのだ。そして、その欲望の多様さが、そのまま世界の複雑さを示している。
一点だけ注文をつけたい。内容の面白さに比べると、本書のブックデザインは凡庸。あまりにもスッキリと整理されすぎていて、ちょっと物足りない。もう少し、遊び心を感じさせるものだとよかったのに。