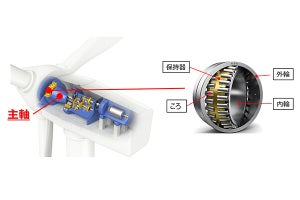アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』シリーズでヒットを飛ばした山本寛監督による初の実写映画である映画『私の優しくない先輩』。インタビュー前編では、初めて実写作品を撮ることになった経緯などを語っていただいたが、後編では、映画『私の優しくない先輩』とアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の関わりから『新世紀エヴァンゲリオン』が映像業界にもたらした影響などについて山本監督に話を伺った。
――作品を拝見した時にアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の感触が感じられたので、監督からお話が出て驚きました(詳細はこちら)。最後のシーンで決着をつけない感じや観客に考えを委ねる感じが近いですよね。
山本「『新世紀エヴァンゲリオン』以降の尖った表現は、どれも必ず『エヴァ』になってしまうんです。『告白』も『バトルロワイヤル』(2000)もそうです。エヴァの呪縛というか、すべての映画が『エヴァ』に還っていくようで恐ろしいんですけど。この作品もそれを意識する暇も余裕もなければそれっぽくしようなんて当然思いませんでした。それなのにエヴァっぽく見えてしまう。でもそれはそれとして、いろんな見方があるのは別に良いと思います。ただ、ひとつのメルクマールたる作品である『エヴァ』から、なかなか抜け出せないなという思いはずっとありましたね。日々の問題意識として『どうすればエヴァから抜け出せる? 呪縛から解放されるんだ? 』と考えていましたし。だからこそ、焼き直しにならないよう僕なりの抵抗はしたつもりです。心からリスペクトするがゆえに真似事になってはならないという気持ちがうまく出せたと思うんですが」
――ご自身なりの抵抗というと、具体的にどのような表現になるのでしょう。
山本「簡単に言えば、コメディでやったということです。難病という重いテーマもあったので、いくらでも重い方向へ作品を持っていくことはできました。でもこの作品には、それを寄せつけない程の軽く冷めたノリがあった。例えば『告白』は、『エヴァ』から『バトロワ』という系譜をなぞれるけれど、この作品は違います。すごく乾いたライトな感覚でセカイ系を捉え直し、表現し直している。最後もハッピーエンドに思わせるようなおとぎ話感があるでしょう。主人公である耶麻子の自意識過剰っぷりや感情表現を追いかけて揺さぶりをかけている作品だし、痛々しい描写もあるけど、そこまで深く考えなくても『思春期』という枠で捉えられるよう一応はまとめています」
――なるほど。
山本「僕は思春期を描く場合、見た誰もが思春期に戻ってその生々しさを体験できるものでないとダメだと思っています。今も昔も思春期はモラトリアムで悶々とする時だけれど、この作品の世界は現代的なドライさや軽やかさが感じられるんです。『エヴァ』が出てきた1990年代末は世紀末感が世の中に蔓延して、やたらに重い空気がありました。でも今は、『不景気でもなんとか生きていけているよ』といった感覚の方が強いんです。"世界が終わる"というドラマを失った分、身が軽くなった感覚が僕にもあります。そんな時代の流れも盛り込みつつ、思春期をセカイ系の枠組みの中で捉えられたのではないかと思っています。軽佻浮薄な作品だと言われても仕方ないんです。でも、それこそが今の現代に訴えかける意味があるとわかってほしいですね」
――重いテーマをコメディで表現するというスタンスは、山本監督の中にあるどのような趣向や感覚から生まれてきたと思いますか?
山本「ゼロ年代に入って重々しいドラマよりもコメディが中心となり、その中でも日常系で軽いタッチの作品が受け入れられるようになったんです。そういう仕事をずっとやってきたので自然に慣れたという感じですかね。まぁコメディ云々は別にして、この10年はみなさん苦労されたと思いますよ。『エヴァ』にいくら歯向かってもうまくいかない時期といいますか。でも、そろそろエヴァの呪縛から逃れよう、自分の中できちんと消化した上で出していかないとやばいぞとみんな思い始めていると思うんです。それができるのは、若い頃に『エヴァ』に感化されて表現することを仕事にした僕ら世代なのかもしれません。ヴィヴィッドな問題意識として持っていたのもこの世代だろうと思いますし。やっと抜け出せるチャンスが来ている気がするんです。だからこそ、エヴァを葬る作業をこの作品を足がかりとして、みんなでやっていきたいですね」
――これはアニメのひとつの作品に立ち向かう最初の作品でもあると。実写で得た新たな発見や影響は、今後やはりアニメに活かす形になるのでしょうか。
山本「今は、なぜ実写映画で撮ったんだろうと思うんです。僕がエヴァに向けて発した言葉を実写でやらないといけなかったのは因果なものだなと。多分アニメではできなかったんでしょう。ただ、いつかはアニメの言葉でも語る責任があると思っています。ポストエヴァを考える時、庵野さんは実写にもいきましたよね。その展開を思うと僕らの戦うフィールドは実写にもあると思いますし、今後はアニメ・実写分け隔てなく戦わなければならない気がします。過去の残滓を削り取るばかりではなく、その時代に響くものを作っていかないと先輩方にも申し訳が立ちませんからね。難しいことですが、新しい地平は自分たちで切り開かなければと考えています」
――新しい地平を見つけるという意味でも、今回はご自身に大きなフィードバックがなされたようですね。
山本「とてもあったと思います。まずちゃんと制作できたことは自信につながりました。僕らの世代全体に共通するのですが、みんな自信がないんですよ。近場でまとめちゃう監督さんも多いですし、そんな中にひとりくらいこんな冒険野郎がいてもいいんじゃないかと。エヴァを倒すには多角度的に攻めないと到底勝てないですよ。強敵ですから。だから、こういった実写のフィールドから矢を向ける作業も意味があるんじゃないかなと」
――表現面で一点お聞きしたいのですが、妄想シーンはチープなセットを用いて撮影されており、ミシェル・ゴンドリーの『恋愛睡眠のススメ』でも夢のシーンでダンボールが使われています。そうした表現を選ばれたのは、夢や妄想の描写にぴったりハマる要素が何かあってのことなのでしょうか。
山本「ミシェル・ゴンドリーの名前はよく出ますね。実は、僕よく知らないんですよ。もちろん、この手の手法はすでに誰かやっているだろうという自覚はありました。ただ言えるのは、あの表現はシナリオが要求したものだということです。耶麻子の視点を大事にして現実とは、空想とはなんだと考えた時にこうなるだろうと。彼女はすごくリアリストぶりますし、すごく自意識過剰です。その自意識過剰さを生々しく表現するためにも、斜に構えて世界を見るという意味でも、妄想と現実をくっきり分ける必要があったんです。耶麻子が些細なことで心が折れて傷ついて、自分の中に作っていた妄想世界がどんどん揺らいでいくというテーマを描ききる上でも必要だったという。実は、僕の思春期と耶麻子が似ているんです。僕もずいぶん色々な妄想をしましたが、どれもつくりごと前提でした。こんな事が現実に起こるわけない、だから楽しいんだぜっていう。そういう妄想が現実と混濁する瞬間がショッキングなわけで、ぐちゃぐちゃになって頭を抱える瞬間を描ききらないと、この映画はやる意味がなかったんです。もしかすると、だから最初に分析を必要しなかったのかもしれないですね、過去の記憶だけで撮っちゃえたんだろうという」
――最後に読者のみなさんに一言お願いします。
山本「いろんな捉え方をしてください。それくらい、一筋縄ではいかない不思議な映画だって部分を面白がってもらえればいいと思います。大笑いすることも大泣きすることも可能で、あるいは耶麻子みたく斜に構えて観ることも可能です(笑)。見る人それぞれがいろんな感じ方をしていただくことが、この作品にとっての幸せだと思っています」
山本寛
1974年生まれ。京都大学文学部卒業後、京都アニメーションに入社。アニメーションDoに移籍後、2007年に自身が運営するアニメ制作会社Ordetを設立。これまでに演出家として『涼宮ハルヒの憂鬱』シリーズを手掛けるほか、監督としてアニメ『らき☆すた』、『かんなぎ』などを制作している。また、『涼宮ハルヒの憂鬱』のエンディングダンスや、『らき☆すた』のオープニングダンスの仕掛け人としても知られている。映画『私の優しくない先輩』は自身初となる実写監督作品
映画『私の優しくない先輩』は、新宿バルト9、新宿武蔵野館ほかで全国公開中
(C)2010 「私の優しくない先輩」製作委員会