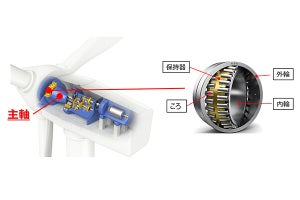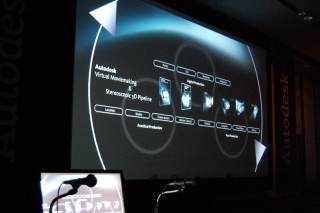「Autodesk Presents Lightstorm and ILM Blockbuster Tour 2010+After NAB 2010」では、オートデスクの製品群を活用した映像制作について、様々なセッションが行われた。インダストリアルライト&マジック シンガポール(Industrial Light & Magic Singapore:ILM Singapore)に在籍するブレナン・ドイル氏は、「ASIAの秘めた力」と題して、自身がデジタル・アーティスト・スーパーバイザーとして携わった『アイアンマン2』の制作エピソードを中心に映像制作の舞台裏を語った。
パワードアーマーの映像制作
ドイル氏はイベントで、『アイアンマン2』の制作陣が気に入っているシーンを紡いだシズルリールを上映。『アイアンマン2』で用いられたVFXショットは約500ショット。その約40%の190ショットを2006年より在籍しているILM Singaporeで担当し、内130ショットに関してはすべての作業をシンガポールで行ったという。サンフランシスコとシンガポールは直線距離にして1万数千kmも離れているが、それぞれの作業はシームレスかつ円滑に行われたという。
『アイアンマン2』の映像制作で、もっとも苦労したのは複雑に変化を続けるパイプラインだという。シェーダーやレンダリングの方法、リグやアニメーションなどについては、逐一アップデートしていかなければならなかったという。その最たるは主人公トニー・スタークが装着するパワードアーマー。映画制作が進んだ段階でレトロフィット、言うなれば「型落ち」したものに手を加え「最新型」へと映像データをチューニングしなければならなかったという。ブレナン氏は「映画制作ではそれぞれ個別の問題、独特な問題の解決に取り組まねばならない」と語る。クライアントから提供されたパワードアーマーのイメージをもとにコンセプトワークを行っていく段階で、ILMのコンセプトアーティストたちは現実的な動きを持たせることを念頭に置いた。そうして完成したコンセプトアートをクライアントへ提出する際、「アートワークにある手首のブレスレットは、こんな感じでパチンと閉まる」といった具合に、どのような形でアニメーションするか参考情報を添えていたという。ドイル氏は数々の写真資料を見せながら、「実写かCGで置き換えるかについての判断は非常に重要なものだった」と語った。シーンによってはスーツのすべてを実写からCGへと置き換えた箇所もあったそうだ。
世界観の創造
今回の作品でもうひとつ解決させなければならなかった問題として、舞台環境のイメージ構築があった。ジョン・ファヴロー監督の希望により、1964年に開催されたニューヨーク万博の雰囲気を再現・創造していくことが求められた。万博会場の環境イメージ制作では、まずコンセプトアートを作成する過程で、この万博会場はファンタスティックに見えるものなのか、または写実的にリアリスティックなものなのか、作成しては絞り込んでいくといった行程を経たという。コンセプトが決まり、実際にショットで使用するイメージを制作する段階においては、「Autodesk 3ds Max」とILM自社製のツールを用いてライティングやレンダリング等の作業を行ったそうだ。ジョン・ファヴロー監督の求めた映像は、実際の写真のようなリアリスティックなもので、レンズのフレアや歪曲収差といった光学的な要素を持たせたいという。しかし、3Dレンダリングでコントロールすることが非常に難しく、コンポジットによる付加作業が発生したそうだ。その一例として、実際にニューヨークで空撮したフォトグラフィックバックグラウンドから、フォトリアリスティックな映像に仕上げるための工夫を披露。細かな作業のなかにも監督の要求に応えるための試行錯誤が伺える。
兵器としてのリアルさ
また、ドイル氏は新たなキャラクター「War Machine」を誕生させたことについても触れた。マーベル・コミックで登場していた元のデザインにできるだけ近付けつつ、リアリスティックな味付けを行ったのだという。それに加え、ドイル氏はスーパーバイザーとして「ちゃんとエンジニアリングして、現実的な視点を盛り込もうとした」。金属の表現や武器の動き、メカニズムなど、そのリアルさにこだわったのだという。実際に銃弾が当たりどのように着弾後の処理を行うかなどは、物理シミュレーションを繰り返し何度も試行錯誤したという。
デジタル合成のために
アクションシークエンスはこのような映画には必要不可欠。しかし仕上がった映像として見るとどこか違和感がある。「そういったケースは往々にしてある」とドイル氏は語る。実際に撮影する映像はブルーバックで、俳優のアクションも少なく完成時のイメージが掴みにくい。特に合成するキャラクターの大きさが掴みにくく、それを解消するために撮影現場に多くのポールを立てて位置関係や大きさを把握し易くしたのだそうだ。そういった努力や試行錯誤の積み重ねにより、リアリスティックな迫力ある映像が生み出されたのだ。 スーパーバイザーとして大切なのはコミュニケーションだとドイル氏は語る。アーティスト間で何かトラブルがあった場合は、作業をスローダウンさせ話し合いなどによって確認し合うようにする。共通のリファレンスを用意することで「皆が何を成し遂げなければならないのか」を明確にして理解を浸透させていくのがスーパーバイザーの責任だとも語った。ジョン・ファヴロー監督が発した意思を、スーパーバイザーであるドイル氏が映像として忠実に具現化していく。彼らの強い信念のもとに誕生した映画であると認識してから本編を見ると、また新たな面白さを発見できることだろう。