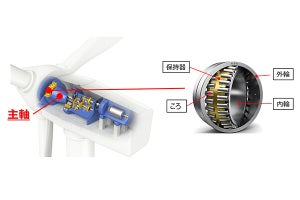映画『APPLESEED』や『ピンポン』、『ICHI』などの監督として知られる曽利文彦氏は、世界レベルのクリエイターを養成するデジタルハリウッド・東京本校にて、曽利監督自身の映像制作に対する考え方を語った。
同講義は、曽利監督と大ヒットゲームソフト『龍が如く』シリーズの総合監督・名越稔洋氏の特別イベント内で行われたもの。曽利監督は、1996年、南カルフォルニア大学に留学。デジタル・ドメイン社にて映画『タイタニック』(1997)の制作にCGアニメーターとして参加する。帰国後はVFXスーパーバイザーとして活躍し、2002年に映画『ピンポン』で映画監督デビュー。その後、3DCG技術を生かした劇場版3Dライブアニメ『APPLESEED』(2004)や『ベクシル-2077 日本鎖国-』(2007)などを手掛け、多くの国際映画祭で高い評価を受ける。2009年12月にブルーレイ&DVDが発売された『TO 楕円軌道/共生惑星』は、自身の3Dライブアニメ最新作となる。
和製フルCG映画への挑戦
デジタル映像制作の第一人者と評される曽利監督が、アメリカ留学時代から取り組んできたのが、アニメをCGで表現する"和製フルCG映画"の制作。曽利監督は日本人ならではの独創的な3DCG表現を生み出すために"3Dライブアニメーション"という技法を確立した。特徴は「トゥーンシェイダーを利用した輪郭線や陰影による手描きアニメーション風のタッチと、人間の演技をモーションキャプチャでそのまま取り込んだ動作にあります」と曽利監督。アメリカから帰国後、この技術をテレビアニメに生かせないかとデモ作品を制作した。そのうちのひとつ『アイアン・メイデン』が、曽利監督の最新作である星野之宣のSFコミック「2001夜物語」をベースに描かれた3Dライブアニメ『TO 楕円軌道/共生惑星』の一番の基礎になっているのだという。
日本人ならではの3DCG表現を
曽利監督曰く、映像作品の技術的な面では昔に比べ、やはり今の作品の方が進化しているが、作品と対峙するときのテンションの高さや、良い作品を制作しようとする熱意といった精神面は当時とまったく変わっていないという。「僕が『3Dライブアニメ』をやるのは、日本人として戦いやすいフィールド、つまり日本のアニメ表現の良さを生かして戦う方がいいと考えたからです。ピクサーが得意とする子ども向けフルCGのような表現は、資金的にも環境的にも日本で制作することは難しいんです。それならば、自分たちにしかできない手法で観客に楽しんでもらおうと思い、『3Dライブアニメ』制作に取り組んでいるのです」
その表現は世界各地の映画祭で高い評価を獲得。曽利監督は2作目となる『ベクシル』で、さらにその制作スタイルを高めていった。例えば、表情や人の骨組みなどを一新し、前作は予算の問題で夜のみだったバトルシーンに日中を追加。エフェクト面でも更なる進化を見せている。「プリプロから考えると、この作品の制作に2年かかっています。これだけの密度の作品を作るのはかなり大変でしたが、キャプチャ技術や、人物・表情の表現、トゥーン技術など、得たノウハウは大きかったですね。技術に関しても改めて基礎から組み上げたので、インフラとしても素晴らしい作品ができたと思います」。当然ながら、『TO 楕円軌道/共生惑星』にもこうした技術が存分に使われている。この作品の制作では、ブルーレイでの鑑賞にも耐えるクオリティでありながら、参加したスタッフ数や制作期間は『ベクシル』の半分以下だったという。スタッフの経験値の向上はもちろん、技術の追求が作業の効率化をも進めたことは想像に難くないだろう。
また、制作過程でデジタルハリウッド大学からのインターン生が参加したことにも触れ、学生に向けて次のように助言した。「今ではプロも学生も使用するソフトやツールは同じですから、心意気さえあれば、学生でもプロ同様の作品を制作できます。そんな状況ですから、プロの現場に携わって少しでもシーンを担当できれば、授業を受けるだけに比べて、自分の精神をより高めることができるはず。OXYBOTでもそんな機会があるかもしれませんので、その際はぜひ参加してみてください」
講義の最後、「日本人としてハリウッドに通用する作品を作るには? 」という受講者からの質問には、「とにかく真似をしないこと、独自の表現が出来て始めて同じフィールドに立てる」と独自性の重要さを語った。また、最近増え始めた「立体視の映像を作る予定は? 」との質問には、「まだ具体的ではない。日本では立体視の演出論が確立されていないだけに、まずは誰かがその分野を引っ張る必要はあると思う」と回答した。今年の3月からは実写作品の撮影も始まるという曽利監督。マーケットの世界的な広がりに対応すべく、世界マーケットに向けた3Dライブアニメ作品を心がけたい、として講義を終了した。「和製3Dアニメの挑戦」は、今後も更なる高みを目指して進化し続けることだろう。