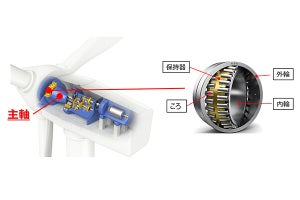情報通信研究機構(NICT)は26日、「NICT超臨場感コミュニケーションシンポジウム」を開催した。同機構が総務省と連携して進めている超臨場感コミュニケーションに関する研究成果が、展示や講演などで発表された。クリエイターにも気になる映像最新技術をレポートする。
インテグラル立体テレビ
目が疲れず、裸眼で自然な立体視が可能な「多並列・像再生型立体テレビシステム」の実現を目指す研究。画面上には直径2.64mmの小さなレンズが並んでおり、これによって被写体と同じ光線空間を再現し、奥行き感を再現している。
映像に奥行き感があるのはわかるだが、現状ではまだ、リアリティはイマイチ感じられない。現在、8K(7680×4320)の画像に140×180のレンズが使われているそうだが、直径が約半分のレンズを使ったより解像度の高いものを開発中とのこと。家庭用の立体テレビ実現に向けた技術として有力視されている。
キューブ型立体ディスプレイ gCubik
ガラスに入れた標本のようにどの角度からも裸眼で見ることができる、小型の立体ディスプレイ。原理としては上記のインテグラル立体テレビと同じで、VGAサイズの液晶画面の上にレンズが並べられている。センサー付きディスプレイと連動させた「gCubik+i」では、画面上のものを「取り出す」ことができる。超臨場感システムの要素技術となるもので、手が届く程度の距離におけるコミュニケーションツールとして提案されている。
単色電子ホログラフィー
何もない所に、立体的に物を映し出すホログラフィー。専用の装置で被写体を撮影してホログラムデータに変換し、再生装置で光によって被写体のある状態を再現する。立体的に見える映像ではなく、光によって立体像を再生しているという状態は、なかなか理解しづらい。展示では3840×2160のホログラムデータから、240×130程度の立体が再生されていた。カラーのホログラフィーや、より大きな表示システムも開発が進められている。
ナチュラルビジョン
通常の映像システムにおけるRGBの限界を超えて、被写体の色や質感を忠実に再現するシステム。6バンドHDTVカメラで撮影された映像をリアルタイムで色変換し、5原色ディスプレイで表示している。通常のカメラ/ディスプレイを使った表示とは、見える色や質感が大きく異なる。表示側では視聴環境の照明の影響を再現することが可能で、被写体が実際に観察者の目の前に置かれているように色を再現できる。
立体映像、感触、音による多感覚インタラクション
高松塚古墳から出土した「海獣葡萄鏡」の立体映像と感触・音をリアルに再現。立体映像を見るだけでなく、位置センサとモーターを内蔵したペンによって、形状の凹凸感やサビの質感を手で感じることができる。また、表面に触れた際の接触音も生成され、触れた強さによって音量も変化する。感触や音があったせいか、他の展示物よりもリアルな印象が強い。貴重な文化財等に触れられるリアルな体験学習や、医療シミュレーション等への応用が研究されている。
NICTユニバーサルメディア研究センター長の榎並和雅氏は、「今後、"向こう"の情報をこちらに持ってくるだけでなく、こちらの手足となる部分を"向こう"に持っていくことができれば、本当の『超臨場感』が実現できるだろう」と述べている。