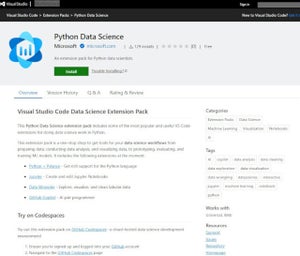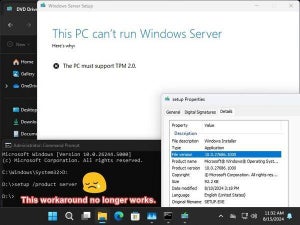レッドハットは9月25日、クラウド・コンピューティング実現に向けた同社の戦略説明を行なった。説明したのは、米Red HatのVice President, Platform Business UnitのScott Crenshaw(スコット・クレンショウ)氏。
同氏は、「Red Hatの次世代コンピューティングへの取り組みは4年ほど前から開始されたものだ」と説明。発端となったのはユーザーからの要望であり、「次世代コンピューティングに関するRed Hatのビジョンを示してほしい」との声があったからだそうだ。
次世代コンピューティングへの取り組み
同社が掲げる目標は「ユーザー企業のITインフラのコスト削減を支援する」「ローコストのx86プラットフォームを活用する」「ITインフラのオペレーションのスケーラビリティを向上させる」という3点に集約される。
そして、これらの目標を実現するための技術的な実装手法として考えられた次世代のコンピューティング・ビジョンとは、「コンピューティング容量を共有可能な"プール"に集め、さまざまなアプリケーションをそのプール上で実行する」というものだ。これは、技術面ではGridであり、ユーティリティ・コンピューティングであり、クラウド・コンピューティングだといえる。
Red Hatは長く「Linuxの会社」と見られており、仮想化やクラウドといった分野への取り組みは、Linuxが成熟し、そうした機能を実装するに至ったからという、いわば受動的な反応と見ることも可能だろう。しかし、まず「ユーザー企業のITインフラのコスト削減を支援する」という目標があったと考えれば、そもそもオープンソースOSであるLinuxに取り組んだことも、それがコスト削減に極めて有効だからだ、と理解することができる。
オープンソースという思想性の濃い動きに深く関わっていることから、同社の取り組みは極めて独自性の強いものとみる向きもあるようだが、最近同社が強調している「UNIXのリプレース」に関して言えば、実はユーザーにとっての直接的なメリットは"オープンソースであること"よりも、"同じことがより安価に実現できる"点にあるのは間違いないだろう。
Linuxの強みは、標準化されたIAプラットフォームで動作することで、結果として業界各社の支持を得て、大規模な市場を獲得している点にある。自社製の独自ハードウェアとの組み合わせを前提とする商用UNIXとの違いは、ハードウェアに注目して市場規模を見れば明らかになる。
技術的な視点で見れば、Linuxを殊更UNIXと区別する理由はなく、同じようなインタフェースを備え、同じように使えるほぼ同等のOSということになる。もちろん、ここまで言えるようになったのはLinuxが先行する商用UNIXに追いつき、肩を並べるレベルにまで成熟したからこそだが、こうなった以上、現時点では既に"Linux対UNIX"という対立軸で発想すること自体、意味が失われているといえるだろう。
現在の対立は、ハードウェアを持たないソフトウェア専業ベンダーが提供する標準ハードウェアを対象としたOSか、独自ハードウェアとセットで提供されるOSか、という違いだ。これは、Microsoftが、PCのOS市場で圧倒的な地位を築いたのとほぼ同等の戦略とも言える。Red Hatは「オープンソース企業としてよく分からない動きを示す」わけではなく、むしろコストパフォーマンスに優れたITインフラを提供するための、いわば王道とも言える戦略を実行しているのだと考えてよさそうだ。