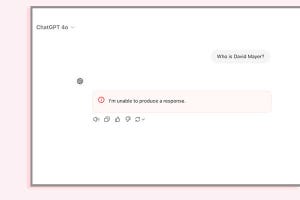著作権の保護期間延長や非親告罪化などについて議論をする「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム・第4回公開トークイベント」が8月23日、東京都港区の慶應大学三田キャンパスで開かれた。同フォーラムや慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ(DMC)機構などの共催。米国が年次改革要望書で求めている著作権に関する各種の要請に対し、「日本モデル」を提示できるかどうかについて、参加者が白熱した議論を繰り広げた。
弁護士の福井健策氏をコーディネーターに、東京大学法学部教授の中山信弘氏、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)専務理事の久保田裕氏、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事のドミニク・チェン氏がパネリストとして参加した。
米国の要望書が著作権議論の発端に
議論の冒頭で福井氏は、著作権の保護期間延長や非親告罪化の議論について、2002年に米国が日本政府に提出した年次改革要望書(日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への米国政府要望書)が発端になったと指摘した。
日本の著作権法では現在、著作権の保護期間は著作者の死後50年(映画の著作物は公表後70年)となっているが、米国は70年となっている。また、親告罪とは被害者の告訴がないと起訴できない罪のことを指し、日本の著作権法では一部の違反を除き現在親告罪を採用しているが、非親告罪化されれば、被害者の告訴がなくても起訴できる。
米国政府は、2006年12月にも、これらを求める要望書を提出している。福井氏によれば、著作権の保護期間延長や非親告罪化を求める米国政府の要望に対し、文部科学省は、2007年3月から同省の文化審議会著作権分科会に設置した「過去の著作物の保護と利用に関する小委員会」で保護期間見直しの検討を進めている。
また、非親告罪化に関しては、内閣官房の知的財産戦略本部が策定した「知的財産推進計画2007」の中で、「著作権法における親告罪を見直す」とし、「2007年度中に親告罪の範囲拡大を含め見直しを行い、必要に応じ法改正等制度を整備する」と今年度中に見直す方針を政府が示している。
理にかなっているのか見極めが必要
福井氏はこうした状況に対し、以下の4つの論点を提示した。
- 米国の外交要求をどう考えるか
- 「欧米水準に追いつきたい」という意識について
- 知的創造サイクルの「日本モデル」は可能か
- 日本は世界とどう向き合うべきか
第1の「米国の外交要求をどう考えるか」について、まず「非親告罪化」をテーマに意見が繰り広げられた。ACCSの久保田氏は「非親告罪化で誰がメリットを受けるか分からない。文化発展のためにあえて権利行使をしない権利者が存在するなど、親告罪だからこそバランスがとれている」と発言。クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのチェン氏も「先日コミックマーケット(コミケ)に初めて行ってみたが、同人文化などにおける二次利用は、決して権利者を愚弄(ぐろう)するためのものではないと改めて実感した。クリエイティブ・コモンズも同様に著作権を否定するものではなく、合法と違法の枠を超えた中間領域こそ大切だと思っている。その意味で、表現を抑圧する可能性のある非親告罪化には同意しかねる」と述べた。
これに対し、東大教授でクリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長でもある中山氏は「米国は自国の利益になるから要求しており、国というものはそういうもの。何が理にかなっているかを見極めることが大切だ。客観的状況として、海賊版がテロ組織の資金源になることの防止や知的財産権における重罰化の流れが、非親告罪化の背景となっていることも理解する必要がある」と話した。
「保護期間の延長」のテーマについては、チェン氏が「米国の要望はあからさまで、慎重に対応する必要がある」と発言。久保田氏も「ACCSの中にも、創作活動において二次利用を活用している会員と、保護期間延長を支持する会員と、意見が真っ二つに割れている。地域活性化など草の根での著作物の利用を促すという意味でも、保護期間延長が正しいかは疑問」と述べた。