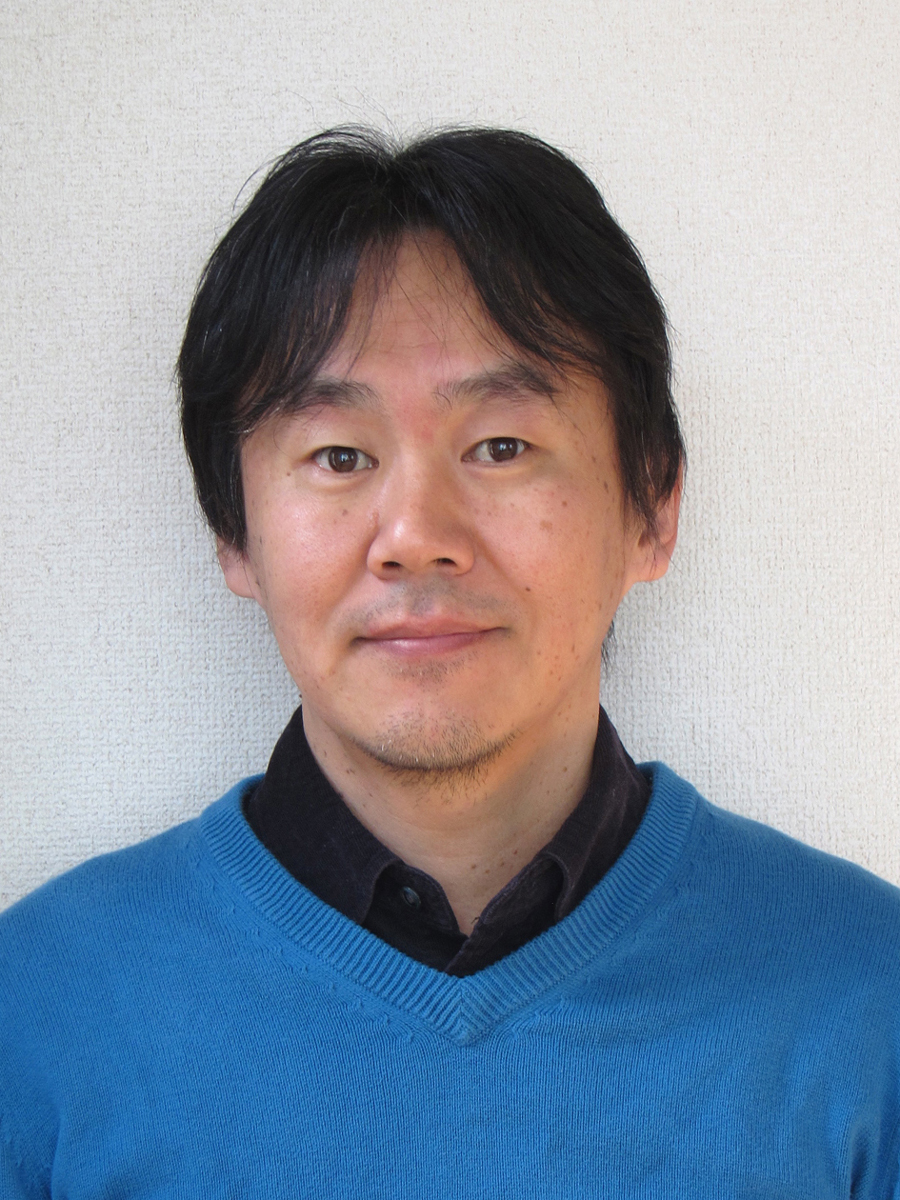世界中の自動車ブランドがEV(電気自動車)の開発に注力している。しかし、その多くはエンジン車をリファインし、サブブランドを与えることで済ませているのが現状だ。これが真のEVデザインなのだろうか。この分野のリーディングカンパニーである日産自動車で、これまでに多くのEVを手掛けてきたエグゼクティブ・デザイン・ダイレクターに話を聞いた。
EVならではのデザインとは?
田井氏の入社は1982年。当然ながら、しばらくはエンジン車に関わっていたのだが、最近はEVに携わることが多いそうで、市販車「リーフ」のほか、過去3回のモーターショーのコンセプトカーも手掛けたという。こうした経歴を持つ田井氏にまず聞きたかったのは、「EVならではのデザインはあるのか」という点だ。
-
インタビューは銀座四丁目の交差点にある「NISSAN CROSSING」で実施。展示してあった「ニッサン IMx KURO」(画像)は、日産が2017年10月の「東京モーターショー」で世界初公開したコンセプトカー「ニッサン IMx」に、“黒”をテーマとするデザインの変更を施した車両だ(画像提供:日産自動車)
EVはエンジンとガソリンタンクを持たない代わりに、モーターとバッテリーを搭載する。タンクとバッテリーの形状は自由度が高いが、モーターはエンジンに比べて大幅に小さく、トランスミッションも不要だ。ここまで機能的な部分が変われば、それに合わせて形状も変わるべきだろう。「フォルム・フォローズ・ファンクション」(形は機能に従う)という言葉もある。
しかし、市販されているEVの多くは、ハイブリッドを含めたガソリン車やディーゼル車に近いカタチをしており、中には顔つきを変えてサブブランドを名乗っているだけの代物もある。この状況を田井氏はどう考えているのか。
「確かにEVは、エンジン車とはメカニズムの内容も配置も違います。バッテリーは床下に積むことになりますが、逆にエンジンからの排気管を通す必要がないので、フロアを平らに作りやすいですし、モーターはエンジンよりはるかに小さいので、全長に対して広いインテリアが作れます。2015年の東京モーターショーに出展した『TEATRO for DAYZ』など、箱型ボディとの相性も良いと考えています」(以下、発言は田井氏)
さらに田井氏は、EVがシェアを伸ばしつつあるSUVにふさわしいメカニズムであることも指摘した。前述のように、EVではバッテリーを床下に積むので、車高に余裕がある方が広いインテリアを生み出しやすい。それでいて、重心は低くなるので走行安定性はスポイルされない。現状でリーフは前輪駆動だが、ハイパワーな車種では前後にモーターを積む4WDになるとのことだった。
大変革の自動車業界、過渡期を迎えるクルマのデザイン
ただし、田井氏は同時に、現在がEVデザインにとって過渡期であることも付け加えた。リーフでいえば、旧型はフロントグリルをなくすなど思い切ったデザインを取り入れたが、その試みには賛否両論があったという。この経験から、従来の自動車から離れ過ぎるとユーザーは付いてこないことが分かったそうで、現行型はグリルがあるような意匠を施すなど、トラディショナルなカッコ良さを目指す方向にしたという。
EVの良さは乗れば分かると思うので、まずは乗ってもらうことを心掛けた。それが、新型リーフのデザインアプローチだ。しかし田井氏には、将来的には全く違うデザインにしたいとの考えもあるそう。頭の中はその方向に振り切れているけれど、伝統的なクルマのスタイリングを好む人が多いことも理解しているため、状況を見ながら少しずつ歩みを進めていきたいとのことだった。
自動運転についての言及もあった。EVと自動運転が制御面で相性が良いことは、筆者もさまざまな開発担当者から聞いているし、高速道路で前車や車線を検知してアクセル、ブレーキ、ステアリングを自動制御するリーフの「プロパイロット」は、きわめて滑らかな制御であることを確認してもいる。
さらに、人間が運転しない完全自動運転の普及が衝突安全性対策を見直すきっかけとなれば、クルマのカタチも大幅に変わるだろうと田井氏は予想する。運転席が後ろ向きになったり、フラットになったりという仕掛けは、自動車会社としては勇気がいるものの、数年先には現実になっているかもしれないという。
“動物的ではない”ダイナミズムを目指す
エンジン車のスタイリングの中には、動物からインスピレーションを受けたものが多い。そうなった背景には、疾走する様子が動物を連想させるというほかに、エンジンの構造的な理由もあるのではないかと筆者は思っている。
エンジンは空気をシリンダー内に吸い込んだところに燃料を噴射して点火させ、ピストンを押し下げて回転運動を生み出し、燃焼によって発生したガスを排出する(直噴方式の場合)。これは人間を含めた動物が呼吸し、活動する様子と似ている。このエンジンがないわけなので、EVのデザインに、動物的なラインは似合わないと筆者は思っていた。これについては田井氏も似たような考えだった。
「EVでは、動物的ではないダイナミズムの表現を目指そうと思っています。昨年の東京モーターショーで世界初公開したコンセプトカー『IMx』はその方向でデザインしました。モーターは、回り始めで最大トルクを発揮しますが、動物の走りではこうはなりません。EVならではのモダンでクールな路線にしたいと思いました。長年クルマと親しんできた方よりも、若い人たちの方が入っていきやすいのではないかと考えています」
EVは“和風”自動車!?
取材場所のショールーム「NISSAN CROSSING」には、今年のジュネーブ・モーターショーで日産が公開したコンセプトカー「IMx KURO」が展示してあった。ボディカラーをIMxのパールホワイトから深みのあるダークスモーキーグレーに変更したこともあって、エッジを強調したフロントフェンダーやサイドのキャラクターラインが際立っていた。次世代のクルマであることがひと目で分かる。隣に置かれたリーフとの共通部分が多いことも理解できた。
IMx KUROは自動運転技術も搭載しているが、合計12個のカメラはルーフ後端など目立たない場所に仕込まれてある。また、グリルやルーフにはイルミネーションが入るが、ここは自動運転時と手動運転時で色が変わる。クールでありながら、周囲とのコミュニケーションを大切にしようという姿勢に筆者は好感を抱いた。
インテリアには一転して和のイメージが漂う。インパネやドアトリムは黒ベースの中にウッドパネルを張り巡らせている。注目は、そのパネルに細かいスリットを何重にも刻み、中にLEDを並べているところ。ここには、外の景色を映し出すことができる。こういった意匠には、安全性を高めるという目的もあるが、障子のように外が透かして見える和の雰囲気も織り込んだとのことだ。
お気付きの読者もいるだろうが、黒いパネルは漆器、グレーのフロアは枯山水の砂紋、シートのヘッドレストは組木がモチーフとなっている。
日産は、1999年にルノーとアライアンスを結成した。それがIMxやIMx KUROのインテリアに展開された「ジャポネスク」につながっているのだろうか。田井氏に尋ねると、筆者の予想は一部あたっていたが、それ以外にも和風を取り入れている理由があった。
「アライアンスを組んでからは、確かに日本ならではの動き方や作法などを意識するようになりました。外国人スタッフも日本をリスペクトしてくれる人が多いですし。ただ、それとは別に、EVは“和風なクルマ”だとも思っています。動物的なデザインは、狩猟民族といいますか、西洋のものだという風に感じますが、日本人は物事をフラットに捉えることができます。この思考は未来的かもしれません」
インタビューの中で田井氏は、平らな床だけでなく、非対称のシートや遠くにあるインパネなども「日本の美」を連想させる要素だと話していた。それらはモダンかつクールであり、EVにもつながる雰囲気を漂わせていた。
これからのEVのカタチは、日本が主導していくのかもしれない。日本の美とEVの親和性について語る田井氏の言葉を聞いて、未来のカーデザインが楽しみになった。