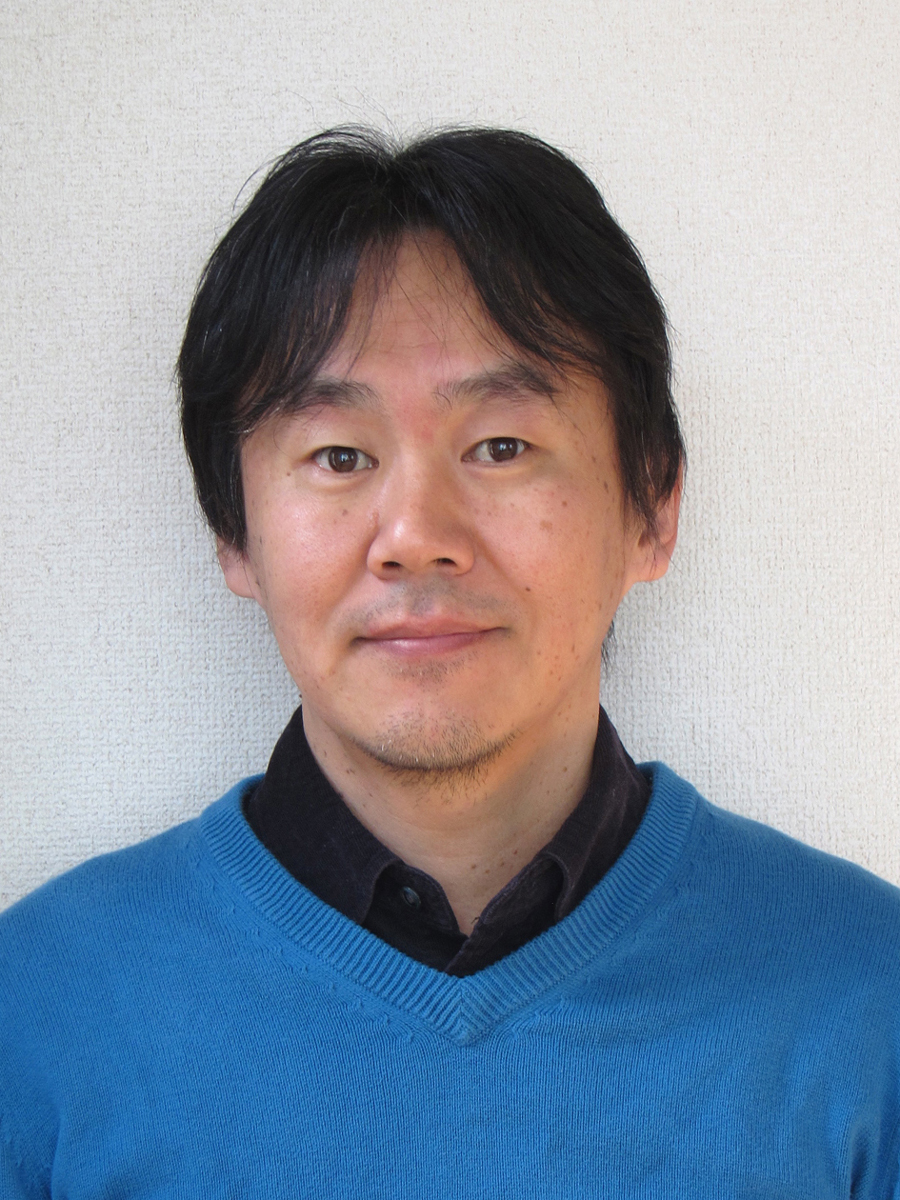近年、自動車メーカーがヒストリックカーの取り扱いに積極的になりつつある。新車の開発、生産、販売を本業とするメーカーがなぜ、旧いクルマに力を入れ始めているのか。日産自動車が神奈川県座間市で公開している「日産ヘリテージコレクション」を取材したのを機に考えてみた。
ひっそりと引退していくクルマ達
この原稿を書いているのは、安室奈美恵さんが引退前の最後のステージを、生まれ故郷の沖縄県で終えた直後。全国各地から多くのファンが沖縄に向かい、別れを惜しむ様子がニュースで報じられていた。
モビリティの分野でも別れを惜しむシーンは見られる。代表的なのは鉄道で、長年走り続けてきた車両の引退や路線の廃止ともなれば、駅のホームは多くの人であふれ、沿線にはカメラを構えたファンが並ぶ。こうした状況を理解して、鉄道会社も「さよなら運転」などのセレモニーを催すのが一般的になった。
でも、自動車業界ではほとんど、このような催しを見ることがない。「ファイナルエディション」など、生産終了を記念(?)した限定車を出すぐらいで、ほとんどのクルマはひっそりと生涯を終えていく。
過去に目を向けることに意味はあるのか
自動車の中でもとりわけ乗用車は、移動のための道具というだけでなく、デザインや走りを楽しむ商品という側面も持つ。この点では、ファッションに近い部分があると思っている。
そのためメーカーは、ユーザーに買ってもらうために、デザインやテクノロジーで新しさをアピールする。そのためにモデルチェンジを行う。当然ながらメーカーは、最新が最良という考えで開発しているから、旧型にスポットを当ててこなかったのも無理はない。
しかし、モデルチェンジごとの進化ではなく、ひとつのブランドというスケールで見ると、過去に目を向けることにも重要な意味があると思えてくる。
レースでの勝利がスカイラインを育てた
例えば日産自動車には、50年以上にわたり作り続けている「スカイライン」という車種があるが、ロングセラーの理由として、1960年代終わりから70年代はじめにかけての3代目「C10型 2000GT-R」、1990年代前半の8代目「R32型 GT-R」などがレースで発揮した圧倒的な強さがあったのは間違いない。
自分たちの愛車と基本的には同じクルマがレースで連戦連勝する。その戦績は、オーナーにとって誇りになるはずだ。GT-Rはその後、独立した車種になったけれど、ルーツがスカイラインにあることは疑いのない事実。スカイラインというブランドの根強い人気は、過去の名車たちによって支えられている部分もある。
これはスカイラインに限ったエピソードではなく、フェラーリやポルシェにも通じる話である。レースやラリーに出ていない実用車でも、多くのユーザーが日常的な使用によって導き出した高い評価が積み重なり、同様の伝説になっていった。確かに新型モデルは、旧型より性能面で優れているが、長い目で見れば、1台1台の蓄積が今日のブランドを作る上で大きな役割を果たしているのだ。以前も書いたように、文化として認識すべき存在なのである。
ゆえに、欧米の自動車ブランドは昔から、過去の名車を展示するミュージアムを用意してきた。そして日本でも、1980年代後半あたりから「トヨタ博物館」や「ホンダコレクションホール」などの開館が続いた。こういった施設は館内を自由に見学できるだけでなく、以前の記事で紹介した「AUTOMOBILE COUNCIL」などのイベント時には、数台を出張展示し、走行を披露することもある。
「ダットサン」と「フェアレディ」に込められた意味
ただし日産は少し前まで、トヨタやホンダなどとは異なる姿勢を取っていた。
同社でも以前から、1933年の創業当初から現在に至る歴代の市販車やレーシングカー・ラリーカーなど約400台を「日産ヘリテージコレクション」として収蔵し、うち約300台を庫内に並べていたのだが、それをトヨタ自動車やホンダのように博物館として運営してはいなかった。収蔵車の一部をイベントなどで見られることはあったが、当初は一般公開していなかったのだ。
その場所は、1990年代まで座間工場として車両の生産を行い、現在は新型車の量産試作と生産技術の企画製作を担当するかたわら、電気自動車のモーターやインバータの開発、リチウムイオンバッテリーの開発・生産を行う座間事業所である。
その施設を日産は、2013年から一般公開している。事前の申し込みが必要になるが、入場無料というのはうれしい。
今回は、この日産ヘリテージコレクションを取材したのだが、改めて思ったのは、日産が多様なルーツを持ち、注目すべきポイントの多いメーカーであるということだ。ネーミングひとつを取っても、そう感じる。
日産は創業時から第2次世界大戦後の1950年代まで、「ダットサン」という乗用車を主力としていた。この名前、日産のルーツのひとつである快進社自働車工場が1914年に生み出した自動車に起源がある。そのクルマとは、3人の出資者の頭文字を取った「ダット」(DAT)だ。このダットには、「脱兎のごとく」速いという意味も含ませていた。
その後、快進社自働車工場が実用自動車製造や戸畑鋳物などと合併し、日産の母体を形成していく中で、ダットの息子ということで「ダットソン」(DATSON)というクルマを1931年に生み出す。しかし、「ソン」は「損」につながるということから、翌年には「ダットサン」とし、この名前を長きにわたり使っていくことになる。「ブルーバード」や「サニー」も、当初はダットサンブランドだった。
ダットサンには1950年代からスポーツカーもあったのだが、時代を考えればかなり先進的で、台数は出なかった。そこで、イメージアップを図るべく日産は、当時の社長が観劇したミュージカル「マイ・フェア・レディ」にちなんで、「フェアレディ」という車名を与えたのだという。
これが「フェアレディZ」に発展することは説明するまでもないだろう。それまでオープンカーだったフェアレディがZでクーペになったのは、メインマーケットの北米で、安全かつ快適なスポーツカーが望まれていたからだった。デザインの変遷には当時の世相も反映されていることが分かる。
スカイラインを生んだもうひとつの会社
一方、さきほど例に出したスカイラインは、プリンス自動車工業という、もうひとつの自動車会社から生まれている。プリンスは第2次大戦中に軍用機を製作していた立川飛行機が母体で、戦後は自動車作りに転身。日産の電気自動車「リーフ」のルーツとも言える「たま電気自動車」を世の中に送り出したメーカーでもある。その後、やはり航空機会社がルーツでエンジン設計に長けた富士精密工業と合併し、1957年に作り出したのが初代「スカイライン」だった。
プリンス・スカイラインは2代目で高性能エンジンを積んだ「2000GT」を追加し、1963年のレースでポルシェと互角の戦いを演じるなど、日本を代表する高性能車として名を馳せた。これがGT-Rへとつながっていくのである。
プリンスは技術主導のブランドだったがゆえに経営面は厳しく、1966年に日産と合併した。しかし、旧プリンスの開発拠点はその後しばらく存続し、日産初の前輪駆動車「チェリー」やその流れを汲む「マーチ」、国産ミニバンのパイオニアといえる「プレーリー」などを生んだ。これらのデザインがブルーバードやサニーとはひと味違うことも、日産ヘリテージコレクションに行けば理解できる。
海外から技術やデザインを積極的に取り入れたのも日産の特徴だ。第2次大戦直後、敗戦によって欧米と差が開いた技術水準を埋めるべく英国BMC社の「オースチンA40・A50」をノックダウン生産すると、1960年代はブルーバードや「セドリック」のデザインをイタリアの名門デザインスタジオ「ピニンファリーナ」に依頼した。しかし、1970年代になると一転して、スカイラインや「バイオレット」などに当時の米国車を思わせるフォルムを採用していった。
こうした経緯があり、現在はルノーや三菱自動車工業とアライアンスを組んでいる日産の歴史は、日本の自動車ブランドでは複雑な方かもしれない。しかし、日産ヘリテージコレクションに足を運べば、こうしたヒストリーを追いつつ、ブランドへの理解を深めることができるだろう。その意味でも、ヒストリックカーを見せることは、自動車メーカーにとって価値ある取り組みだと思っている。