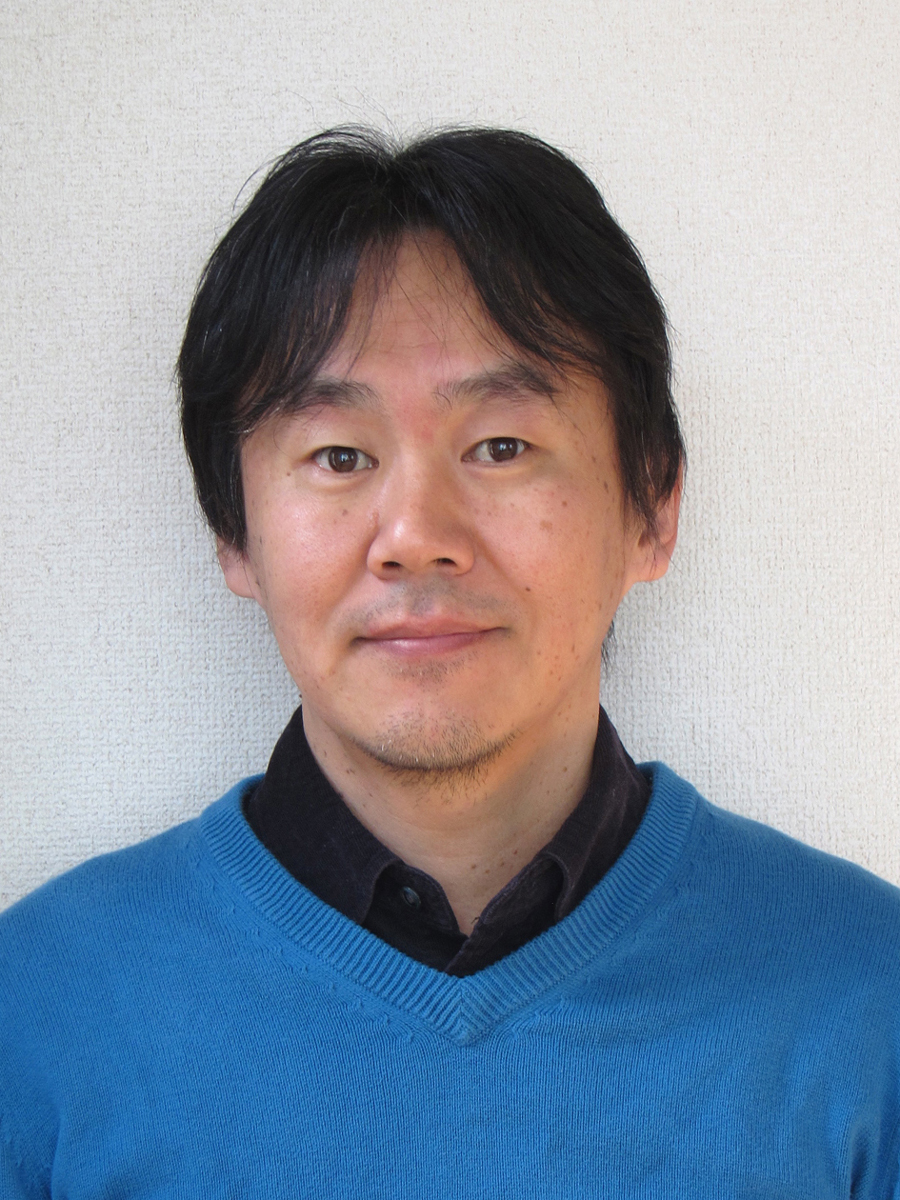多くの人の目がSUVに吸い寄せられている昨今だが、その中でハッチバックに新たな流れが生まれつつある。実用性や経済性ばかりを重視するのではなく、カッコいいデザインや楽しい走りを追求する車種が増えてきているのだ。マツダの新車も控える2019年は、ハッチバックが自動車業界のトレンドになるかもしれない。
ハッチバックのルーツは?
ハッチバックの歴史を語る上で外せない車種が2つある。1961年に発表されたルノー「4」(キャトル)と、その11年後に登場したルノー「5」(サンク)だ。
ルノー初の前輪駆動車でもあった「4」は、量産車初のハッチバックでもあった。コンセプトは「ブルージーンズのようなクルマ」だったそうで、背が高くて後端まで伸びたルーフは、マルチパーパス(多目的)であることを強調していた。
ところが、同じプラットフォームを使って1972年にルノーが送り出した「5」は対照的だった。当初のボディは3ドアだけであり、前後のバンパーは量産車でいち早く樹脂製とするなど、ファッショナブルな面を強調していたのだ。
もうひとつの無視できない流れはイタリアにあった。1964年、フィアットがグループ内のアウトビアンキというブランドから前輪駆動ハッチバック「プリムラ」を登場させると、5年後にはひとまわり小さな「A112」を送り出したのだ。アウトビアンキは同クラスのフィアットより上級という位置づけで、ルノー「5」のように、付加価値を与えられたクルマだった。
「5」が生まれた1972年前後には、アウトビアンキ「A112」とプラットフォームやエンジンなどを共用したフィアット「127」、プジョー「104」、ホンダ「シビック」などが相次いで発売となり、1974年にはフォルクスワーゲン(VW)が「ゴルフ」を送り出すなど、ハッチバックは次第に勢力を増していく。
その過程においては、前輪駆動ではないハッチバックも生まれた。代表格といえるのがトヨタ自動車の2代目「スターレット」だ。当時のトヨタは前輪駆動車を市販化していなかったこともあって、FR(フロントエンジン・リアドライブ)のままハッチバックを仕立てていたのだ。
FRのスターレットは、室内の広さなどで前輪駆動のライバルには劣っていたものの、前輪駆動のハッチバックが主流になる中で、コンパクトな後輪駆動の実用車という独自のパーソナリティが逆に注目されて、走り好きの人々に愛されることになった。
忘れがたきホットハッチの名車たち
走り好きの人々に愛された車種といえば、「ホットハッチ」と呼ばれたクルマたちを忘れることはできない。ハッチバックをベースとして高性能エンジンを積み、サスペンションを低く固め、ボディやインテリアを精悍に装ったものだ。
この分野のパイオニアといえるのが、1973年発表のアウトビアンキ「A112アバルト」だろう。アバルトは1960年代、フィアットのリアエンジン小型車「600」をベースとした高性能車を製作してレースで大活躍したが、600の生産中止に伴い、同じエンジンをA112に載せた車種を企画したのだ。現在のアバルト「595/695」のルーツになった1台といえるかもしれない。
A112アバルトが登場した翌年には「シビック1200RS」、1976年には「5アルピーヌ」と「ゴルフGTI」が登場する。
シビックRSはシビックのスポーツタイプだが、ホンダは大気汚染やオイルショックなどが問題となっていた当時の国内事情を鑑みて開発を行っていた。エンジンは従来から出力を7psアップさせたに過ぎない。もっと早そうな名前も付けられただろうが、「ロード・セーリング」の略である「RS」を選んだのも、当時の情勢を考慮してのことだろう。
昨年はルノーが「アルピーヌ」ブランドを復活させ、新型車「A110」を発表してファンを喜ばせたが、A110にも脈々と流れるスポーツカーのノウハウを注ぎ込んで生み出したのが、ホットハッチの「5アルピーヌ」だった。1.4Lから93psを発生したエンジンは、のちにターボ化されて110psまで力を増した。現在も作り続けられているゴルフGTIの初代は、1.6Lから110psを発生していた。いずれのクルマも、小さな体に大きな力を秘めていたのだ。
ハッチバックは1980年代に入っても、若者を中心に根強い人気をキープし続ける。その中で、異彩を放っていたのが3代目シビック、通称“ワンダーシビック”だった。
ワンダーシビックは3ドアと5ドアのハッチバック、4ドアセダンという3つのボディ全てが専用設計で、3ドアはスポーツカーのように低く、5ドアは逆に現在のSUVを思わせる背の高いシルエットで、「シャトル」というサブネームが与えられていた。
しかし、その後はバブル景気の到来で、多くのユーザーが高級志向に走ったこともあって、ハッチバックに目を向ける人は少なくなっていく。この時期は、日産自動車が初代「マーチ」をベースにレトロ風デザインを与えた「Be-1」「パオ」「フィガロ」が目立っていたが、バブル崩壊とともにこの流れは消滅している。
その頃からハッチバックの主役となっていったのは、1991年発表の2代目「マーチ」、1999年デビューのトヨタ自動車「ヴィッツ」、2001年誕生のホンダ「フィット」といったクルマたち。つまり、実用的かつ経済的な車種だ。「コンパクトカー」という言葉もこの頃に生まれた。一方、かつて一世を風靡したホットハッチは次々に姿を消していった。
元来、欧州でハッチバックは合理性重視の車種として認識されていたのだが、質実剛健なVWのゴルフがベンチマーク的な存在となったことで、その印象が強まっていく。ルノーの「5」も、1990年に後継車の「ルーテシア」(欧州名はクリオ)が登場したあたりから、実用性を重視する方向性にシフトしていった。
2001年にBMWプロデュースの新世代「ミニ」が誕生した後には、VW「ニュービートル」やフィアット「500」など、かつての大衆車のリバイバルが相次いだ。これらのクルマは、パーソナルカーとしてのハッチバックの役目を受け継ぐ存在のようにも見えたのだが、そもそも元ネタがないと生まれなかったわけだし、世界的なブームになるまでには至っていない。
実用車からの脱却が始まった? ハッチバックの今後は
しかし最近、ハッチバックに新たな流れが生まれつつあると感じている。SUVやミニバンの台頭もあってか、実用性追求の姿勢が薄れつつあるのだ。かつてのルノー「5」やワンダーシビックのように、ファッショナブルでスポーティな方向性を目指す車種が増えてきたような気がする。
その流れを象徴しているのが、これまでもハッチバックに革命を起こしてきたシビックではないかと思っている。
かつては日本製ハッチバックの代表格だったシビックだが、2005年発表の9代目から国内生産はセダンのみとなり、ハッチバックは高性能版の「タイプR」を英国から輸入するようになっていた。しかし、10代目となる現行型では、やはり英国からの輸入車ではあるものの、タイプR以外のハッチバックが復活している。
ボディサイズはかつてのシビックと比べるとかなり大柄になったが、長さや幅に対してかなり低いプロポーションや、窓が大きくて開放的なインテリアなどは、1980年代のワンダーシビックを思い出させてくれる。
トヨタが2018年夏、12代目カローラのトップバッターとして発売した「カローラ スポーツ」も、これまでカローラが守り続けてきた5ナンバー枠を脱したボディサイズに加え、個性的なフロントマスクもあいまってダイナミックな雰囲気を発散している。
そして、今年の注目はマツダの新型「マツダ3」(日本名はアクセラ)だ。長いボンネット、高めのベルトライン、小さなキャビン、スロープしたリアなどに加え、キャラクターラインをほとんど使わず、線ではなく面で形を表現しているところなど、理屈抜きにカッコいい。
新型マツダ3の原型は、2017年の東京モーターショーに「魁(カイ) コンセプト」という名前で登場していた。その時にマツダは、ワンモーションのシンプルなラインでフォルムを描きつつ、繊細な造形で光の移ろいやリフレクション(反射)の動きをクルマに取り込むことで、これまで以上に力強く、味わい深い生命感を作り込んだとアナウンスしていた。でもそれが、ほぼそのまま市販型になるとは思わなかった。
もちろん、ゴルフに代表される実用的なハッチバックが消えていくとは思っていない。しかし、SUVやミニバンが実用車の役目を担う今、ハッチバックがパーソナル化するというのは理解できる流れだ。今後はこうした車種がいくつも登場してきそうで、長年ハッチバックに乗り続けてきた筆者は嬉しい気持ちになっている。