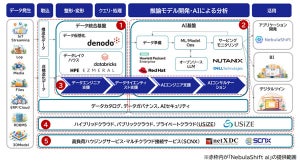Microsoftが間もなくリリースを予定しているOffice 2010には、これまでにない2つの特徴がある。1つはWebブラウザ上で動作するクラウド版が用意されること、もう1つは機能限定の無料版が用意されることだ。価格競争力でライバル製品をことごとく打ち負かしてきたMicrosoft Officeは、現在では同社ビジネス部門の売上の90%を占め、社内全体の営業利益では60%を占める大黒柱だ。だが同製品はいまGoogle Appsという製品にかつてないほどの競合にさらされており、Office 2010での初の試みの数々もその延長線上にある。Microsoftはこれまでの勢いを維持できるのか、その行方に注目が集まっている。
同件についてレポートしているのは、米Wall Street Journalの3月29日付けの「Microsoft Office Faces Challenge From Free Google Tools」という記事だ。前述のようにMicrosoftはWindowsとOfficeという2大製品に極度に依存しており、最近では特に景気後退による企業のIT投資抑制の影響を強く受けている。コンシューマ版Officeの販売価格が100ドル程度なのに対し、エンタープライズ版Officeのライセンス価格は数百ドル程度とさらに高くなっており、もし低価格戦略が浸透した場合、業績への影響は大きい。
だが現時点で、Googleがエンタープライズ市場に与える影響は限定的のようだ。WSJでは3つの事例を紹介しているが、MicrosoftがGeneral Motors (GM)やStarbucks Coffeeといった大手とのOfficeソリューションに関する大口契約を結ぶ一方で、電機メーカーのSanmina-SCIが1万6,000人の従業員の電子メールシステムをMicrosoft ExchangeからGmailに変更するといった、比較的小規模なレベルに収まっている。Googleのエンタープライズ版GmailやGoogle Appsの魅力は年間契約あたりの利用料金の安さだが、米Gartnerの試算によれば、Google Appsの全2,500万ユーザーのうち、有償サブスクリプション契約を結んでいるユーザーはわずか100万ユーザー程度だという。Googleにとってエンタープライズ市場の規模はまだそれほど大きくなく、ハードルが高いようにも見受けられる。
一方でOfficeのWeb対応、つまりクラウド化は、MicrosoftにとってのGoogleへの戦略的対抗措置となっている。OfficeアプリケーションをWebブラウザ経由で利用できるメリットの1つは、ソフトウェアのマシンへのインストールなしに、どこからでもデータを閲覧し、編集が可能な点にある。これはモバイル機器等でのリモートからのアクセスのしやすさや、チーム間での作業のしやすさに直結する。Microsoftではこのほか、Office製品と連携するExchangeやSharePointのクラウドサービスを1年前より提供しており、主に中小企業をターゲットに販売を続けている。先日、Microsoftが「Windows Essential Business Server (EBS) 」の新規開発を停止したことを紹介した(http://journal.mycom.co.jp/news/2010/03/08/018/)が、これも同社がクラウド戦略を推進するなかで、社内競合する製品の優先順位を落としたことに起因する。
ライバルの登場でクラウド化が推進され、製品が強化されつつあるのが現在のMicrosoftだといえるかもしれない。一方でGoogleは苦手分野であるエンタープライズ市場をどのように攻略していくのだろうか。こうした戦いは、Windows AzureやGoogle App Engineといったバックエンド型のサービスでの企業の取り込みを含め、幅広い分野でこれからも続いていくことになるだろう。