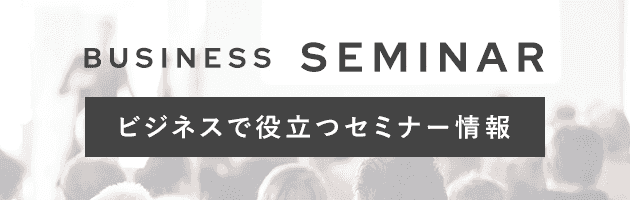みなさんはいま、何が日本の電力供給を支えているかご存知でしょうか。
今回は、日本の電力供給のほぼ3分の1を担う「石炭火力(※)」、なかでも従来型では最高の効率を誇る「超々臨界圧石炭火力発電」(USC)についてのお話です。現在における石炭火力の立ち位置とこれら電力の今後について解説します。
現在の日本の電力供給を支える石炭火力は、政府が掲げる「エネルギー基本計画」(※)でも、2030 年時点の電源構成で26%程度を占めるという位置付けになっています。
石炭火力のなかでも、最高の発電効率とその分CO2の発生量も少ない石炭火力発電技術が「超々臨界圧石炭火力発電(USC:Ultra-Supercritical)」と言われる技術です。そこで本稿では、最新技術である「USC」やその背景にある「石炭火力発電」そのものの必要性についても考えてみたいと思います。
最新技術「超々臨界圧石炭火力発電(USC)」は何が違う?
石炭火力発電は、蒸気機関車と同様に石炭を燃やして水蒸気を発生させ、その力で羽根車(タービン)を回して発電しています。発生した水蒸気の力でピストンを押して車輪を回すのが蒸気機関車になります。
水蒸気に仕事をさせるとき、常温常圧との温度や圧力の差が仕事量になるため、蒸気温度や圧力が高ければ高いほどより多くの仕事をさせることができ、発電効率(使う燃料あたりの発電量)が高くなるのが特徴です。
このため、石炭火力の高効率化には、水蒸気の高温高圧化の追求によって行われてきた歴史があります。水蒸気温度374.2℃および圧力22.1M㎩(225kgf/cm2)を臨界温度及び臨界圧力といい、これを超えると液体と気体の特性を併せ持つ超臨界状態になります。これ以下の温度と圧力で発電する技術を亜臨界圧発電、それ以上の温度と圧力で発電する技術を超臨界圧発電(SC:Supercritical)といいます。
このSCをさらに上回る高効率化技術が、超々臨界圧石炭火力発電(USC)です。これは、石炭ボイラで温度593℃以上、圧力24.1M㎩(246kgf/cm2)以上という高温高圧の水蒸気を発生させ、その水蒸気でタービンを回して発電する技術です。1993年4月に、日本で初めてのUSCである株式会社JERA(当時、中部電力株式会社)の碧南3号の稼働以降、日本の大型石炭火力発電所にはこのUSCが採用されています。USCは、高温高圧に耐える材料や溶接など高度な技術が要求され、これらの技術開発は日本がリードしてきました。今やこの技術は世界中の⽯炭⽕⼒発電所に広く適用されています。
技術は日々進歩しています。今年6月に営業運転を開始したJ-POWER(電源開発株式会社)の竹原新1号(広島県)は、最新のUSC発電所。都市型の新鋭火力として有名な横浜にある同社の磯子新2号(蒸気温度620℃、圧力25MPa)をさらに上回る、蒸気温度630℃、圧力は27MPa(275kg/cm2)と世界最高水準の高温高圧条件による高効率化が図られています。より少ない燃料でより多くの電力を取り出すことでCO2の発生を抑え、より環境にやさしい石炭火力を目指しているのです。
さらに、現在のUSCよりもさらに高温高圧を目指した先進型のUSCの研究開発もすすんでいます。700℃を超える高温と35MPa(357kgf/cm2)の高温高圧水蒸気を使うA(Advanced) -USCです。従来の石炭火力と同じシステム構成により経済的に既存のUSCを更新し、さらなるCO2の削減が期待されます。
日本の電力供給を「石炭火力」に頼る理由
それは、日本のエネルギー事情が大きく影響しています。イギリスやフランスなどのヨーロッパ諸国では一部の産炭国を除いて石炭火力は少なく、種々のエネルギーが自給できています。さらには各国が送電線やガスパイプラインで繋がっていて、エネルギーを融通し合えるのです。一方、ほぼすべてのエネルギーを海外から輸入し、しかも他国との送電線やパイプラインの連係がない日本では、エネルギーの安定供給が非常に重要です。
そのため日本のエネルギー政策は、安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境への適合(Environment)、安全性(Safety)の「3E+S」が基本。電力では複数のエネルギー資源を併せて使う「エネルギーミックス」が基本となっており、他のエネルギー資源に比べて世界中に豊富に賦存(ふぞん)し価格も安い石炭は安定供給、経済効率性の面で重要な資源のひとつとなっています。このような背景のもと、日本の電力の32%を石炭火力が担っているのです。
他の燃料に比べてCO2の発生量が多いことが石炭の弱点ですが、この問題を解決するために高効率化が進められているのです。
現在も進化を続けている石炭火力「USC」、実証段階に入った「IGFC」
日本のエネルギー事情もあり、今後も日本の電力供給を支え続ける「石炭火力」。 先述の通り、従来の石炭火力から大きく効率化が図られたUSCは、現在も進化を続けています。 今後、再生可能エネルギーが主力となっていくなかで、ベース電源や調整電源となって電力安定供給を担うため、引き続き、USCを主体に石炭火力を活用していく必要があるのです。
CO2の排出削減に向けた新しい技術として、USCのように石炭を直接ボイラで燃焼させる方式ではない石炭火力発電技術も実用化されました。石炭をガス化炉でガス化してガスタービンを回し、さらにその熱で水蒸気を作り蒸気タービンで発電する石炭ガス化複合発電(IGCC)が実用化されたのに加え、IGCCに燃料電池を加えた、石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC)の実証事業が大崎クールジェン(広島県)で開始されています。
このように日本の電力供給を支える石炭火力は、高効率化に向け日々チャレンジが続けられています。さらなる技術開発から目が離せません。
関連リンク:
>>>2020/9/8~9/10
オンライン方式で「第29回クリーン・コール・デー国際会議」が開催されます
[PR]提供:クリーン・コール・デー実行委員会(事務局:一般財団法人石炭エネルギーセンター)