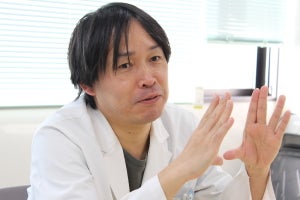12月1日に都内で開催された「第82回 日本皮膚科学会東京支部学術大会」において、皮膚がんの早期発見に役立つ「ダーモスコピー」の普及を促進する取り組みが紹介された。ここでは関連するセミナーの様子と開発中のダーモカメラの展示を紹介する。
臨床現場のニーズに応える臨床&ダーモカメラ
ダーモスコピー(dermoscopy)は、悪性の皮膚病変、特に「ほくろのがん」とも呼ばれる「悪性黒色腫(メラノーマ:malignant melanoma)」の早期発見への有効性が認められ、十年ほど前から急速に普及してきた。ダーモスコープという特殊な拡大鏡で病変部を観察する診療方法で、薬品を用いたりせず、低コストで診断できるのも特徴だ。
ただし、ダーモスコピーは医師に代わって診断してくれる技術ではなく、あくまで病変を拡大して見やすくする技術にすぎない。このため、医師が所見を理解するには十分な専門知識と診断の経験、「勉強」が必要になる。
今回の学術大会におけるダーモスコピー関連のセミナーも主眼はそこにあり、集まった受講者の知識と経験の底上げを目指す内容となっていた。
東京女子医大東医療センターの田中勝先生が座長として進行を務めるランチョンセミナーでは、千葉大学の外川八英先生がトップに登壇し「新たなダーモカメラによる診断へのアプローチ」と題して講演した。
外川先生はまず、現在の皮膚科の外来初診室では、デジタルカメラで撮影したダーモスコープ画像をFlashAir™(※)で飛ばし、ネットワークストレージに記録。同時に大型モニターで表示し、さらに電子カルテに取り込むなど、デジタルカメラが大変重要な役目を担うようになったと述べる。
※無線LAN機能付きSDカード
ところが、外川先生が現在使用中のダーモスコープ+カメラは約1.3kg。臨床用カメラは1.5kgと重く、大きく、壊れやすいのが悩みだという。このため現場では、臨床写真とダーモスコピー画像が同じカメラで撮影でき、病変全体を撮影でき、ワンボタンで偏光/非偏光の撮影ができ、オートフォーカスに対応、コンパクトで軽く、丈夫なカメラが欲しいというニーズが高まっていた。
これを知ったカシオが外川先生を始めとする皮膚科専門医と協力。「臨床&ダーモカメラ(仮称)」の共同研究開発に乗り出し、いまは試作機でテストを繰り返している段階だ。試作機ではすでに悩みの多くを解消する工夫が盛り込まれている。
たとえば、本体重量は約300gと軽量に抑え、病変を含む部位全体を写す臨床写真も撮影可能。ダーモスコピー撮影は偏光・非偏光・UV画像がワンシャッターで記録できる。撮影時に周辺部に歪みが発生しないようなレンズ構成になっており、病変部を接写することで、被写体のサイズを把握することができるスケールの表示も可能だ。
この臨床&ダーモカメラを利用することで、現場でダーモスコピー画像をより容易に撮影することが可能になる。同時に得られる画像のクオリティの向上も図れ、ひいてはダーモスコピー学習用の優れた教材も増えるという訳だ。
外川先生は最後に、ダーモスコピー学習サイト「D'z IMAGE」に英語版のページが登場したことにも触れた。D'z IMAGEは、カシオが運営するクラウドサービスで、ユーザー登録することで無料で利用可能だ。豊富な症例データベースを参照しながら、効率良くダーモスコピーが学習できることから、皮膚科医はもちろん、他の科の医師や医師を目指す学生も活用している。
AI開発から分かるダーモスコピー診療における経験の重要性
続いて、初来日したウィーン医科大学のハラルド・キトラー(Harald Kittler)先生が登壇した。キトラー先生は皮膚科の世界的な権威で、この機会に先生の講演を聴講しようと、大勢の医療関係者が集まった。
講演のタイトルは「Ghost in the shell: Will machines replace human expertise in skin cancer diagnosis」。日本語訳すると「ゴースト・イン・ザ・シェル: 機械は皮膚がん診断において人間の専門家に置き換わるか」といったところ。「Ghost in the shell」はもちろんあの作品のことで、日本の聴衆を意識したサービスだ。
キトラー先生によれば、人間の代わりに機械に皮膚がんを診断させる試みは実はかなり古くから研究されており、1950年代には既に「Expert systems」と呼ばれる取り組みが始まっていたという。1985年頃からニューラルネットワークを用いて診断する仕組みが開発され、その当時は10年後には診断が機械に取って代わると言われていたそうだ。
しかし、たくさんの試験が繰り返され、機械学習が重ねられていきながらも、機械が診断するようにはならなかった。この当時、病変部の写真から所見を見分けるテストでは、機械は人間よりも正確に所見を見抜けたが、臨床では未だ使い物にならなかったのだ。
やがて、2012年頃からディープラーニング(深層学習)が始まり、再び、近未来に機械が人間に取って代わると言われた。だがやはり、人間の代わりに診断まで行う機械(AI)は未だに実用化されていない。
昨今、世界最高のラボを用意してディープラーニングで学習させたAIと、専門の医師達とで、病変部の画像から病名を当ててスコアを競うテストが実施された。このテストでは良性病変の画像も大量に加えて行われたが、AIが圧倒的な正確さで勝利する結果に終わった。
テストではトップクラスのエキスパートでさえ手も足も出ないほど優秀な成績を出すAIは、なぜ医療現場では医師と交代していないのか。
ヒントのひとつは、医師達の成績を分析した時、ダーモスコピーの経験が長い医師ほど成績が良かった点にある。しかも、経験さえ長ければ皮膚科でなくても成績が高いという、専門医にとっては残念な結果まで明らかになった。
ここから分かることは、医師の経験が大きく影響すること。経験の深い医師は何をしているのだろうか。結論を言ってしまえば、「経験の深い医師ほど所見だけ見て判断していない」となる。患者の顔色や体調、患者との会話や天気などの周囲の状況も参考にして、総合的に診断を下す。AIにはこれができないのだ。
AIが少なくとも近い将来のうちに、医師の存在意義を奪うことがないと分かっても、次の疑問が頭をもたげる。どれだけ進化してもAIが医師に取って代わることがないのであれば、何のために開発するのか。
この答えはシンプルだ。テストで示されたとおり、AIにはベテラン医師も及ばぬ得意分野を持つ。つまり、役目を限定すれば大きな助けになるからだ。
例えば、ホクロがたくさんある人は、新たにホクロができても気が付きにくいが、定期的に肌を撮影してAIに探させれば、人間では容易に見つけられない変化も簡単に見つけ出す。現在の技術でも、スマートフォンが一台あれば自分で自分の肌を観察して、異常を探せるところまで来ているのだ。
キトラー先生は、「Ghost in the shellの世界のように、機械が人体を支配してどうこうする世界にはならない。AIは画像から診断しないので変な失敗もする。人間に取って代わるものではなく、人間の手は必ず必要だ」と語った。
ダーモスコピーの普及は日本の医療の底上げにつながる
午後にはこれまでの「ダーモスコピー道場」に代わる「ダーモスコピークイズ」が開催された。ダーモスコピー画像を見て、疾患名を診断するクイズで正解率が優秀な参加者には豪華な景品も出すという、少しエンタメ性を持たせた催しとなっている。特に今回は参加者がスマートフォンかタブレットを持参してクイズに参加するスタイルを採用。こちらも約200名の席は満席となる盛況ぶりだった。
クイズに先立ち、田中先生による「メラノサイト病変」と題するミニレクチャーも実施され、出題に向けての参考となっていた。
セミナー会場のすぐ近くには協賛メーカーがブースを出展するコーナーがあり、開発中の臨床&ダーモカメラもカシオのブースで展示。ランチョンセミナーで外川先生が紹介したこともあり、多くの来場者が足を止めて実際に手に触れたり、説明員に話を聞いたりしていた。
前回の取材のときからも進化を続けており、たとえば今回は新たに付け剥がしの容易なレンズフィルムを用意していた。レンズを病変部に密着させて撮影するとレンズに皮脂が付着してしまうが、いちいち拭き取らなくてもフィルムを剥がせばメンテナンスできるというわけだ。
また、液晶画面はスマートフォンと同じ操作性を意識して、二本指による拡大縮小操作に対応した。これは以前の取材中に外川先生がリクエストしていた機能で、さっそく実装された形だ。
冒頭、臨床&ダーモカメラを紹介した外川先生は、キトラー先生が「皮膚科医か内科医じゃなくて、経験年数が大事なんだ」と述べた言葉は、示唆に富んでいるという。日本でも都心部の大きな病院だけでなく、離島の医師でも往診医でも、臨床&ダーモカメラで見て「あ、これは危ないな」と気づけば、悪い病気を見つけやすくなる。
臨床&ダーモカメラは皮膚がんの発見に特化している訳ではないので、別の病気の兆候でも医師や看護師が異変に気付いて撮影することで早期発見、診断の取っ掛かりとなる。専門医以外でも扱いやすい点が大きなポイントだ。
「日本は人口あたりの医師の数が多く、往診も多いため、ダーモカメラが活躍する余地が多い」と外川先生は指摘する。
ダーモスコピーの普及で、皮膚がんに対する危機意識を一般人レベルから高められれば、皮膚がんの早期発見率が上がり、相対的にがんの死亡率は下がっていく。臨床&ダーモカメラは、その道筋を切り拓く大きな可能性を秘めている。
[PR]提供:カシオ計算機