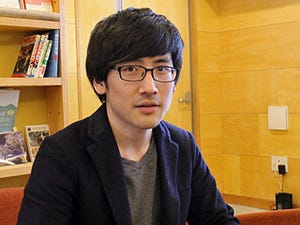対戦やシューティングゲームまでできる「けん玉」
モノとインターネットをつなぐ“IoT“が、いよいよ本気を出してきた。「スマートスピーカーに語りかければ、好みの動画や音楽が再生できる」「外にいながらスマホで、エアコンなどの家電がカンタンに操作できる」といったIot製品やサービスが数多く登場。人々の利便性と期待感を、ぐぐっと押し上げはじめているからだ。
もっとも「電玉」が、今春発売したIoT機器には、そうした“利便性”はあまりない。ただ、その分、ワクワクするような“期待感“は、ほかのIot製品よりずっとありそうだ。
株式会社電玉の大谷宣央代表。1983年生まれ。某大手メーカーを経て独立。けん玉をIoT化した「電玉」で、世界に挑む。「僕自身もけん玉は昔からやっていましたが、最近、デモをやる機会が増えて、ずっとうまくなりましたね(笑)」
何せ、同社がIoT化したのは、日本の伝統おもちゃ「けん玉」。そう。電子×けん玉で「電玉」というわけだ。
「見た目はよくあるけん玉ですが、3つの受け皿と尖った剣先の内側には、それぞれコイル状のセンサーがついているんですよ」と、開発者で同社代表の大谷宣央さんは言う。
仕組みはこうだ。「電玉」のボディに、金属のメッキが施された玉が近づくと、周波数が変化する。それによってボディから玉の距離を即座に認識。さらにボディの内部にはジャイロセンサーや加速度センサーも内蔵されているため、「大皿にどんなタイミングでのったか」「大皿にのせたあと、剣先にうまく刺さったか」といった玉の動きはもちろん、けん玉の細かな角度まで、データとしてリアルタイムで分かるわけだ。
ようするに、「とめけん」や「日本一周」などのけん玉でどんなワザを繰り出して成功したか否かまでを、センシング技術で正確に瞬時に判別してくれるのである。
「この電玉の動きが通信モジュールでタブレットやスマホのアプリと連動させられる。だから、ネットを介して世界中のプレイヤーとワザを競い合う“対戦プレイ”ができたり、電玉をコントローラー代わりにした“けん玉のワザでマトを倒していくシューティングゲーム”などもできる。またAPIを公開して、いろんな個人や企業が電玉を使ったアプリを開発してもらうことを考えています」(大谷さん・以下同)。
そもそも、派手なトリックがいろいろできるけん玉が「KENDAMA」として、海外でも「クールな遊び」として今や世界大会が開かれるほどポピュラーになっているのは周知のとおりだ。けん玉の遊び方を拡張する「電玉」の登場が、この流れがさらに加速していくに違いない。
「もっとも……最初は、けん玉をIoT化しよう、なんていう発想はまったくなかった。『老人用の杖をIoTで作れないか』と考えていたんですよ(笑)」
公園のおじいちゃんへのヒアリングから生まれた。
1983年生まれの大谷さんは、小学生の頃からプログラミングで遊ぶようなエンジニア体質。複雑系ネットワークを学んだ後は、開発や企画などの仕事をしていた。
「ユニークな開発や企画などをさせてもらっていました。ただ一方で、会社の判断は常に慎重。なかなか手がけたプロジェクトがカタチにならないフラストレーションは、いつもありましたね」。
薄い紙も積み重ねれば、うず高くなるものだ。大谷さんは2015年、31歳で会社を退職。「自ら手がけたものを製品化して世に問いたい」というモチベーションを胸にあるハッカソンに参加した。時代は「IoT」という言葉がポピュラーになり始めた頃。そこに「高齢化」というマーケットのニーズを練り込もうとした。
「そこでハッカソンでは高齢者向けのITデバイスを考えた。『勝手に外に連れ出してくれる杖』のようなものを提案したんです」
最初のプレゼン、評判は想像以上に良くなかった。「危ないでしょ?」「実現性がないのでは?」「そもそもおもしろくないよね」。しかし、ITで高齢者の課題を何か解決したい…というコンセプトは間違ってないという声もあった。「それなら、実際のニーズを聞いてみよう!」。そう考えた大谷さんは、公園へ向かった。え、公園?
「上野にあるシニアがよく集まっている公園があって、でそこへ。『すいません…こんなものがあったらいいな、みたいなものあります?』と直球でヒアリングというか、世間話ですね(笑)」。
ここで聞こえてきた声がヒントになる。「孫たちともっと遊びたいけれど、今のゲームは難しい」「昔のおもちゃみたいなものだったら遊べるんだけれど…」。IT×伝統的なおもちゃの着想が、生まれた瞬間だった。
「シニア層も自然に楽しめて、子供たちもゲーム感覚で嬉々と遊べる。世代を超えて皆が楽しめるものがIT×伝統おもちゃでできそうだなと思いついた。コマや竹馬なんかもあるけれど、サイズ的にも気軽さからも『けん玉』がいいだろうなとそこまでは早かったですね。ただ…」
日本人ならほぼ誰しも一度は触ったことがあるようなおもちゃ。「すでにIoT化したけん玉を誰かが手がけているに違いない…」という危惧をいだいた。
これが「電玉」。一見、普通のけん玉に見えるが、中には加速度、ジャイロなどのセンサーとLEDや振動モーターなどがはいったIoT機器だ
「結論からいうと、ラッキーなことに誰も手がけていなかったんですけどね。そこで一気に企画を作り上げた。それを2回めのハッカソンで発表すると前回とは全く違う手応えを得ましたしね。これはイケる、とさらに確信しました」
しかし、走り始めると、“誰も手がけてなかった”理由が見えてきた。
ヒントになったのは空港にもあるアレだった。
ハッカソンでの提案に前後して、実はKDDIが支援するスタートアップ支援を受けられることになった。またハッカソンではプログラマーやデザイナーなどのスタッフとも出会うことにもなった。さらにクラウドファンディングで130万円ほどの資金を集められた。
順風満帆なまま、大谷さんは、2016年に株式会社電玉を創設。しかし、いよいよ「もの」をつくる段になり、悪戦苦闘がはじまった。
「考えてみたら当たり前なんですけどね。まず小さなボディにセンサーとバッテリーや回路をのせるのは極めて困難だった。そのうえガンガンと球をあてる遊びなので、衝撃に強い必要もある。そのうえで複雑なけん玉のワザを、しっかりと精緻にセンシングできるようにしなければならない……。とまあ、ようは『ああ、面倒だから誰も手がけられなかったんだな』と(笑)」。
例えば最初の頃は、フォトリフレクターという光を検知するしくみでセンシングする方法を社内メンバーで考えた。皿や剣先に球がのったり、刺さったりすれば、暗くなるので、その明暗の差で「のった」「刺さった」と検知できるからだ。
「ところが、当たり前ですがそれだと明るい場所じゃないと検知できない。しかもけん玉って、いろんな持ち方をして、皿の部分を思いっきりもって繰り出すワザもある。そもそも皿に乗せずに皿と皿の間の部分でとめるワザなどもある。光によるセンシングそのものが、もう使えないと考えた」。
-
電玉」と連動して遊べるアプリ画面。対戦やシューティングなどのゲーム要素はもちろん、着実に技を習得できる練習ツールによってアナログではできなかった「ワザの習得の見える化」を実現。けん玉プレイヤーの裾野のレベルアップにも貢献しそうだ
ただ、こうした技術的なハードルに即座に早めに気づき、次の一手を受けたことは電玉がうまくローンチできた大きな要因だった。後押ししたのは、得意の“ヒアリング”だった。試作段階で、「グローバルけん玉ネットワーク」というけん玉団体と知り合い、彼らからけん玉の様々なワザを教えてもらった。その結果、「皿をもってもワザが検知できる仕組みが不可欠」「けん玉の角度が測れないと意味がない」など、よりリアルな競技者の声を製品に落とし込めたからだ。
「彼らの声を聞くまでは、もっとメカ的なギミック。たとえば、対戦システムで相手がけん玉のワザに成功したら、相手のけん玉の大皿に磁石がついていて、皿にのらなくなる…とか。逆に何かアクションをしたら、ビタッ! と磁石で皿に球がすいつくような普通のけん玉ではありえないようなワザができたらおもしろい、という発想でいた。けれど、けん玉のプレイヤーにきくと『いや。そうではなく、今のけん玉のワザをまずしっかりとセンシングしてくれるほうが市場がひろがる』『すでにいる世界中のけん玉プレイヤーに響く』と。それはそうですよね」。
もっとも、当初の「磁石」の発想も、今に活きている。けん玉の皿に磁石のようなギミックをいれるため、皿の部分に電磁コイルを備え付ける発想は早くからあった。これそのものをセンサーとして利用できるのではないか、と繋がったからだ。
「空港にある『金属探知機』と同じです。金属が近づくと、電磁コイルが周波数が変化して分かる。『そうか、玉に金属をメッキすれば、できるな』って」
しっかりセンシングするほど玉の金属メッキができず時間がかかったり、センシングが温度に左右されて回路的な調整が必要であったり。あるいは大量生産のための工場を中国で見つけるも、最終的に品質面で折り合えず、急遽、国内生産に切り替えたり――と右往左往しながらも、2017年3月には正式リリースにこぎつけた。
クラウドファンディングに参加した方に配布は約束より数カ月遅れたが、けん玉は難度の高い技をクリアしたときこそ盛り上がるものだ。現在はアマゾンや家電量販店などを販路に、人気を博している。
「来年は世界大会を開催する予定。海外のプレイヤーからの注目は高いので、ここでブレイクしたらいいなと考えています」。
それだけじゃない。アプリのプログラム、電子部品の組み立て、3Dプリンタによる筐体づくり、さらには体を動かすゲームからの学び…など、電玉にはIoTや、これからのものづくりを学ぶための要素が凝縮されている。格好の教材だ。
「小中学校などの教育用途での展開も考えています。ついでに体も動かしますからね。フィットネスの分野でも楽しみながら体を鍛えるプログラムとして活用できるはず。シニアと子供たちのコミュニケーションがひろがれば…というアイデアからたどり着いた電玉。想像以上に可能性をひろげそうです」。
高齢者を外に連れ出すための杖――。そこから始めった発想が、“魔法の杖“のように世界を広げていく。電玉がワクワクさせるのは、きっともっとこれからだ。