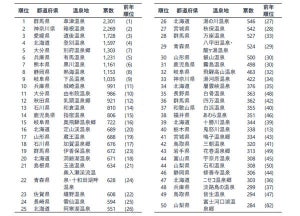この連載では、2020年の東京、これからの都市と生活についての記事を「PLANETSチャンネル」から抜粋してご紹介しています。"東京2020"がテーマの文化批評誌『PLANETS vol.9』(編集長: 宇野常寛)は今冬発売予定。
2020年の東京を舞台に、宇野常寛氏が仕掛ける「A,B,C,D」とは? もうひとつのオリンピックに東京の都市開発、カルチャーの祭典、そしてフィクションとしての破壊計画まで……。4つのキーワードで、『PLANETS vol.9』のコンセプトが語られます。【構成: 中野慧】
宇野常寛(うの・つねひろ) 評論家。1978年生。批評誌〈PLANETS〉編集長。著書に『ゼロ年代の想像力』(早川書房)。『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎)。『日本文化の論点』(筑摩書房)、『原子爆弾とジョーカーなき世界』(メディアファクトリー)。共著に濱野智史との対談『希望論』(NHK出版)、石破茂との対談『こんな日本をつくりたい』(太田出版)。企画・編集参加に「思想地図 vol.4」(NHK出版)、「朝日ジャーナル 日本破壊計画」(朝日新聞出版)など。京都精華大学ポップカルチャー学部非常勤講師も務める。 |
「64年の東京五輪をもう一度!」というノスタルジーにどう向き合うか
――ポップカルチャーをはじめとした「文化」の側から発言してきた宇野常寛という評論家が、スポーツの祭典であるオリンピックについて提言しようと考えたきっかけはどんなものだったんでしょうか。
宇野 2020年の東京オリンピックが決定したとき、これは放っておけないなと思った。このままだと2020年の東京五輪は、戦後日本の最後の盛り上がりに、線香花火が落ちる前にぱっと輝くあの最後の一瞬になってしまうんじゃないかと思ったんですよ。実際に、今回の東京五輪招致運動には、1964年の最初の東京五輪の時代の、高度成長の頃の日本を取り戻したいという願望が終始見え隠れしていたと思うわけ。あの日本人が自信を取り戻した64年よもう一度、とね。
でも、当時とは何もかも違う今の下り坂を転がり落ちる日本に、無理矢理オリンピックを呼んで表面的に元気なふりをしても何も生まないと思う。いい加減にこの国は「プロジェクトX」や『ALWAYS 三丁目の夕日』的な「あの頃はよかった」というノスタルジーから脱却すべきだと思う。
だから僕は逆に、自分たちが考える2020年のオリンピックを提案してやろうと思ったんですよね。亡くしたものの数を数えながら、過去の成功体験に逃げ込んで現実から目を逸らすのではなく、2020年に五輪がやってくることを「利用」して、〈古い日本人の思い出を温めるもの〉から〈新しい日本人の希望になるもの〉に変えていくことが必要なんですよ。
そこで、僕自身が編集長となって刊行している「PLANETS」の最新号、『PLANETS vol.9』(以下、『P9』)の特集を「東京2020」として、オリンピックに関連する社会提案を出していこうと考えたんです。
「テレビオリンピック」から「インターネット以降のオリンピック」へ
――では『P9』ではどんな考えのもとに、どんなプランが2020年の東京五輪に対して提示されるのでしょうか。
宇野 内容は、各パートにおけるテーマの頭文字をとって「A」「B」「C」「D」の4パートとしました。Aは「Alternative」、Bは「Blueprint」、Cは「Cultural Festival」、Dは「Destruction」を表しています。
まず「A」は、オルタナティブ・オリンピック/パラリンピックを考えるパートです。さっきも言ったようにオリンピックというのはメディア装置としての機能が大きく、とりわけ1984年のロサンゼルス五輪以降は、何億人もの人々が視聴する広告媒体としてその価値が急騰し、「テレビオリンピック」や「商業オリンピック」とまで言われるようになった。オリンピックはマスメディア時代のビッグコンテンツとなっている。
しかし、2020年の東京五輪というタイミングは、そろそろこの「テレビオリンピック」から脱却していく時期だと思うんですよね。
オリンピックの招致が決まる前って、街中やテレビなどの至る所に、テレビタレントや「スポーツ文化人」たちの、「五輪招致が成功したら、私・〇〇は、××します!」という限りなくジョークに近い公約が掲げられていましたよね。たとえばお笑い芸人の浜田雅功(ダウンタウン)は「開会式のどこかで必ず見切れます」、女子サッカー日本代表選手・澤穂希は「銀座のホコ天でサッカーの試合をします」、というふうに。
これを見て僕は、率直に言ってサムいと思ったし、「日本中の誰もがテレビを見て、テレビタレントを人気者として認知する『世間』に所属している」といまだに思っている広告屋やテレビ局のどうしようもない傲慢さを感じてしまった。仮にもしそんな世の中が持続しているのなら、広告もテレビも昔のように羽振りがいいはずだし、ニコニコ動画もボーカロイドも普及していないし、テレビに出ない(出られない)ライブアイドルのブームも起こるわけがない。そういったインターネット以降の「夜の世界」の拡大を、テレビや広告業界などの「昼の世界」の人たちは決定的に見過ごしている。
ある時期からの近代オリンピックは「国民統合」、つまりばらばらの人々をひとつにまとめて、国民の一体感を高める道具として機能していて、その典型的な例が1936年のベルリンオリンピックだったと思います。第一次大戦で敗戦国となり、その後の大不況などで疲弊しきったドイツ国民を、ナチスの名のもとにまとめあげていく役割をオリンピックは果たしたわけです。
でも、現代の先進国の成熟社会に、ばらばらの人々をひとつにまとめるためのマスメディア的なオリンピックなんて必要ないと思う。むしろ従来の五輪の「感動をありがとう!」的な押し付けがましさや、「同じ日本人だから応援しよう!」という空気に違和感を抱く人も増えていますよね。これから必要なのは、ばらばらの人たちがばらばらのまま共存できるオリンピックじゃないかと思う。
具体的には「インターネット以降のオリンピック」が提示されるタイミングに来ていると思う。2020年の東京はその恰好の舞台となるはずです。そうなるとネット以降の文脈で、開会式や競技中継のあり方をどう面白くできるのかが課題になってきます。
現代のオリンピックは何よりも「テレビで見るもの」になってしまっていて、開催地の街にいる人がチケットが手に入らなくて閉め出されてしまうということが現実に起こっているわけです。そういった状況に対して、チケットを持っていない人間も、テレビ中継ではない「スタジアムならではの空気に参加できる」オリンピックを提案したいと思っています。
そもそも僕のような人間がオリンピックに興味を持てないのは、テレビで見ているだけでは「自分も参加している」という実感が得られないからです。ですが日本のインターネットや情報関連の技術はこの「実空間を超えて空気を共有し、自分も参加している実感が得られる」という部分で強みを発揮できると思います。
このパートはチームラボの猪子寿之が中心となって、最新の情報技術を使って開会式や聖火リレーや選手入場にバーチャル参加できるようにしたり、実際の選手の運動をホログラムで再現することによって、一緒に走ったり跳んだりできるなど、「誰もが参加できる」参加型オリンピックのプランを出していく予定です。
パラリンピックから人間観と公平性を再考する
――Aパートのもう一つ、「オルタナティブ・パラリンピック」とはどういうものなんでしょうか?
宇野 さきほど僕は、「ばらばらの人たちがばらばらのまま共存できるオリンピック」ということを言いましたが、その意味でパラリンピックのあり方を、今一度問い直す必要があると考えているんです。
どういうことかというと、たとえば野球やサッカーって明らかに成人男性がプレイすることを念頭にゲームルールが設計されていますよね。でも、「様々な障害を持った人たちがいて、運動が苦手な人もいて、男女がいて……」ということまで含めて、多様性を念頭に置いたスポーツのゲーム設計だってあってもいいはず。「健康な成人男性がやるもの」という近代スポーツの狭い人間観の枠を取り払って「スポーツ」というものを考えてみたい。
また、義手や義肢装具の性能は今、大きく向上しているのですが、身体的な条件から何から何まで違う人間が同じ競技に参加するとき、フェアネスはどう確保するのか、という問題が出てきています。実際に性能のいい義足とドーピングの境界線は曖昧になりつつあります。
このとき、僕たちが手がかりにするのがずばり「ゲーム」の知見です。たとえばテトリスって、野球やサッカーと違って5歳から80歳くらいまでの「バラバラな条件のプレイヤー」でもフェアに戦えるようにつくられている。他にもたとえば「ロボコン」なんかもそうで、多様なプレイヤーが参加するからそれを念頭に、ルールを工夫することでフェアに戦えるゲームを構築している。そういったゲーム設計なども参考にしながら、本当の意味で誰もが参加できるオリンピックのかたちを、最終的には2016年にスイスで開催予定の「サイバスロン」(ロボット技術を駆使した義手・義足・パワードスーツを付けて競技する義体者のオリンピック)についても言及しながら「拡張身体を持った人間を前提としたオリンピックはありえるか?」ということまで含めて議論していく予定です。
新しいライフスタイル/文化の発信地としての湾岸新都心
――続いて「B」パートは、具体的にはどんな内容になるんでしょうか。
宇野 「B」パートは「Blueprint」――2020年の東京の青写真、要するに「都市開発」のことを考えていきます。2020年五輪に際した東京の再開発で都や国がターゲットとしているのは、これまで何度も挫折してきた「湾岸新都心の開発」にほかならない。そこに対してどうポジティブな介入を図っていくのかというテーマを設定しています。もちろんそこには、僕が専門とする文化論的な要素が非常に大きな影響を及ぼすでしょう。
そもそも戦後の東京の中流文化って、新宿・渋谷をターミナル駅とする私鉄沿線に沿って西へ西へと延びていったものだったと思います。そこで想定されていたのは、「大企業に勤める正社員男性が専業主婦の妻と、子どもと一緒に郊外に住む」というライフスタイルだったわけです。
しかし現在、その傾向は一段落していて、20-30代のホワイトカラーはあまり東京西側の郊外に一軒家を買ったりしない。共働きであるために職住が近接していたほうが暮らしやすいと思っていたり、子どもを持たない夫婦だったり、もちろん独身の男女も多かったりと、ライフスタイルが非常に多様化していて、賃貸を借りる人が多くなっているからです。そもそも勤務形態がフレックスだったり、年俸制だったりするので24時間の使い方も戦後のサラリーマンとは全然違うものになってきます。そういった新しい世代のホワイトカラー、新しいクリエイティブ・クラスが都心に住むというライフスタイルが出現しているのではないかという仮定のもとに、東京の都市計画の再編を考えています。
2020年の東京オリンピックでは、東京西側のベッドタウンの起点である新宿・渋谷周辺のエリアを「ヘリテッジゾーン」、そして東京東側の湾岸部を「東京ベイゾーン」とそれぞれ位置づけて利用していく予定になっています。前者は代々木のメインスタジアムを除けば既存の施設の改修が多く、後者は新設の施設が集中します。建築学者の門脇耕三は、この会場構成プランを策定したオリンピック招致委員会の意図を「文化的側面の強い開会式/閉会式は世界によく知られた現時点の東京都心=旧市街で行い(そのためにメインスタジアムは代々木に新設し)、競技そのものは湾岸部の新設施設で開催する」というものだと説明しています。
これはなぜかというと、現時点の東京=旧市街は、地価は高騰し地権者も複雑化していて、地下から上空まで無数の権利と関係性が絡み合ってグロテスクなほどに膨張してしまっているために、都市空間の大規模な再編が難しくなっているからです。これはまさに戦後日本の「昼の世界」の写し絵であると言えると思うのですが、であるならば既存の市街地とは別の場所にまったく新しいビジョンの都市空間をつくっていくしかないと思います。
かつて64年の東京オリンピックの頃に開発された住宅地は、戦後ホワイトカラー層のライフスタイルの"雛形"になりました。ならば今度の2020年には、湾岸から「これからの日本人のライフスタイル」を象徴するようなモデル都市を提案していくことができるのではないでしょうか。たとえば五輪開催後は分譲住宅になるであろう湾岸の選手村から新しい住宅のモデルを提示していきたいし、湾岸エリアを学校選択制や外国人労働者の受け入れなどを試験的に行う特区にする、などのプランもあり得ると思います。
――これまで戦後日本のライフスタイルを象徴していた西側市街地に対置されるかたちで、東側の湾岸部にはポスト戦後の、21世紀の東京のあり方が表象されていくということですよね。
宇野 そうですね。さらに付け加えると、「グローバルシティとしての東京」の未来像も湾岸に立ち上がってくると思います。今回の五輪計画で「東京ベイゾーン」と呼ばれている湾岸部は、羽田と成田の空港群と高速道路網に支えられた高い機動力を武器に、国際競争力のあるグローバルシティの機能を一手に担うことになることが予測されます。
これも『P8』で議論したことだけれど、東京は鉄道網が発達しすぎて、かつ車が非常に使いづらいがゆえに、街と街のあいだの距離や方向感覚が掴みにくく、それがある種の閉鎖性を生んでいる。そんな東京のなかで湾岸部だけは数少ない自動車移動が有利な地域になっています。今後開発がさらに進むと、自動車で千葉や神奈川の郊外都市とより円滑に結ばれて、成田空港や羽田空港を経由して海外と直接結ばれる新たな国際都市が形成される可能性が高いと思います。
オリンピック/パラリンピックの裏で開催される文化祭計画
――続いて「C」パートの文化祭(Cultural Festival)計画ですが、これはどのような意図で企画されているものなんでしょうか。
宇野 最初にも言ったけれど、僕はそもそもオリンピック自体にはまったく興味のない人間で、正直ロンドン・オリンピックなんて一秒も見ていないんです。今でこそ健康のために運動したりはしているけど、もともとスポーツは嫌いだったし、毎回のオリンピック期間中の「感動をありがとう」モードにも嘘臭さを感じてしまう。そういった違和感を感じている人は僕だけではなく、若者を中心にたくさん存在するようになっていますよね。
僕はオリンピックに「嘘くささ」を感じる層の増加は、ある意味では社会と文化の成熟の証だと思っています。むしろ今の僕の関心は、オリンピックという、半ば役目を終えた古い祭りに「乗れない」人々を、新しい方法で巻き込んで、新しい「祭り」をつくることができないかということにあるんです。
たとえば、毎年お盆と年末に東京ビッグサイトで開催されているコミックマーケットは50万人以上を動員する世界最大級のイベントですよね。こういうイベントの存在自体がマスメディアできちんと取り上げられていないのはそもそも問題なんだけど、ここではその問題は措くとして、2020年夏のコミケは、開催時期と会場が五輪とバッティングするため、変則開催になるか、中止になる可能性が高い。
そこで提案したいのは、この事情を逆手に取ったもうひとつの五輪、「裏オリンピック」の開催です。「体育祭」である本家オリンピックに乗れない人たちのための「文化祭」ですね。
2020年8月9日(長崎原爆の日)に東京五輪は閉会する予定になっていますが、その後開催されるパラリンピックに並行してその「文化祭」をやりたいと考えています。サブカルチャーを中心としたもうひとつの祭典を開くことで、五輪目当てに来日した外国人観光客にもうひとつの「日本」をアピールできたら面白いのではないでしょうか。
――その文化祭は、湾岸の東京ビッグサイトなどの大バコが五輪期間の前後で使えないとなると、どこで開催することになるのでしょうか。
宇野 五輪の主役となるのは湾岸の新都心ですが、逆に言えば五輪期間中は旧都心は放置されるわけです。なのでその隙をついて、池袋・新宿・原宿や秋葉原などの旧市街地のほうで「文化祭」を開催することによって、この地域を盛り上げればいいかな、と。
――具体的なプログラムとしては、どのようなものを構想しているんでしょうか?
宇野 変則開催されるコミックマーケットを中核にしつつ、漫画・アニメ・ゲーム・アイドル・V系バンドや原宿系ファッションなどの見本市となるものをやりたいと思います。
他にもたとえば、「JAPAN EXPO(ジャパン・エキスポ)」という、フランス発祥の日本文化の祭典があって、最近ではどんどん人気が拡大してベルギーやアメリカなどでも開催されるようになったのですが、2020年にはぜひ本家・東京での開催を誘致したいと思っています。
その他にも、たとえばARを用いた位置ゲームが実現できたら面白いと思います、地図とキャラクターが結びついていて、水木しげるさんゆかりの調布の森に『ゲゲゲの鬼太郎』に出てくる妖怪がたくさんいたり、浜松町にピカチュウがいたりして、東京の街を歩けば歩くほど妖怪やモンスターをゲットできるという某大ヒットゲームのイメージですね。それと、これは「怪獣合法地帯」と名づけたんですけど、日替わりで夜な夜な都内のランドマークに怪獣が出現する催しも考えています。ある夜は湾岸にキングジョー、翌日は東京タワーにレッドキング、その翌日は浅草にメトロン星人、原宿にケムール人が出てきたりする。ちなみに元ネタは『ウルトラマン』第8話の「怪獣無法地帯」です。
こういった催しが本家の五輪と違うのは、決して「日本」という単位に縛られるのものではなく、「〇〇という文化が好き」という無数のコンテンツを媒介に世界中の人々が「ゆるく」つながるための実験的プロジェクトであるという点です。これはサブカルチャーが肥大した現代日本ならではの独創的な挑戦でもあるはずだと思っています。
戦後日本文化の限界を「超える」ためのオリンピック破壊計画
――最後の「D」パートは、どのようなものになるんでしょうか。
宇野 これは「オリンピック破壊(Destruction)計画」ですね。と言っても、実際に破壊するのではなく、「東京オリンピックを破壊するにはどうすればいいか」を考えたりリサーチしたりすることによって、東京という都市やオリンピック計画が抱える課題の洗い出しをしたり、セキュリティ意識を喚起したりしたいという意図を込めています。実際に「オリンピック時にテロをどう未然に防ぐか」というのは極めてシリアスな課題ですしね。
それと同時に、僕としてはこの「オリンピック破壊計画」を通して、「フィクションの可能性」についても考えたい。実は戦後日本において、ポリティカル・フィクションというものはすごく成立しづらかったと思っています。下手すると20年以上前の作品ですが、おそらく押井守監督のアニメーション映画『機動警察パトレイバー2 the Movie』(1993年)くらいまでさかのぼって考えないといけなくなる。それぐらいにはこの国でポリティカル・フィクションというものは成立しづらい。それも、成功したものの多くがアニメや特撮、つまりファンタジーの体裁を取っている。その理由も明白で、そこには戦後民主主義の問題があるわけですよね。
「徹底的に個人的であること、反国家的であるということが、結果的に公共性につながる」という戦後民主主義的なアイロニーが――個人と国家をつなぐアイロニカルな回路が――ポリティカルな想像力を良くも悪くもファンタジーの中に押し込めていった。しかし、個人的にはこの回路が衰微して来ているように思う。戦後民主主義という問題設定自体が賞味期限切れを起こしている今、このアイロニカルな回路も破綻してしまっている。だから今の日本においては個人と社会、文学と政治の断絶が決定的になっている。そういったことが、日本におけるポリティカル・フィクションの不在と結びついているのではないか。そういった前提が僕らの中にあるのですが、「じゃあそこをどうやって超えていくのか?」ということをテーマに、このパートを考えていきたいと思っています。
なので、一見おふざけ企画に見えるこの「D」パートが実は、ポップカルチャーの専門家の僕として一番ディープなことをやろうとしているのかもしれないですね。
――『PLANETS vol.9』制作後に、これらのプロジェクトはどうなっていく予定なんでしょうか?
宇野 もちろん発売後も2020年までイベントやシンポジウムや展示会、メディア露出を通じて社会に対して提案を続けようと思っていますし、現実化のために具体的に動いていくつもりです。『P9』はそのためのマニフェストという位置付けですね。
文化人や評論家や学者のような人たちが社会提案をすると「いきなり巨大な箱物をつくろう」というようなことになってしまいがちで、「こんな箱物をつくるには50億円かかるけど、どうするの?」と実現可能性をツッコまれることが多いですよね。
でも僕は、予算的にも技術的にも実現可能なものを提出するつもりです。何十億もするデカい箱物を作るような話には絶対にしないし、実際に実現可能なものを出して、2020年への提案にしていきたい。
これまであちこちで言ってきたことだけど、今のこの国は政治や社会を動かすための「OS」が古くなってしまっている。OSがアップデートされないせいで様々な弊害が出てきていて、これは政治や社会だけでなく、メディアやポップカルチャーなどの「文化」の世界でもそうだと思います。
けれど、僕たちがこうやって実現可能なプランを出して、かつ現実化していくことで初めて、文化や言論が力を持てると人々は確信できるだろうし、僕ら若い世代が「自分たちが社会のOSをアップデートして、未来を作っていける」という実感が持てる。そういう将来像を描いていきたいと思っています。
『P9』では、ここでは話していない、あっと驚くような仕掛けや企画がまだまだまだまだたくさんあるので、ぜひ楽しみにしていてください。そしてできたら僕らのプロジェクトにいろんなかたちで「参加」してほしいと思っています。発売は来年の初頭ぐらいを考えています。(了)