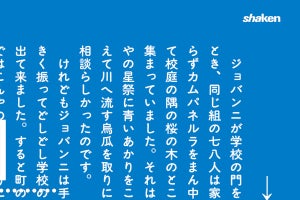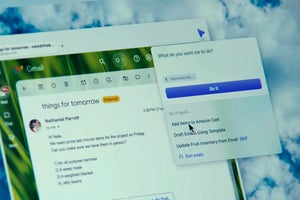フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
工場の閉鎖
森澤鉄工所の工場の様子が変わってきたのは、信夫が太田高等小学校の2年生(14歳)になったころのことだった。経営状態が悪化し、職人が1人、また1人と去っていった。3棟あった工場は、1棟ずつ壊されては、どこかに運び去られた。最後の1棟がなくなると、あとは広々としたむなしい空き地となり、白壁の塀のなかにはぽつんと母屋が残った。
父・豊次郎は、工場を閉鎖すると、土地などを売り払い、長男・勝治と二男・信夫を連れて、明石細工町 (現在の兵庫県明石市) に移った。そして小さな家を借り、残ったそうめん製造機を活用して、うどん玉の製造と卸の商売を始めた。まず、得意先の開拓から始めなくてはならない状態だった。
商売を始めた以上は、毎朝うどん玉をつくった。売れ残ったものは、その日のうちに売らなくてはならない。信夫は売れ残りを荷車に積み、「うどんの玉! うどんの玉!」と大声を上げて売り歩いた。もっとも、裕福な家庭で育った信夫には、その声を出すことがなかなかできなかった。ようやく自然に声を上げられるようになったのは、明石に来て1カ月が経ったころだ。
そのころには、商売の目処も立ち始めた。父は、兄弟だけでやっていくことができそうだと判断すると、郷里に戻ってしまった。兄は17歳、信夫は15歳だった。
町のうどん屋さんは朝10時ごろに開く。これにまにあうように、信夫たちは毎朝5時からうどん玉づくりを始めた。その日の売り上げから小麦粉を仕入れ、金が余れば食費に当てた。当初は資金も少なくて、食費を確保すると仕入れができない日もあった。兄弟は、歯を食いしばり努力した。 3年目に入るころには商売はようやく軌道に乗り、6貫 [注1] の小麦粉が入った袋を3個分も使うほどに、うどん玉が売れるようになった。
こうなると、人手不足だ。それを知った父は郷里の太田村 (兵庫県揖保郡) を引き払い、一家全員で明石に移ってきた。家族総計10人でうどん玉製造販売をおこなうこととなり、本格的に製麺業に取り組める体制が整った。
しかも、かつて父から小麦粉を融通してもらった恩義のあった増田製粉が、森澤家が一家で製麺業を始めたと知り、貨車一両分の小麦粉を送ってくれた。小麦相場の安いときに送っては、相場が上がると「上がった値段で売って、儲けてください」という。森澤家にとってはありがたい援助で、このおかげで製麺業の経営はひじょうに楽なものになった。兄弟で商売をしていたときにはまったく寸暇もなかったが、人手が増えて、時間の余裕がもてるようになった。そして信夫はいつしか考えるようになった。
「うどん玉づくりは、自分の一生の仕事ではない。なにかもっと自分に合うと感じられる、意義のある仕事をしたい」
家を飛び出して
1921年 (大正10)、20歳になる信夫は徴兵検査を受けた。家を出るよいきっかけになると思ったが、不合格になってしまった。翌1922 (大正11) 年、21歳を迎えた春に、信夫はついに心を決めて、父に打ち明けた。
「お父さん、うどん玉製造販売の商売は私の性に合いません。どうか、家を出させてください。家に仕送りはできませんが、家からの送金もいりません。なにもいらないのです」
「家を出て、なにをするつもりなのだ?」
「これから探します」
「職のあても決まっていないのに家を出るなど、許すわけにいかないだろう!」
「お父さんに許していただけなくても、出ていきます!」
父と口喧嘩になり、信夫は着のみ着のままで家を飛び出した。そして、大阪市難波立場町 (現・大阪市浪速区) で製麺業を営む伯父、西村惣一郎の家に転がりこんだ。惣一郎のもとには、信夫の伯母 (母の姉) が嫁いでいた。とにかく家を出ることが先決だったから、行くあても、やることも決まってはいなかった。信夫は伯母の家に居候をしながら、製麺業を手伝いはじめた。
やがて大阪の生活に慣れ、近所に親しいひともできた。季節はすでに秋だった。ある日信夫は、いつも訪ねては雑談する仲だった近所の大川薬店に立ち寄った。すると主人が1枚の封筒を取り出した。
「森澤くん、星製薬から歓迎会の招待状が来ているんだが、うちは行けないんだ。もし暇だったら、きみ、代わりに行ってみないか?」
ヨーロッパ旅行から帰国した星製薬の社長・星一 (ほし・はじめ)が、外遊中に見聞したことについて講演をおこなうという。星製薬は当時「東洋一」といわれる規模の製薬会社だった。[注2] そしてこのときの信夫は知るよしもないが、星一はのちのSF作家・星新一の実父である。
信夫は明石にいたころから、「社交」を一番の趣味としていた (尺八もすこし嗜んでいたが)。隣近所だけでなく、明石から神戸にまで自転車で足をのばし、いろいろなひと、なかでも社会的地位を持つひとにできるだけ会って、話を聞いた。信夫は書物を通してよりも、ひとから生きた体験談を聞くことによって知識を得、みずからを育てるタイプだった。
「趣味は社交」と自負する信夫が、この機会を逃す手はない。信夫は招待状を受け取り、参加することにした。信夫の運命の歯車が、おおきく動いた瞬間だった。
(つづく)
◆本連載は隔週更新です。
[注1] 1貫は3.75kg。よって6貫は22.5kgのこと。
[注2] 「星製薬のあゆみ」星製薬Webサイト 〈大正10年 製薬会社として東洋一と言われる規模となる〉 (2022年10月20日参照)
[注3] 同上
【おもな参考文献】
産業研究所編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代(1) 』(産業研究所、1968) pp.185-245
沢田玩治『写植に生きる 森澤信夫』(モリサワ、2000) pp.16-25
馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1974) pp.76-82
「星製薬のあゆみ」星製薬Webサイト (2022年10月20日参照)
【資料協力】株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影