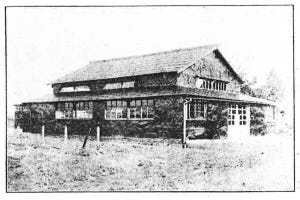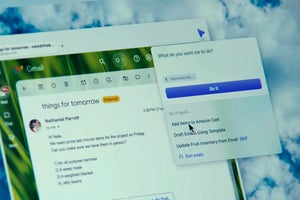フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
レンズの専門家をたずねて
邦文写真植字機の実用化のためには、それを実現しうる高精度のレンズがなくてはならない。レンズは茂吉の担当だった。1925年 ( 大正14 ) 10月に発表した試作第1号機では市販の拡大鏡のレンズをもちいたが、お話にならなかった。ついで1926年 ( 大正15 ) 夏に完成し、11月にお披露目をした試作第2号機では、おなじ市販でも顕微鏡や双眼鏡のレンズを使えばうまくいくのではないかとかんがえたが、それでもまったくの精度不足だった。茂吉と信夫のふたりは東京高等工芸学校の研究室を借り、自分たちの手で試作第2号機を完成させたものの、レンズと文字盤については満足な結果を得ることのないままだった。
-
写真植字機の植字見本。凸版複製から印字したもの。写真植字機では、レンズによって1枚の文字盤から大きさを変えて印字できる。(「邦文写真植字機遂に完成」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926 p.10より)
試作第2号機の完成を経て、茂吉の心はますます「レンズ設計」に奪われた。実のところ茂吉のレンズ研究は、試作第1号機の完成後から始まり、試作第2号機の前後も通じて続けられていた。
1925年 ( 大正14 ) 10月に試作第1号機を完成させたあと、高性能な写真用レンズを求めて、茂吉はさまざまなところを訪ねた。第2号機の試作が始まったころには、神戸時代の友人に紹介してもらい、日本光学工業 ( 現・ニコン ) の役員をつとめる藤井竜蔵のもとを訪ねた。彼は日本の光学研究の第一人者だった。
訪ねてきた茂吉に、藤井はレンズ設計部長の砂山を紹介した。茂吉は自分たちがつくろうとしている邦文写真植字機がどんな機構をもつ機械で、どんな機能を有するのか、どんなレンズが必要なのかをていねいに説明した。
「この邦文写真植字機にもちいる写真用レンズの製作をお願いしたいのです」
たのむ石井に、砂山はきっぱりと答えた。
「それはよしたほうがよいでしょう」
砂山は続けた。
「顕微鏡や望遠鏡のレンズであれば、そこまでむずかしくはありませんが、写真用レンズはそう簡単にできるものではありません。写真用レンズの製造がおこなわれていない現在の日本で、これから『写真用レンズ』と呼べるものをつくるためには、少なくとも3年の歳月と巨額の費用がかかります。採算度外視で取り組める軍関係の研究ならばともかく、個人の一発明のために写真用レンズをつくるなど、きわめて無謀な話です。あきらめたほうがよい」
茂吉は当惑した。ならば、実際にレンズを製造している現場でつくり方を聞こうと、東京・新宿淀橋にあった小西本店 ( 現・コニカ ) の工場・六桜社をたずねた。[注1]
「写真用レンズのつくり方を教えていただきたいのですが」
質問する茂吉に返ってきた答えは、
「ここでは写真機をつくっているだけで、レンズ自体は輸入したものを使っているため、つくり方はよくわかりません。調べて返事をします」
というものだった。
数日後、茂吉のもとに手紙が届いた。そこには、とうてい写真植字機には使えない、初歩的なレンズの計算公式が書かれているだけだった。茂吉は落胆した。
そうこうしているうちに、1926年 ( 大正15 ) 夏には試作第2号機が完成した。しかしレンズに関する解決策は見つからないままだった。まったく絶望的な状況だ。求めるレンズがなくては、邦文写真植字機を実用化することなどできない。レンズは印字物の品質に直接影響をおよぼす、重大な存在なのだ。だからこそ、どんなに困難な状況であっても、茂吉はどうしてもあきらめきれなかった。
どうしたらよいのか……思案をめぐらす茂吉の頭に、ふと、ある人物の顔が浮かんだ。第一高等学校、そして東京帝国大学機械工学科の同窓生、野口尚一 ( のぐち・ひさかず ) だった。[注2]
差しはじめた光
そのころ、野口は東京帝大の助教授となっていた。茂吉とは一高入学以来のつきあいだが、ほんとうに親しくなったのは東京帝大で同じ機械工学科に入学してからのことだった。のちに野口は〈 あのやさしい静かな調子で大いに世間学の講義を聞かされたものである 〉と大学時代の茂吉をふりかえっている。[注3]
大学卒業後に茂吉が神戸に就職したこともあり、野口と茂吉はしばらく会っていなかった。そんななか、本郷にある東京帝大の野口の研究室に、ある日突然、茂吉が現れた。邦文写真植字機のレンズについての相談だった。
そのときのことを、野口はこんなふうに書き残している。
〈 もうこのときには古来から発明者には避けることのできない果て知らぬ苦難の道がすでに始まっていたのだと思う。写真植字機は幾多の困難な条件をもっている。いくつかのレンズの組み合わせで一つの母字から原版の上にあらゆるサイズの写影を得る。しかもその写影の文字は輪郭がどれも同じように正しくしかも鮮鋭でなければならない。そして各部分の組み合わせとその調整とはできるかぎり簡単直截で、しかも正確でなければならない。ということはそう容易に解決のつくはずのものではなかった 〉[注4]
野口の研究室は、おなじ工学部助教授の谷安正と同室で、谷はこのときたまたま部屋におり、茂吉の話を聞いていた。谷は東京帝大物理学部出身の応用物理学者で、光学の専門家ではないものの、光学方面にひじょうに明るいひとだった。
茂吉に相談をもちかけられた野口自身は、光学上の難問題への対応がむずかしかった。そこで野口は、〈もっとも身近くもっとも信頼できる同僚の谷安正氏を紹介し、その助言を得られるよう勧めた〉。[注5]
谷は茂吉に聞いた。
「石井さん、いまお話しされていたレンズは、あなたの発明に絶対欠かせないのですか」
「このレンズがつくれるかどうかが、邦文写真植字機が実用化できるかどうかの鍵を握っているんです」
茂吉が答えると、谷は言った。
「あなたの求めるレンズをつくる方法は、ないわけではありません。現在もっとも高級なレンズといわれるドイツ・カールツァイス社のテッサーF4.5のように、七収差すべてを補正するとなると大変なことですが、石井さんが必要としているレンズは球面収差と色収差を補正すればよいのではないかとおもいます。その範囲であれば、なんとかなるのではないでしょうか」
「それは、どうやればいいのですか!?」
ふだんはポツリ、ポツリとゆっくり話す茂吉が、身を乗り出して息せきこみながら、話の先をうながした。
「もちろん、そう簡単にいくわけではありません。特定の条件をそなえたあたらしいレンズを設計するのですから、最初から計算しなくてはならない。さしあたって6本分のレンズの計算が必要ということであれば、なおさらかなりの計算量になりますから、これから3年、へたすれば4年はかかると覚悟しなくてはなりません。ぼくが設計と計算の方法をかんがえますから、実際の計算は、石井さん、あなたのほうでやってください」
谷の言葉は、茂吉にとって、ようやく差した光だった。[注6]
谷は、計算の助手も紹介してくれた。彼と同じ富山の出身で、東京物理学校 ( 現・東京理科大学 ) の学生だった柴田久三という青年だった。[注7] 茂吉は柴田を自宅の2階に住まわせ、計算をまかせた。長らく茂吉の頭を悩ませていたレンズの設計に、ようやく道がひらけはじめた。
(つづく)
[注1] 小西本店は、杉浦六三郎 ( のちに六代目杉浦六右衛門と改名 ) が1873年 ( 明治6 ) に開業した石版・写真器材の販売店。1882年 ( 明治15 ) ごろには、石版印刷機、写真暗箱 ( カメラ )、写真台紙などを国内で製造するため、下請け工場を設けた。さらに1902年 ( 明治35 )、六代目杉浦六右衛門は東京府下淀橋十二社に研究製造拠点となる六桜社 ( ろくおうしゃ ) を開業し、印画紙や乾板など感光材料の開発をおこなった。茂吉がたずねたのは、こことかんがえられる。この場所は現在、新宿中央公園となっている。なお、小西本店は、1936年 ( 昭和11 ) に株式会社小西六本店を設立。1987年 ( 昭和62 ) にコニカに社名変更。2003年 ( 平成15 )、コニカミノルタとなった。
参考:「六代杉浦六右衛門」東京工芸大学100周年特設サイト https://100th.t-kougei.ac.jp/kougeihistory/05/ (参照:2023年10月28日)
「詳しい沿革」コニカミノルタ https://www.konicaminolta.com/jp-ja/corporate/history-timeline01.html (参照:2023年10月28日)
[注2] 野口尚一 ( のぐち・ひさかず/1888-1986 ) 機械工学者。福島出身。1912年 ( 明治45 ) 東京帝国大学工科大学を卒業の後、鉄道員技手を経て、1917年 ( 大正6 ) 東京帝国大学工科大学助教授に就任。のちに同大学教授、名誉教授、日本機械学会会長。1949年、工学院大学初代学長に就任 (~1966年 )。1986年(昭和61) 97歳で逝去。
参考:工学院専門学校同窓会ウェブサイト http://www.kogakuin-senmon.com/about/history/ ( 参照:2023年11月1日 )
[注3] 野口尚一「石井君と写真植字機」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965 pp.135-139
[注4] 野口尚一「石井君と写真植字機」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965 p.136
[注5] 野口尚一「石井君と写真植字機」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965 p.136
[注6] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 pp.92-97
[注7] 柴田久三は、のちに富山県上市 ( かみいち ) 中学校校長となる。柴田久三「石井先生」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965 pp.91-94 より。
【おもな参考文献】
『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969
「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975
『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965
森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960
馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974
沢田玩治『写植に生きる 森澤信夫』モリサワ、2000
「邦文写真植字機遂に完成」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926
「発明者の幸福 石井茂吉氏語る」『印刷』1948年2月号、印刷学会出版部
「発明」編集室編「本邦印刷界に大革命を招来する 『写真印字機』の発明者 石井茂吉君に聴く」『発明』1933年12月号、帝国発明協会
橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 株/写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号、日本印刷新聞社
【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影