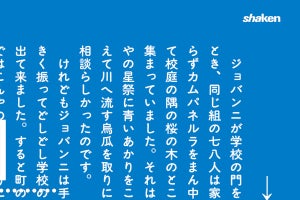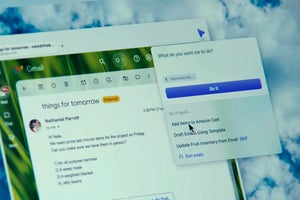フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
一歩を踏み出すために
何度となく森澤信夫に助言をもとめられるうち、邦文写真植字機の発明にしだいに関心を寄せはじめた石井茂吉。しかしそれは、企業人という安定した道ではなく、まぎれもなく茨の道である。妻とふたりの子ども、老母と弟妹……養う家族の多い茂吉には、その道に一歩を踏みだす決心がなかなかつかなかった。
仮に機械がつくれたとしても、そもそもほんとうに写真植字機は必要とされているものなのか。必要なのであれば、どんなものが望まれているのか。茂吉にとって印刷はまったく未知の世界であり、将来についての確証はなにも持っていなかった。
茂吉は信夫に、しばらく時間をもらえるよう伝えた。自分でも邦文写真植字機の実現の可能性を調べてみようとおもったのだ。ためらういっぽうで茂吉は、信夫の「一緒にやってほしい」という声に、気持ちをおおきく傾かせていた。星製薬には多くの技師がおり、出入りの機械屋もたくさんいた。にもかかわらず、信夫は自分に話をもちかけてくれたのだ。その期待に、できればこたえたかった。
自分の足で調べる
茂吉はまず、東京・丸の内の丸ビルにあったタイピスト養成所に足を運んだ。「邦文タイプライターをベースにしよう」という考えが頭のなかにあったからだが、タイプライターの機構を調べるだけでなく、その打鍵能率も調査した。
-
杉本京太が1915年 (大正4) に発明した邦文タイプライター。文字盤には、中央にひらがな、カタカナ、ゴシック仮名の3種類の文字と、約3,000の漢字が並んでいる。(『邦文タイプライター』日本書字機商會 [注1]、1915) p.11
アルファベット26文字と数字、約ものなど数十のキーで足りる欧文タイプライターと異なり、邦文のタイプライターでは、おおきな文字盤にひらがな、カタカナのほか、約3,000の漢字が並んでおり、そこから使用する文字を探して1字ずつ打たなくてはならなかったため、打鍵速度がおおきく劣っていた。このスピード差が将来じゃまにならないかということを、第一に考えたのだ。
しかし、1つ1つのキーを打つのは速くても、欧文はアルファベット数文字を組み合わせてひとつの意味をなす単語となる。いっぽう漢字は、その字自体が意味をもっている。だから同じ内容の文章を書くと、欧文のほうがはるかに字数が多くなる。茂吉が調べてみたところ、欧文で500回印字するのと同じ意味の文章を打つのに、邦文では100回の印字でよいということがわかった。
すなわち、欧文は平均5文字で一語が構成されるが、日本語は1ないし2文字で一語となるので、打鍵速度が遅くても (邦文タイプライターは毎分30字ぐらいしか打てない)、能率には実質たいした差がないのだ。それは、同じ文章を英語と日本語であらわした場合に、日本語のほうが30%以上も少ない用紙スペースで済んだことで裏づけられた。
そのうえ、欧文は一語ごとに語間スペースをとることと、ABC……とアルファベット各文字の幅に違いがあるので、行末をそろえる作業が面倒であること、行末にきた単語を途中で改行し2行にわたって打つときに、ハイフンを入れる位置は音節の区切りに限るというように、制約があることなどがマイナスとなり、実際の作業では、むしろ日本語のほうが能率的だと感じられた。
茂吉はまた、芝浦にある東京高等工芸学校 ( 現・国立千葉大学工学部 ) を訪ねた。同校にはそれぞれその分野の第一人者として知られる、写真製版の鎌田弥寿治教授 (1883-1977) 、印刷全般の伊東亮次教授 (1887-1964) がいる。両教授に写真製版、印刷の実態を教わり、印刷作業の現況について知識をもとめた。さらに、両教授の紹介で、実際に作業がおこなわれている印刷会社にも出かけていった。
そこで茂吉が知ったのは、活字組版が印刷物全体の価格のなかで、ひじょうにおおきな割合を占めていることだった。書体ごと、大きさごとに膨大な量の活字が棚に常備され、それを人の手で拾って組み上げる。印刷が終わると、組版をバラバラに解版して活字をもとのケースに戻す。多量の鉛資材と、広い面積の工場、多くの人手と時間が必要なのだ。これでは料金も高くなるはずだ、と茂吉はおもった。新聞紙上でときおり騒がれていた鉛害についても、一日中鉛にかこまれ素手で扱っていては、じゅうぶんにありうることだとうなずけた。
こうして茂吉は、1カ月以上をかけて自分の足で歩きまわり、邦文写真植字機の可能性について、たんねんに調べた。結果、「写真植字機は十分実用性があり、かつ日本の印刷産業に欠くべからざるものになる」と確信できた。
1923年 (大正12) 9月1日の関東大震災で潰れたあとに新しい家ができ、妻のいくが母から引き継いで神明屋の切り盛りをはじめて、数カ月が経っていた。いくが継いだのは経済的な理由ではなく、単にのれんを継ぐ意味だったが、茂吉がどこかに勤めることなく「写真植字機の発明」という無償の仕事に飛びこむのであれば、いくが店をやっていることは渡りに舟だった。開発費用とまではいかなくても、家族の食い扶持だけはなんとかできる。
「森澤くんと一緒に、新しい機械の発明に取り組もうとおもっている」
ある日、茂吉に腹づもりを打ち明けられた いくが異論を唱えなかったのも、そうした状況だったからだ。
茂吉は決めた。そして、「一緒にやろう」と信夫に応諾の意を伝えた。力強く視線を交わすふたりの姿が思い浮かぶ。
石井茂吉と森澤信夫のふたりはいよいよ、ともに邦文写真植字機の発明に取り組むことになった。
(つづく)
[注1] 日本書字機商會は、杉本京太が設立した会社。日本タイプライター株式会社の前身。1918年 (大正7) に改称。
【おもな参考文献】
『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)
石井茂吉「写真植字機 光線のタイプライター」『書窓』第2巻第5号 、アオイ書房、1936年7月
「この人・この仕事 写真植字機の発明と石井文字完成の功績をたたえられた 石井茂吉氏」 『実業之日本』昭和35年4月1日特大号、実業之日本社、1960
杜川生「印刷界の一大革命 活字無しで印刷出来る機械の発明」『実業之日本』大正14年12月号、実業之日本社、1925
橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号、日本印刷新聞社
倭草生「恩賜金御下賜の栄誉を担った 写真植字機の大発明完成す ―石井、森澤両氏の八年間の発明苦心物語―」『実業之日本』1931年10月号、実業之日本社、1931
「いよいよ邦文自働植字機 邦文モノタイプ完成 邦文タイプライターの発明者 杉本京太氏の苦心遂に酬ふ」『印刷雑誌』大正9年5月号 、印刷雑誌社、1920
『邦文タイプライター』日本書字機商會、1915
日本印刷学会編『印刷事典 第5版』印刷学会出版部、2002
郡山幸男「写真植字機と国字問題」『朝日新聞』1924年3月24日付、東京朝刊3面
阿部卓也『杉浦康平と写植の時代 光学技術と日本語のデザイン』慶應義塾大学出版会、2023
矢野道也「日本に於けるオフセット印刷」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926
【資料協力】
株式会社写研、株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影