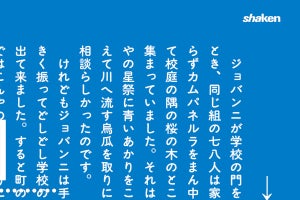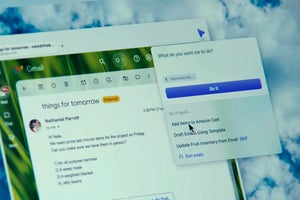フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
オーガスト・ハンターという人はいない
本連載 第19回 (2023/07/25公開)の [注4] に掲載した「オーガストハンターという人の機械」「オーガスト・ハンター機」「オーガストハンターの写植機」という記述について、誤り、または誤解を招く表現であると指摘をいただいた。ご指摘くださったのは、アドビの山本太郎氏である。
「オーガスト・ハンター」という人物は存在せず、これはEdgar Kenneth HunterとJohannes Robert Carl Augustの2人の人物を指しているのだが、日本では以前から「オーガスト・ハンター」「オーガストハンター」と、まるでひとりの人物であるかのように記述されている、との内容だった。
山本氏に教えていただいた海外の文献については現在取り寄せ中のため、まだ詳細を参照できていないのだが、たしかに海外の特許情報を調べると、2人連名の特許がいくつかヒットする ( Espacenet Patent search 2023/07/28参照 )。
また、私自身があたってきた日本の文献をあらためて読み返したところ、なぜそのようなまちがいが定着し、同様の記述が繰り返しおこなわれてきたのかが見えてきたため、はやめに訂正をすべく、現段階でわかったことを補足としてお伝えしたい。
まず、なぜ「オーガスト・ハンター」「オーガストハンター」という記述が繰り返されてきたのか。私自身も参照したのだが、これは、日本の写真植字機にかんする基礎資料の柱となる2冊、『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969) と馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1974) にこの記述があるからである。
〈オーガストハンタの写真植字機のカタログもすでに読んでおり〉『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.82)
〈写真で字を組む方法が、いまイギリスで研究されてるんだよ。オーガスト・ハンターという人の機械のことを外国の本で見たんだ〉馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1974 p.66)
※いずれも強調表示は筆者
そもそも森澤信夫が石井茂吉に見せた朝日新聞の記事、郡山幸男「写真植字機と国字問題」『朝日新聞』(1924年3月24日付、東京朝刊3面) には〈さて此写真植字機の考案が不思議にアメリカに起らず、イギリスやドイツに盛んである。そしてイギリスの考案が矢張一番早く吾等に解るのであるが、其中世間に最も多く知られて居るのはバウツリー氏のと、ハンター氏 (Hunter) のである。〉(強調表示は筆者) とハンターの名前のみ書かれているので、「オーガストハンター」という記述は、朝日新聞の記事から生まれたものではない。
ではいったい、どこから生まれたのだろうか。
朝日新聞の記事を書いた郡山幸男は、本連載ですでにふれたとおり、この当時、印刷雑誌社で『印刷雑誌』編集人をつとめていたひとである。
『印刷雑誌』では朝日新聞に郡山が寄稿した翌1925年 (大正14) 11月号 (印刷雑誌社、pp.11-13)で、「西洋の写真植字機と校正刷りだけ出来る植字機」という記事を3ページにわたり掲載している。無記名記事だが、おそらくは編集人の郡山幸男が執筆したものと推察する。この記事に「オーガスト・ハンター機」「オーガストハンター機」「オーガストハンター植字機」という表記が見られるのだ。
ただし本記事では、〈このオーガストハンター機というのは、オーガスト (J.R.C.August) とハンター (Kenneth Hunter)という二人が共力 (ママ) の発明であります。5、6年前から発表されて居ますが、今日になるまでには四度の根本的改良を施して居るそうですが、その運転の委しい (くわしい) 模様は分りかねますけれども、本社に近着の2枚の写真で大略が想像されます〉と、「オーガスト」と「ハンター」のふたりによる発明であることを明記している。
※引用文は、現代かなづかいに直した。
これが、1969年に写研が刊行した『石井茂吉と写真植字機』で「オーガストハンタ」となり、1974年にモリサワが刊行した『写真植字機五十年』では「オーガストハンターという人」になってしまった。これらの文献が執筆される際、前述の『印刷雑誌』の「オーガスト・ハンター機」「オーガストハンター機」という表記を受けて書かれた結果、誤解が生じてしまったのではないだろうか。馬渡力による「オーガストハンターという人」の記述は完全にまちがいだが、本書『写真植字機五十年』は、写真植字機の歴史を書こうとすると必ず参照される資料であるため、それが定着してしまったのだろう。
誤解を避けるために、今後は「オーガスト&ハンター写真植字機」あるいは「オーガストとハンターの写真植字機」などの表現で書かれていくべきだろう。
『ペンローズ年鑑』にオーガスト&ハンター写真植字機の記事が掲載されたのは、特許が受理されて数年後の1926年である。執筆者はW.B.Hislop、記事タイトルは「The August-Hunter Photo-Composing Machine」 (「The Penrose Annual」(the Museum of Printingによるウェブ記事) 公開の「penroseannualsindex」より。2023年5月27日参照)。
写研、モリサワ両社の書籍が本文執筆の際にこの記事を参照していたとしても、そのまま「オーガスト・ハンター写真植字機」と書かれるうちに、いつしかひとりの人物のように誤解を招きがちな (あるいはまちがった) 表記で定着してしまったとかんがえられる。
オーガスト&ハンター写真植字機のしくみ
せっかくオーガスト&ハンター写真植字機の話題になったので、『印刷雑誌』1925年 (大正14) 11月号の記事を参照して、どのような機械だったのか紹介しよう。下の写真は、同記事に掲載されていたものだ。
また、下は1929年10月15日に申請された特許明細書 ( 何度目かの改良時とおもわれる ) の図面である。
-
1929年10月15日にEdgar Kenneth Hunterが特許出願した「Photographic-printing process and apparatus therefor」([US1732049](https://patents.google.com/patent/US1732049A/en?inventor=Hunter+Edgar+Kenneth)) に掲載の図面 (一部) 。(2023年7月29日参照)
欧文タイプライターのキーみたいなものを打つと、そのうしろにある文字円筒が回転する。すると、背面に見える長い筒口 (レンズ筒とおもわれる) で、その文字が撮影されるようだ。
欧文組版においては、アルファベットの各文字によって幅が異なるうえ、1行を両端にきれいにそろえるジャスティフィケーションが必要とされることが、写真植字機の開発を困難にしていたといわれる。しかしオーガスト&ハンター写真植字機は、スペースの幅を自由に調整するしかけがあり、これから植字する文字がどれだけの寸法になるから、語と語あるいは字と字の間のスペースをどれくらいにすべきか、を即座に計算することができたという。具体的にどのようなしくみなのかまでは書かれていないが、複雑な機構が必要だったのではないかと推察する。
文字の種類が90字 (ABCの大文字小文字と記号などを加えて) あり、それが30書体、90種類の大小に変更されるため、実に24万3,000種に変化できた、と紹介されている。
これほどの機械だったが、結局は実用化あるいは普及しなかったようだ。
(つづく)
【おもな参考文献】
『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)
馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974
郡山幸男「写真植字機と国字問題」『朝日新聞』1924年3月24日付、東京朝刊3面
「西洋の写真植字機と校正刷りだけ出来る植字機」『印刷雑誌』大正14年11月号、印刷雑誌社、1925 pp.11-13
【資料協力】
株式会社写研、株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影