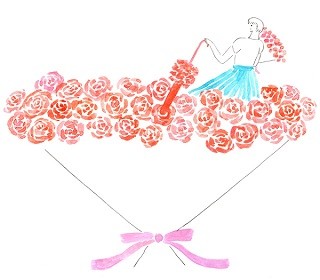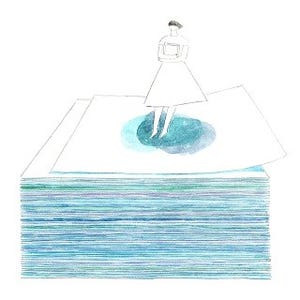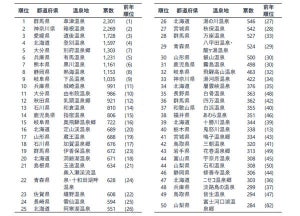愛美には、大事にしている指輪があった。
出張で行ったイタリアの、ほんのわずかな空き時間にアンティークショップで見つけたその指輪は、ベネチアンガラスでできていた。光を透かし、反射して輝くその指輪は、愛美には宝石の指輪よりずっと魅力的に見えた。
勧められるままつけてみると、左手の薬指にぴたりとおさまった。愛美は、結婚指輪でもないものをこの指につけていいものかとためらったが、そんな愛美の思惑を知ってか知らずか、店主の、少しふっくらした年配の女性は、こんなことを言う。
「ガラスの指輪は、サイズの調節がきかないの。合わなかったらそこでおしまい。どんなに気に入っても、入らないものは入らないでしょ? 気に入って、それが指にぴったりだったら、運命なのよ」
百合の刺繍の入ったストールを纏った店主にそう言われると、愛美はまるで占い師に運命を言い当てられたような気持ちになった。指につけてみると、指輪はなおさら綺麗に見えた。これを手に入れなければ後悔する、とはっきり思い、それを買うと言った。店主はわずかに微笑み、指輪を入れるための箱を用意してくれたが、愛美はこのままつけていくと言い、空の箱だけをバッグに入れた。
左手の薬指につけていても、こんなガラスの指輪、誰も結婚指輪だなんて思わないだろう。だから、ぴったりなのが左手の薬指でもかまわない。
海辺に沈む夕陽にガラスの指輪をかざし、光を楽しみながら、愛美は、小さな自由を勝ち取ったような誇らしい気分でいた。自分だけの、自分のための勲章を見つけたような気がしていた。
「結婚してるの?」
そう訊かれたのは、帰国して二ヶ月が経った頃だった。愛美の会社が扱っているタイルを使ってくれている、内装業者の太一とは、仕事上では数年の付き合いだった。仕事以外の場所で会ったこともなければ、プライベートな会話もほとんどしたことがなかったので、愛美は不意を突かれ、一瞬言葉に詰まった。
「あ、彼氏からのプレゼント?」
からかうような口調だが、太一の口元は笑っていない。つられて愛美も、堅い口調になった。
「違います。一点もので、この指にしか合わなくて」
「へぇ……。でも、そういうの自分で買う? 誰かに買ってもらったんでしょ?」
「自分で買ったんですよ」
思わず、怒ったような声になった。
太一は、「いい男」だった。愛美がそう思っていた、というわけではなく、周りの評価がそうなのだった。仕事はできるし、人望もある。女にももてるが、男性社員からも一目置かれていた。美形ではないのに、少し厚めの唇や太めの眉が表情豊かで、その顔が屈託なく笑うのを見ると、誰もが嬉しいような気持ちになる、そんな魅力があった。そんな太一が、自分なんかの指を気にしている、ということが、愛美には驚きだった。
翌週、太一に食事に誘われたときは、ただ頷いてしまった。まさか太一が、自分なんかを相手にするわけがない、という気持ちと、太一のような男に誘われて舞い上がる気持ちの両方がこみあげてきて、どういう態度でいればいいのかわからなかった。
上の空のまま、前菜の皿が空き、冷たいポタージュを飲み、メインの肉は、喉を通らないのを無理して半分なんとか平らげた。そして、帰りに当たり前のように、家に誘われた。
愛美は、太一のような男に誘われて、自分に断る理由などないように感じた。タクシーを降りて、家までの細い路地を歩いているとき、太一が不意に愛美を抱き寄せ、キスしてきた。そんなに欲されていることが夢のようだった。
太一は、自分のことが好きなのだろうか。求められ、触れられている最中は、まるで好かれているような気がした。太一は眠るとき、愛美の身体を抱きしめた。すべて、好きな女にしかしない仕草のように思えた。
朝が来て、太一がシャワーを浴びている間、愛美はベッドサイドの棚に置いていた指輪をつけようとして、その手を止めた。もし、これを忘れていけば、どうなるだろうか? 「忘れていたよ、取りにおいで」と、笑って言ってくれるだろうか。気づきもしないだろうか。
その反応で、太一がどう思っているか、わかると思った。大事な指輪。この世に二つとない指輪。だからこそ、賭ける価値がある。愛美は棚に指輪を置いた。太一から連絡は来なかった。
二年が経ち、愛美は会社の同僚から、太一が結婚するという知らせを聞いた。披露宴は先だが、もう新居に引っ越して新婚生活を送っているという。
真っ先に頭をよぎったのは、あの指輪はどうしたのか、ということだった。返す気もないのなら、捨てたのだろう。他の女のアクセサリーを置いておけるはずもない。太一の中で、自分の存在がどのようなものだったのか、改めて知る思いだった。忘れ物に気づいても、それが大事なものだと知っていても、声すらかけない程度の存在。
愛美は自分の左手を見た。ひとつも指輪はつけていない手だった。「あんな美しい指輪を捨ててしまえるような男なんて」。
そう思うと、ふっと、口元がほころんだ。どんなにいい男だったとしても、太一は、私に合う男じゃない。私のための男じゃない。好きになる価値も、賭ける価値もない男だった。捨てられてしまった、あの美しい指輪が私にそれを教えてくれたのだ、と、愛美は裸の指を見つめながら、はっきりと悟った。
<著者プロフィール>
雨宮まみ
ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)を昨年上梓。最新刊は『女の子よ銃を取れ』(平凡社)。
イラスト: 安福望