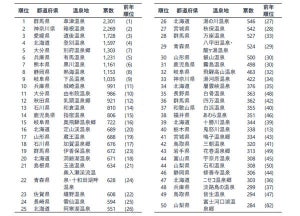高級フレンチという地獄
高級フランス料理店。黒のベストとロングエプロンを身に着けたスタッフがうやうやしく頭を下げて接客。きれいに磨かれたシルバーのカトラリーがズラーッと並び、分厚いワインリストはフランス語の連続。慣れない人からすればプレッシャーの嵐で、もうなんだか生きた心地がしないくらいの気分になるであろう。
私の高級フランス料理店デビューは銀座のRだった。まだ上京する前。前回、地元の友人と初めて東京へ遊びに来たときの話をしたが、そのときにRにも行っていた。アルバイトをして貯めたお金をはたいてランチで1万円ほどのコースを頼んだ。このレストランの前に行ったカフェで屈辱的な気分を味わっていた私たちは、「このコースを」と頼んだときのスタッフの顔が「小娘の癖にうちの店にきやがって」と思ってそうに見えるくらい、とても卑屈になっていた。
ズラーッと並んだカトラリーは基本的に外側から順に使っていけばいいのだが、あまりの緊張から前菜で一番内側のフォークとナイフを使ってしまい、皿を引きに来たスタッフが「チッ、手間かけさせんなよ」と思っているようにも見えた。
しかし、さすがは高級フレンチ。料理だけではなく、パンもおいしい。何種類もあるので色々食べたくなる。「あの、すみません、パンをください」とお願いするのだが、そのときに袖が引っかかってフォークを落としてしまった。その瞬間、「パンばっか食ってるからフォーク落とすんだよ」とスタッフが毒づいているような気がした。
なんていう極悪人なスタッフ。もうこれ以上、いじめないでください。ごめんなさい。小娘の癖にこんな高い店に来てしまった私たちが悪うございました。完全な負け犬気分で、初めての高級フレンチを満喫できないまま店を後にした。まぁ、全て私の被害妄想なのだが。
その後、フードライター&エディターという仕事に就き、本場フランスの三ツ星も取材することになった。あの頃とは違うのだ。もう高級フレンチも怖くない。
そんな折、友人と某高級フレンチで食事をすることになった。ディナーで最低2万円はする店だったが、隣の席には社会人1年目のような若いカップルが座っていた。何かの記念日で来ていたようなのだが、男性も女性もかわいそうなぐらいにガチガチに緊張していた。給仕スタッフに席へ案内され、椅子を引かれると、男性は「ああ、スミマセンスミマセン」と恐縮しきりな様子。女性は自分で椅子を引いてしまったりしてアタフタしている。
互いに高級フレンチ、いや、フランス料理店自体が初めての様子。席についても落ち着かない様子で、キョロキョロしている。一番安いコースを頼んでホッとしたところで、ワインのオーダーを聞かれている。焦った男性は「お、おすすめのものを」と言った。
……なんて危険な。普通は彼らの様子からリーズナブルなワインを勧めるだろうが、そうでない場合もある。しかもその男性は、スタッフから「こちらでいかがですか」と聞かれたときも、きちんと確認せず、「スミマセン、それでいいです、スミマセン」とオロオロしながら返事をしていた。一体どんなワインが出てくるのだろうか。恐ろしい……。
結果、出されたワインは3万円程度のワインだった。彼らは値段もよくわからぬまま、カチンコチンになりながらテイスティングしていた。友人も私もそのカップルが気になって気になって、「どうか彼らが無事に食事を済ませることができますように」と祈るような気持ちになっていた。
そこに、「パンをどうぞ」とスタッフがやってきた。先に勧められた男性は、少し悩んだ後にテーブルにセットされていたナイフ & フォークを1組持ち上げ、それを使ってパンを取り上げていた。
「えっ!? 」
ギョッとするような光景だった。スタッフに取ってもらえばいいのに……。彼はプルプルと手を震わせながら、なんとかパン皿にパンを着地させた。あまりに緊張感ある光景で、パンが無事着地したときには私たちまで「はぁ~」とため息をついた。
次は彼女のほうへスタッフが移る。彼の様子を見ていた彼女ももちろんナイフ & フォークでパンを取るわけだが、スタッフはたまらず「お取りしますよ」と言った。きっと親切心からだと思うのだが、彼女のほうは動揺してしまい、取り上げたパンをコロンッと床に落としてしまった。
「あぁっ!! 」
少し前から彼らは、こじんまりとした店内全員の注目の的である。きっとその全員が心の中でこう叫んだことだろう。大勢の人々の視線にさらされ、恥ずかしさの頂点に達してしまった彼女は「もう、いやっ!! 」といい、なんと店を飛び出してしまったのだ。
慌てて彼女を追う彼。しかし、「お客様っ」とガシッとスタッフに肩をつかまれていた。先ほどあけたおそらく分不相応である高級ワインと2人分のコース料金を請求されているのだろう。
なんという不幸な結末。他のお客はしばらくの間一言も喋らず、店内全体がどんよりとした空気に包まれていた。