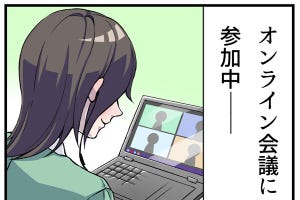パナソニックは、「テクニクス」ブランドの新製品として、DJなどを対象にした「SL-1200 Mark7 ダイレクトドライブターンテーブル」を発表した。2014年にテクニクスが復活して以来、登場が期待されていたDJ向け製品だ。これによって、テクニクスの事業が新たなフェーズに入ったことを示すことになった。
-
DJ向けに発売する「SL-1200 Mark7 ダイレクトドライブターンテーブル」
あわせて、Grand Classのネットワーク&スーパーオーディオCDプレイヤー「SL-G700」、Premium Classのダイレクトドライブターンテーブルシステム「SL-1500C」も投入する。これによりテクニクスブランドの製品は23機種にまで広がり、より多様なユーザーに音楽を楽しむ環境を提案できるようになる。
これらの新製品の発表の場となった家電見本市「CES 2019」(米ラスベガス 1月8日~11日開催)の会場で、テクニクス事業を統括する小川理子執行役員と、パナソニック アプライアンス社 テクニクス CTOの井谷哲也氏に、新製品と事業展望について聞いた。
SL-1200 MK6生産終了から8年、MK7が登場
――2018年は、テクニクスにとってどんな1年でしたか
小川:2018年春に発売した、リファレンスクラスのターンテーブル「SL-1000R」が大きな話題を集めたことがトピックでした。SL-1000Rで実現する音に関しては、技術や企画、デザイン、マーケティングなど、テクニクスに関わるすべての人たちが自信を持って、市場投入したものであり、「この音が、テクニクスの音である」ということを明確に示すことができたといえます。
テクニクスの復活を主導したパナソニックの小川理子執行役員。ジャズピアニストでもある
実際、SL-1000Rは計画の3倍という売れ行きを示しました。アナログの音を最高の環境で楽しみたいというユーザーが多かったことを感じました。最上位のアナログオーディオを実現したことで、「いままでに体験したことのない音が聴こえる」、「アナログの概念を超えた」といった声を、ユーザーの方々やディーラーの方々からいただきました。この製品に象徴されるように、2018年は、テクニクスの取り組みの蓄積がいよいよ実ったといえる1年でした。
――2018年のテクニクス事業全体を振り返って自己採点すると何点になりますか
小川:100点満点で、85点ですね。昨年からは5点ほどあがった感じです(笑)。
2018年は、SL-1000Rによって、テクニクスの音はこういうものだということを定義できましたし、自信をもってお勧めできるものが完成しました。「まずは、ここまでやりたいな」と思った音が実現できました。ただ、やることはまだまだありますから、そのあたりが15点のマイナスになります。
――今回、新たにDJ向けのダイレクトドライブターンテーブル「SL-1200 Mark7」を、2019年夏に発売すると発表しました。この製品はテクニクスにとって、どんな意味を持ちますか
小川:2014年にテクニクスの復活を発表したときに、DJの方々から嘆願書をいただくなど、登場が期待されていたのがDJ向けのダイレクトドライブターンテーブルでした。私たちも、「いつかは製品化したい」と考えていました。その「いつか」というタイミングが、いま訪れたというわけです。このSL-1200 MK7の開発をスタートしたのは2018年1月頃でしたが、このタイミングで様々な要素が揃って、今ならばDJにとって一番いいターンテーブルが投入できると判断し、製品化しました。
ダイレクトドライブのモーターを新たに開発したり、DJ向け製品として搭載する新機能を追加できたりしたことに加え、コストダウンした上でもテクニクスの音を出せるようになったことが大きな要素です。
CES 2019のテクニクス プレスカンファレンスでは、レジデントDJであるSkratch Bastid氏によるデモプレイも披露
テクニクスの再参入当初は、マーケティングの観点から、Hi-Fiオーディオとしてのブランドを確立することを優先し、DJ向け製品の投入は先送りしてきた経緯があります。しかし、この3年間の取り組みを通じて、アナログに対する揺るぎない自信ができたこと、Hi-Fiオーディオとしてのモノづくりをしっかりとやってきたからこその技術やノウハウが確立できました。
そして日本国内のDJを中心に、カナダや英国など世界中のDJの意見も聞き、操作という点での心地よさを追求し、使いやすいものを開発できる環境が整いました。加えて、新たにマレーシアの製造拠点で生産できる体制を敷いたことで、1,200ドル以下という購入しやすい価格の実現にもめどがたちました。さらに楽器店などの新たな販売ルート開拓の体制もできつつあり、DJ向けダイレクトターンテーブルを市場投入するための土壌を、あらゆる観点から整えられたことが背景にあります。
――DJ向けダイレクトドライブターンテーブルは、Hi-Fiオーディオとはモノづくりの手法が異なるのですか
小川:ターンテーブルの技術者は一緒です。そして、SL-1200 MK6の開発者も、今回の新製品の開発に携わっています。ただ、私が開発チームに言っていたのは、これは「楽器」であるということでした。楽器を使う人の声を聞くことが大切であり、それをもとに、楽器として、どんなモノづくりをすればいいのかを追求してほしいといいました。私を含めて、テクニクスの開発メンバーには楽器をやる人が多く、楽器とはどういうものかを知っていますから、この言葉の意味することについては、理解が早かったですね。
井谷:2014年のテクニクスの復活以降、ラインアップしてきたターンテーブルは16ビットのCPUを採用していましたが、今回のSL-1200 MK7では32ビットのCPUを採用しました。また、トルク・ブレーキスピードの調整機能や逆回転再生など、パフォーマンスの可能性を広げる新たな機能も搭載しています。
一方で、新生テクニクスとしての3年間に渡る蓄積も生かされています。2016年に製品化したSL-1200Gをはじめ、アナログオーディオで培ってきた技術を用いて音質を高めています。そしてボタンレイアウトやプラッターの慣性質量など、DJパフォーマンスに影響する仕様についてはSL-1200 MK6を踏襲しているので、過去の製品を使い慣れているDJでも、同様の操作感で使ってもらえます。「楽器」という位置づけですから、手触り感や使い勝手といった点はとてもこだわりました。
2010年に生産終了となったSL-1200 MK6までのシリーズ累計の販売台数は350万台を超えており、いまでも多くのDJに愛用されていますが、そうした方々にSL-1200 MK7を使ってもらったところ、「MK5やMK6に比べて音質がかなり良くなっている」という声をいただけました。
小川:製品化の経緯のなかで、型番に「DJ」と名称をつけようという話もあったのですが、最終的には、これまでの継承性を感じていただけるMK7の型番としました。DJの方々にとって、いままで使っていたものと操作が変わっては使いにくくなってしまうので、その点は継承し、そこに、テクニクスとして新たな機能を搭載しました。継承はしているが、進化をしているというのが、SL-1200 MK7です。
2019年は、音楽を愛する多くの人をファンに
――2019年は、テクニクスの復活から5年目を迎えます。どんな1年になりますか
小川:もっと裾野を広げたいですね。昨年後半には、ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン「EAH-F70N」や、ワイヤレスヘッドフォン「EAH-F50B」を投入し、ヘッドフォンのラインアップも増やしました。より多くの人にいい音で、音楽を聴いていただきたいという狙いからです。また、今回のCES 2019にあわせて、Premium Classのダイレクトドライブターンテーブルシステム「SL-1500C」と、Grand Classのネットワーク&スーパーオーディオCDプレイヤー「SL-G700」を発表し、ラインアップを拡充しました。
-
ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン「EAH-F70N」
テクニクスは、特定の人たちだけにいい音楽を楽しんでもらうのではなく、まさに、「くらしにもっと音楽を」という考え方で製品を投入していきます。現在、23機種のラインアップを、29カ国で展開しています。これをベースに、いままで以上に多くの人にテクニクス製品を届け、ファンになってもらいたいと考えています。
井谷:SL-1500Cには、コアレスダイレクトドライブモーターや高感度トーンアームなど、テクニクス独自の技術を数多く搭載しています。さらに、フォノイコライザーアンプを内蔵するとともに、Ortofon 2M Redフォノカートリッジも付属し、それでいながら、コストを抑えることにも成功しました。
フォノイコライザーを内蔵することで、配線を短くできるというメリットがありますが、一方で、回路が集中することで発生する課題を解決しなくてはならないという難しさがあります。そこで、フォノイコライザー用の専用電源については、ノイズの影響を軽減するためにモーターや制御回路用の電源から絶縁し、さらに、シールド構造により、外来ノイズの影響を抑制しています。「内蔵でありながら、こういう音まで出せるんだ」ということを言ってもらえるほど、追いこんだ作りになっています。これは大きな挑戦ではありましたが、自信を持ってお勧めできる性能を実現しました。
しかもカートリッジもついていますし、フォノ入力端子のないオーディオ機器につなげても、すぐに聴いてもらえます。これによって、アナログレコードを簡単に楽しんでもらうという新たな提案ができるようになります。
――テクニクスは、2014年に、「Rediscover Music」をメッセージに掲げ、「音楽を愛する人たちに向けたHi-Fiオーディオの実現」を目指してきました。今回のDJ向けダイレクトドライブターンテーブルの投入によって、ユーザーターゲットが広がります。このメッセージも刷新となるのでしょうか
小川:それは変わりません。DJ向けダイレクトターンテーブルも音楽を愛する人に向けた製品のひとつです。むしろ、多くの人に音楽を楽しんでもらう方法はまだまだあると考えています。
次のステップでは、パナソニックのアプライアンス社全体で取り組んでいるスマートホームとの連携などを通じて、「くらし」のなかでさりげなく音楽を楽しんでもらう取り組みや、クルマと家をつなぐなどし、様々な空間にテクニクスの世界観を広げていくことも考えたいですね。クルマは、電動化が進んでいますが、それに伴い、軽量化が課題になっています。車内に重たいスピーカーを10個搭載して高音質を実現するのではなく、音場制御をはじめとしたデジタル技術を活用することで、軽いシンプルな構成で、いい音を鳴らすといったこともできるでしょう。そこにはテクニクス独自のLAPC(Load Adaptive Phase Calibration)の利用も有効だと思っています。
私はテクニクスを復活させてから、毎年のように、「飛躍の年にしたい」と言い続けてきました。2019年も、さらに飛躍する1年にしたいですね。これまでにも、私たちなりには飛躍をしてきたつもりですが、外からみると、小さな飛躍にしかみえないかもしれません。外から見ても、大きく飛び始めたといえるように、さらに大きな飛躍をしたいと思っています。
パナソニック全社が次の100年に向かう節目
――小川執行役員は、2018年1月から、パナソニック アプライアンス社の技術担当副社長および技術本部長も兼務しています。この1年の成果はどうですか
小川:2018年は、パナソニックが会社として100周年を迎え、様々な取り組みが行われた1年でした。「くらしアップデート業」や「知能化」といった新たなキーワードも出しました。そうした節目において、技術本部では、これまで100年の家電のモノづくりを、次の100年のモノづくりにどうつなげていくかということを考えはじめました。
くらしに貢献する技術や製品、サービスのすべてが変換点を迎えていますが、最終製品が変化するためには、まずは技術から変わらなくてはいけません。しかし、100年に渡るモノづくりのプロセスを変えるのには、ものすごい力が必要になるのも確かです。
私たちは、この変化に挑戦していきます。技術本部のなかでは、変えなくてはならないという共通認識ができています。そして、変化をドライブするために開発体制も変更しました。現在、技術本部のなかに、エアコン・コールドチェーン開発センター、ホームアプライアンス開発センター、イノベーティブ・エンターテインメント開発センター、R&Dプランニングセンターの4つの開発センターを設置し、デジタルトランスフォーメーションを推進したり、ソフトウェア技術やネットワーク技術に明るい黒物家電の技術者に、白物家電の開発に取り組んでもらったりといったことをしています。
これまでは、ひとつひとつの商品に向き合って開発してきた人たちが、IoTや知能化、くらしという文脈から、横につながったり、サービスとつながったり、あるいはプラットフォームを活用した新たな開発に取り組むといったことをはじめています。
パナソニックの100周年という節目は、技術者の意識を変えるにはいいタイミングでした。そのきっかけによって、次の100周年に向けて、変革をしていくという意識が共通認識として浸透しはじめています。
――パナソニック アプライアンス社では、2021年までに、家電製品の”すべて”のカテゴリーにおいて、知能化した製品を投入する姿勢を明らかにしています
小川:もはや、ハードウェア単品での性能向上や機能強化には、限界があります。ハードのなかに詰め込もうとしていた機能、性能を、クラウドとつないでソフトウェアでアップデートし、ハードウェアを買い換えることなく、くらしに寄り添った家電へと進化させる必要があります。
家電の「知能化」においてはネット接続が前提となり、人の気持ちを察して、ちょうどいいアップデートをしていかなくてはなりません。これをすべてのカテゴリーで展開していきます。また、地域ごとに見ても差がありますから、地域×商品のマトリクスで「知能化」をする必要があります。優先度を考えながら、「知能化」に取り組んでいきます。
パナソニックが、家電業から「くらしアップデート業」に変わって行くには、「100年続いた家電をどう変えていくのか」という意識を全員が持つ必要があります。そして、世界の技術の変化の激しさや、スピードに追随しなくてはなりません。その点では、まだまだ足りないことばかりです。ダイナミックさも足りていません。世界という観点でみると、もっと変えないと変化にキャッチアップできない。今年は、よりダイナミックに、よりスピード感をもって変えていきます。